「質の高い教育をすべての人に」。これは、SDGs(持続可能な開発目標)の目標4に掲げられている重要なテーマです。この目標は、「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進すること」を目的としています。
しかし現実には、世界中で教育を受けられない子どもたちがいまだに数多く存在します。国連教育科学文化機関(UNESCO)の2023年の報告によれば、初等教育を受けていない子どもは約6,000万人、中等教育後期(15〜17歳)ではおよそ1億2,000万人が学校に通えていない状況です。また、読み書きができない成人は世界で約7億7300万人にのぼり、その多くは女性です。
教育の機会を得られない背景には、貧困、紛争、ジェンダー格差、地理的制約など、さまざまな社会課題が複雑に絡み合っています。本稿では、そうした「教育格差」の現状と、その原因・影響、そして私たちにできる取り組みについて考えていきます。
世界の教育格差の現状

国連児童基金(ユニセフ)によると、2021年の時点で約2億4,400万人の子ども(6〜17歳)が学校に通っていないと報告されています。以下は学齢別の内訳です。
初等教育(6〜11歳):約9%(約6,700万人)が未就学(2000年時点では19%)
中等教育前期(12〜14歳):約14%(約5,700万人)が未就学(2000年は25%)
中等教育後期(15〜17歳):約30%(約1億2,100万人)が未就学(2000年は48%)
とくに就学率が著しく低い国として、南スーダン(62%が未就学)、赤道ギニア(55%)、エリトリア(47%)、マリ(41%)などが挙げられます。
中でも深刻なのが、サハラ以南のアフリカ地域です。ここでは、学校に通えない子どもの数が世界最多であり、2009年から2021年の間に2,000万人も増加。2021年には約9,800万人に達しました。教育を受けられない子どもの数が増えている地域は、世界でもこの地域だけです。
さらに、学校に通えない子どもが多い国としては、インド、パキスタン、ナイジェリア、エチオピア、中国、インドネシア、タンザニア、バングラデシュ、コンゴ民主共和国、スーダンが上位に名を連ねています。
また、読み書きができない人の数も依然として高く、世界人口の約10人に1人、すなわち約7億5,000万人が識字力を持ちません。西部・中部アフリカでは、15〜24歳の若者の識字率が男性で73%、女性では60%にとどまっています。
参照元:教育 | ユニセフの主な活動分野 | 日本ユニセフ協会
教育格差が引き起こす社会問題

教育は、貧困や飢餓、健康、ジェンダーといったあらゆる社会問題の根底に関わっています。教育を受けられない子どもたちは、将来的に限られた職業にしか就くことができず、貧困の連鎖から抜け出すことが難しくなります。
教育を受けていないことで、文字の読み書きすらできない人も多く、こうした識字率の低さは、就労機会の大きな障壁となります。また、医療現場においても、医師や看護師といった専門職に必要な教育が不足していることが、開発途上国における医療水準の低下につながっています。
さらに、教育の欠如はジェンダー問題とも密接に関係しています。たとえば「女性に教育は不要」とする価値観は、児童婚や女性の経済的自立の困難さを助長します。また、性教育や衛生教育の不足は、望まぬ妊娠や病気の蔓延、さらには人口爆発や環境悪化の一因にもなっています。
このように、教育格差が引き起こす影響は多岐にわたり、その解消は持続可能な社会の実現にとって不可欠な課題です。
教育格差の原因とは?

教育格差が生まれる要因は複雑ですが、大きく以下の3つに分類されます。
1. 紛争や政情不安
戦争や内戦など、紛争が続く地域では、学校に通うこと自体が危険を伴います。武力衝突の影響で学校が避難所や軍事施設として使われることもあり、教育の機会が完全に奪われてしまうケースもあります。
また、子どもが兵士として戦闘に巻き込まれる例もあり、命の安全が最優先となる状況では教育は後回しにされます。難民として他国に避難しても、受け入れ先で十分な教育を受けられないケースも少なくありません。
2. 教育インフラの不足と予算の限界
政情不安や財政難によって、学校の建設や教員の確保が進まない国も多く存在します。教員の数が足りないだけでなく、その待遇や社会的地位が低いため、教育職に就きたいという若者が少ないという現実もあります。
また、少数民族の子どもたちは母語での教育を受けられないことも多く、言語の壁が学習を困難にしています。遠方の学校に徒歩で通わなければならず、治安の悪さや交通の危険から通学自体が困難になることもあります。
3. 貧困による教育軽視
貧困地域では、「子どもを学校に通わせる余裕がない」と考える家庭が多くあります。短期的な生活のために、子どもに水汲みや農作業、家事労働などを担わせる必要があるためです。
とくに女の子に対しては「どうせ結婚するのだから教育は不要」といった価値観が根強く、教育を受けさせる優先度が低くなっています。
このような問題は開発途上国に限ったものではありません。相対的貧困が深刻化する先進国でも見られる現象です。たとえば日本では、ひとり親世帯の約6割が相対的貧困状態にあるとされており、教育機会の格差が問題視されています。
コロナ禍でさらに広がった教育格差
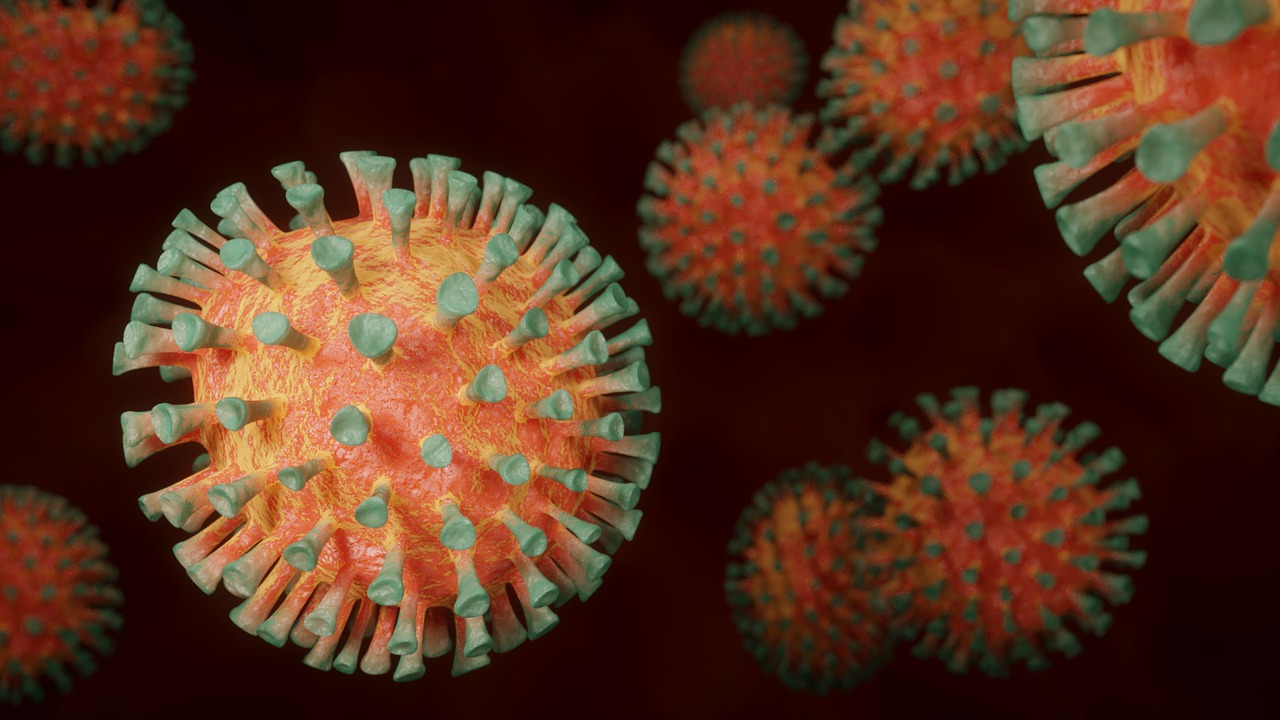
新型コロナウイルスの世界的流行は、教育格差をさらに深刻化させました。世界各国で学校閉鎖が相次ぎ、ピーク時には15億人、つまり世界の子どもや若者の約91%が通学できない状況に直面しました。
代替措置としてオンライン授業が導入された国も多くありますが、インターネット環境や端末が整っていない地域では学習の継続が困難でした。ユニセフによると、約4,700万人の子どもたちがオンライン授業から完全に取り残されたと推定されています。
このような「デジタル・ディバイド(情報格差)」は、教育の格差を拡大させる新たな要因となっています。
世界の教育格差に対して私たちができる対策
 教育格差の問題は、遠い世界の出来事のように感じられるかもしれませんが、私たち一人ひとりにもできることはあります。まずは、現状を正しく理解し、自分にできる行動を起こすことが重要です。
教育格差の問題は、遠い世界の出来事のように感じられるかもしれませんが、私たち一人ひとりにもできることはあります。まずは、現状を正しく理解し、自分にできる行動を起こすことが重要です。
1. 世界の現状を知ることから始める
SDGsの目標4「質の高い教育をすべての人に」の実現には、まず問題を知ることが第一歩です。インターネットや書籍、報道を通じて教育格差に関する正確な情報に触れ、自分自身の理解を深めましょう。このような情報にアクセスすること自体が、支援の入口となります。
2. 教育支援に取り組む団体を知る
教育格差の解消に向けて、国内外のさまざまな団体が取り組みを行っています。信頼できる団体の活動を知り、支援の輪に加わることも大きな力となります。
・日本ユニセフ協会
世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。最も支援の届きにくい地域の子供たちを対象に、保健、栄養、水と衛星、教育などの支援活動を実施しています。
参照元:日本ユニセフ協会
・日本ユネスコ協会
UNESCO(国際連合教育科学文化機関)憲章の理念に基づき、平和な世界の構築と持続可能な社会の推進をミッションとして掲げるNGOです。非識字者や貧困層の人たちが多いアジアで、誰もが教育の機会を得られるよう「世界寺子屋運動」の取り組みを行っています。
参照元:日本ユネスコ協会
・JICA(独立行政法人国際協力機構)
日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っています。JICAは、日本政府の教育戦略(「平和と成長のための学びの戦略」)に基づき、2030年までのSDG4の達成に向けて取り組んでいます。
参照元:教育 – JICA(独立行政法人国際協力機構)
参照元:アフリカにおけるJICAの基礎教育協力 – JICA(独立行政法人国際協力機構)
3. 支援を「行動」で示す
知識を得たうえで、次のステップとして寄付やボランティア活動に参加する方法があります。金銭的な寄付に限らず、情報を広める、イベントに参加する、自分のSNSで発信するなど、さまざまな形で支援は可能です。
たとえば、「井戸を掘る支援」は一見教育と関係なさそうですが、水汲みという労働から解放された子どもが学校に通えるようになるという意味で、教育支援につながります。
まとめ|世界の教育格差の解消に向けて、まず「知ること」から

教育は、人が自らの可能性を切り開くための基本的な権利です。しかし、世界にはその機会さえ奪われている子どもたちが今も大勢います。
教育格差の背景には、貧困、紛争、文化的慣習、ジェンダーなど多くの課題があり、複雑に絡み合っています。その解決には、国際的な連携と、草の根レベルでの支援の両輪が必要です。
まずは、「知ること」から始めましょう。そして、自分が共感できる団体や活動を見つけ、できる範囲で支援の一歩を踏み出してみてください。それが、世界の誰かの未来を変える力となります。






