地球温暖化が進む現代、私たちが直面するリスクは環境問題だけではありません。気候変動とサイバー攻撃という、一見無関係に思える2つの脅威が組み合わさることで、これまでにない複雑で深刻な問題が生まれています。企業や個人にとって、この新しいリスクを理解し、適切に備えることがますます重要になってきているのです。
この記事で学べるポイント
- 気候変動とサイバーリスクがどのように関連し合うかの基本的な仕組み
- 実際に発生している気候関連サイバー攻撃の具体的な事例と影響
- 企業や個人が取るべき効果的な対策と準備方法
気候関連サイバーリスクとは何か

気候関連サイバーリスクとは、気候変動がサイバーセキュリティに与える様々な脅威を総称した概念です。これは単純に「台風でサーバーが壊れる」といった物理的な問題だけではなく、気候変動に関連する複数の要因がサイバー攻撃のリスクを高める現象を指しています。
近年、世界各国でハリケーンや洪水、山火事などの極端な気象現象が頻発していますが、こうした災害の発生時には必ずと言っていいほど、詐欺メールやフィッシング攻撃などのサイバー犯罪も急増します。災害に混乱した人々や組織の隙を突いて、悪意ある攻撃者がサイバー空間で活動を活発化させるのです。
基本的な概念と背景
このリスクが注目されるようになった背景には、私たちの社会がデジタル化とグリーン化を同時に進めていることがあります。企業は環境に配慮した経営を求められる一方で、業務のデジタル化も急速に推進しています。この2つの潮流が交わる部分に、新たなセキュリティの盲点が生まれているのです。
例えば、電力会社が再生可能エネルギーシステムを導入する際、風力発電や太陽光発電の設備はインターネットに接続されて遠隔監視されることが多くなります。これらの新しいシステムは、従来の発電設備よりもサイバー攻撃の標的になりやすいという特徴があります。2021年には、世界最大級の風力発電機メーカーであるヴェスタス社がサイバー攻撃を受け、複数の拠点でITシステムの停止を余儀なくされました。
従来のリスク管理との違い
従来のリスク管理では、自然災害とサイバー攻撃は別々の問題として扱われてきました。しかし気候関連サイバーリスクでは、この2つが相互に関連し合い、複合的な被害をもたらす可能性があります。
最も大きな違いは、リスクの「連鎖性」です。例えば、台風により停電が発生すると、バックアップ電源に切り替わったシステムが平常時とは異なる動作をすることがあります。この隙を突いてサイバー攻撃が仕掛けられると、電力復旧後も長期間にわたってシステムの機能不全が続く可能性があります。
また、攻撃者の動機も複雑化しています。従来は金銭目的や愉快犯的な動機が多かったサイバー攻撃ですが、気候関連の場合は環境活動家による抗議活動や、気候変動による地政学的な対立に起因する国家レベルの攻撃も含まれます。
気候変動がサイバーリスクを高める4つの仕組み

気候変動がサイバーリスクを増大させる仕組みは、主に4つの経路に分けることができます。これらは単独で作用することもあれば、複数が同時に発生して相乗効果を生み出すこともあります。
極端気象による物理的インフラへの影響
最も分かりやすいのが、台風や洪水、熱波などの極端気象がITインフラに与える直接的な被害です。データセンターの浸水、通信ケーブルの切断、冷却システムの故障などが発生すると、本来であれば堅牢なセキュリティシステムに脆弱性が生まれます。
2017年のハリケーン・ハーベイでは、テキサス州で大規模な洪水が発生しました。この混乱に乗じて、多くのフィッシング攻撃や偽の義援金サイトが立ち上げられ、被災者や支援者を標的とした詐欺が横行しました。物理的な被害だけでなく、社会の混乱がサイバー犯罪の温床となったのです。
災害時の混乱を狙ったサイバー攻撃の増加
自然災害が発生すると、人々は情報収集や安否確認のためにインターネットを頻繁に利用するようになります。この心理状態につけ込んで、災害に関連する偽情報や悪意あるリンクを含むメッセージが大量に配信されます。
新型コロナウイルスのパンデミック時にも同様の現象が観察されました。ワクチン情報や給付金に関する偽サイトが多数作成され、混乱した人々から個人情報や金銭を騙し取る事件が世界各地で発生しました。気候関連の災害でも、救援情報や避難情報を装った攻撃が頻繁に行われています。
グリーンテクノロジー導入に伴う新たな脆弱性
環境対策のために導入される新しい技術には、セキュリティ面での課題が潜んでいることがあります。IoTデバイスを使った省エネシステムや、AIを活用した環境モニタリングシステムなど、急速に普及している技術の中には、十分なセキュリティ検証が行われていないものも存在します。
スマートグリッド(次世代電力網)はその代表例です。電力の需要と供給を効率的に管理するため、多数のセンサーや制御装置がネットワークで接続されていますが、これらの機器の一部に脆弱性があると、電力インフラ全体が攻撃の対象となる可能性があります。
地政学的不安定化による国家レベルの脅威
気候変動は水資源の枯渇や農業生産性の低下を通じて、国家間の緊張を高める要因となっています。こうした地政学的な対立は、サイバー空間にも波及し、国家が支援するサイバー攻撃の増加につながっています。
特に、エネルギーインフラや食料供給システムを標的とした攻撃が懸念されています。2021年のコロニアル・パイプライン攻撃では、米国東海岸への燃料供給が一時停止し、経済と社会に深刻な影響を与えました。このような攻撃が気候変動による資源不足と組み合わさることで、より深刻な被害をもたらす可能性があります。
実際に発生した事例から学ぶリスクの現実性
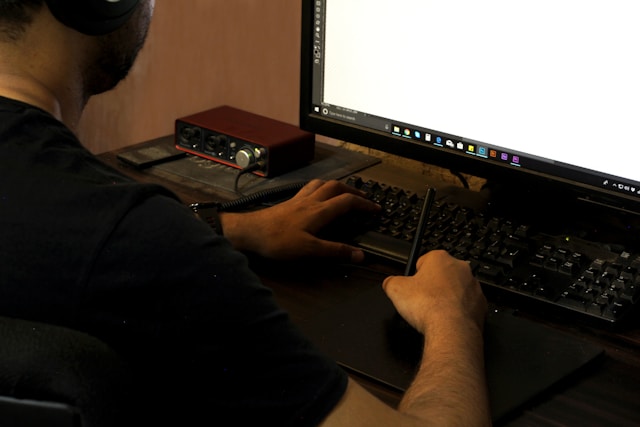
気候関連サイバーリスクは理論的な話ではなく、すでに世界各地で現実の被害をもたらしています。過去の事例を詳しく分析することで、このリスクがどのような形で現れ、どのような被害をもたらすのかを具体的に理解することができます。
自然災害とサイバー攻撃の同時発生事例
2011年の東日本大震災では、日本が未曾有の自然災害に対応している最中に、海外からのサイバー攻撃が急増しました。震災の混乱に乗じて、義援金詐欺を装ったフィッシングメール、偽の安否確認サイト、放射線情報を装った悪意あるソフトウェアの配布などが確認されています。
より最近の例では、2018年から2020年にかけてカリフォルニア州で発生した大規模山火事の期間中に、山火事救援活動を装った詐欺サイトが多数立ち上げられました。これらのサイトは、被災者への寄付を募ると称して個人情報やクレジットカード情報を盗取していました。FBI(米連邦捜査局)は、こうした詐欺活動について警告を発し、災害時には特にサイバー犯罪に注意するよう呼びかけています。
ハリケーン・カトリーナ(2005年)の際にも同様の現象が観察されましたが、当時と比較してインターネットの普及が進んだ現在では、サイバー攻撃の規模と影響がはるかに大きくなっています。ソーシャルメディアの発達により、偽情報の拡散速度も格段に向上しており、短時間で多くの人々が被害に遭うリスクが高まっています。
エネルギーインフラを狙った攻撃事例
エネルギー分野は気候関連サイバーリスクが最も顕著に現れる領域の一つです。2021年に発生したヴィアサット社への攻撃は、その深刻さを物語る事例として注目されました。
ヴィアサット社は衛星通信サービスを提供する企業ですが、同社への攻撃により、ドイツの約6,000基の風力発電機が正常に機能しなくなりました。これらの風力発電機は、発電量の監視や制御のために衛星通信を利用していたため、通信が遮断されると遠隔操作ができなくなったのです。この事件により、ヨーロッパ各地で数千の企業が影響を受け、再生可能エネルギーへの依存度が高い地域では電力供給に深刻な問題が生じました。
また、テキサス州で2021年に発生した大寒波の際には、電力不足により多くの家庭や企業が停電に見舞われましたが、この混乱期にも電力復旧を装った詐欺メールや偽のエネルギー会社サイトが多数確認されています。停電により通常のセキュリティシステムが機能せず、普段であれば検出できたはずの攻撃を見逃してしまった組織も少なくありませんでした。
企業や組織への具体的な影響

気候関連サイバーリスクが企業や組織に与える影響は、従来のサイバー攻撃よりも複雑で長期間にわたることが特徴です。単純な金銭的損失だけでなく、事業の根幹を揺るがすような深刻な影響をもたらす可能性があります。
事業継続性への脅威
最も深刻な影響の一つが、事業継続性(Business Continuity)への脅威です。気候関連のサイバー攻撃は、自然災害による物理的な被害と同時に発生することが多いため、復旧作業が非常に困難になります。
例えば、台風により本社ビルが浸水した状況で、同時にランサムウェア攻撃を受けた場合を考えてみましょう。通常であれば、バックアップシステムを使って業務を継続できるはずですが、物理的な被害により主要なITシステムにアクセスできない状況では、サイバー攻撃への対応も大幅に遅れてしまいます。
製造業では、工場の操業停止が長期化するリスクがあります。スマートファクトリー(IoTや人工知能を活用した次世代工場)を導入している企業では、生産ラインの多くがネットワークで接続されているため、サイバー攻撃により全体の生産が停止する可能性があります。特に、自動車産業のように部品の調達が複雑に絡み合っている業界では、一つの工場の停止が業界全体に波及することもあります。
小売業界では、決済システムの停止により売上機会を大きく失うリスクがあります。災害により実店舗での営業が困難になった際に、オンライン販売に頼らざるを得ない状況で電子商取引システムが攻撃を受けると、収入源を完全に絶たれてしまう可能性があります。
経済的損失と社会的責任
気候関連サイバーリスクによる経済的損失は、従来のサイバー攻撃と比較して桁違いに大きくなる可能性があります。これは、攻撃のタイミングが企業にとって最も脆弱な時期と重なることが多いためです。
直接的な損失としては、システムの復旧費用、事業中断による売上減少、顧客データの漏えいに対する賠償金などが挙げられます。しかし、より深刻なのは間接的な損失です。企業の危機対応能力に対する信頼失墜、株価の下落、顧客離れ、取引先との関係悪化などが長期間にわたって企業の経営を圧迫します。
特に注目すべきは、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からの評価への影響です。近年、投資家は企業の財務実績だけでなく、環境問題への取り組みや社会的責任、経営の透明性を重視するようになっています。気候関連サイバーリスクへの対応が不十分な企業は、投資家からの評価を下げ、資金調達にも支障をきたす可能性があります。
また、顧客や地域社会からの信頼も重要な要素です。災害時に十分なセキュリティ対策を講じていなかった企業は、社会的責任を果たしていないとみなされ、長期的なブランド価値の毀損につながるリスクがあります。特に、エネルギーや水道、通信などの社会インフラを担う企業では、サイバー攻撃による サービス停止が社会全体に大きな影響を与えるため、その責任はより重大です。
効果的な対策と準備方法

気候関連サイバーリスクに対抗するためには、従来のサイバーセキュリティ対策に加えて、気候変動の特性を考慮した包括的なアプローチが必要です。単発的な対策ではなく、長期的な視点に立った体系的な取り組みが求められます。
リスク評価と計画策定のポイント
効果的な対策の第一歩は、自社が直面するリスクを正確に把握することです。気候関連サイバーリスクの評価では、従来のリスク分析に気候変動の要素を組み込む必要があります。
まず重要なのは、自社の事業拠点や重要なITシステムが設置されている地域の気候リスクを把握することです。洪水や台風のハザードマップを確認し、過去の災害履歴を調査することで、どの時期にどのような自然災害が発生しやすいかを予測できます。この情報を基に、災害発生時に予想されるサイバー攻撃のパターンを想定し、対応計画を策定します。
リスク評価では、単一の脅威だけでなく、複数のリスクが同時に発生する「複合災害」のシナリオも検討することが重要です。例えば、台風による停電とランサムウェア攻撃が同時に発生した場合、復旧にどの程度の時間がかかるか、代替手段はあるか、顧客への影響をどう最小限に抑えるかなどを具体的に計画しておく必要があります。
また、サプライチェーン全体のリスクも考慮する必要があります。自社のセキュリティが万全でも、重要な取引先や部品供給者がサイバー攻撃を受ければ、事業に大きな影響が及ぶ可能性があります。
技術的対策と組織的対策
技術的な対策としては、まず基本的なサイバーセキュリティの強化が不可欠です。ファイアウォールの設定、ウイルス対策ソフトウェアの導入、定期的なシステムアップデートの実施など、従来から重要とされている対策を確実に実行することが基盤となります。
特に重要なのは、災害時でも機能するバックアップシステムの構築です。データのバックアップは地理的に離れた複数の拠点に保存し、主要なシステムが被害を受けても業務を継続できる体制を整える必要があります。クラウドサービスを活用する場合は、サービス提供者のセキュリティ対策や災害対応能力も十分に検証することが大切です。
組織的な対策では、従業員の教育と訓練が極めて重要です。災害時には通常とは異なる状況下で判断を迫られることが多く、平時であれば見抜けるフィッシングメールなどの攻撃に引っかかってしまうリスクが高まります。定期的なセキュリティ研修に加えて、災害を想定した実践的な訓練を実施することで、従業員の対応能力を向上させることができます。
また、インシデント対応チームの設置と権限の明確化も不可欠です。災害とサイバー攻撃が同時に発生した場合、迅速な意思決定と行動が被害の拡大を防ぐ鍵となります。事前に対応手順を定め、責任者の連絡先を複数のルートで確保しておくことが重要です。
関係機関との連携の重要性
気候関連サイバーリスクへの対応は、一つの組織だけでは限界があります。政府機関、業界団体、他の企業、セキュリティ専門機関との連携を通じて、より効果的な対策を講じることが可能になります。
政府や警察機関との連携では、最新の脅威情報の共有や、攻撃を受けた場合の報告体制の確立が重要です。日本では、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)や警察庁、総務省などが関連する情報提供や支援を行っています。これらの機関が発信する警報や注意喚起を定期的にチェックし、自社の対策に反映することが大切です。
業界内での情報共有も効果的です。同業他社との間で脅威情報を共有し、攻撃手法の傾向や効果的な対策について情報交換することで、業界全体のセキュリティレベルを向上させることができます。特に、エネルギーや金融、インフラ関連の業界では、業界団体が中心となってセキュリティ対策の標準化や情報共有の仕組みづくりが進められています。
今後の展望と重要性

気候関連サイバーリスクは、今後さらに深刻化することが予想されています。気候変動の進行とデジタル化の加速により、この問題の重要性はますます高まっていくでしょう。
規制動向と企業の対応責任
世界各国の政府は、気候関連サイバーリスクへの対応を法的な義務として位置づける動きを見せています。欧州連合(EU)では、デジタルオペレーショナルレジリエンス法(DORA)が2025年1月から施行され、金融機関に対してサイバーリスク管理の強化が義務付けられます。
米国では、証券取引委員会(SEC)がサイバーセキュリティに関する開示規則を強化し、上場企業に対してサイバー攻撃を受けた場合の迅速な報告を求めています。これらの規制は、単なるサイバーセキュリティだけでなく、気候変動リスクとの関連性も考慮した包括的な対応を求める方向に発展しています。
日本でも、金融庁が気候変動リスクに関するシナリオ分析の実施を推進しており、その中でサイバーリスクも重要な要素として位置づけられています。企業は法的な要求に応えるだけでなく、ステークホルダーからの期待に応えるためにも、積極的な取り組みが求められています。
持続可能な社会実現への貢献
気候関連サイバーリスクへの適切な対応は、単なるリスク管理を超えて、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みでもあります。安全で信頼できるデジタルインフラの構築は、再生可能エネルギーの普及やスマートシティの発展を支える基盤となるからです。
企業が気候関連サイバーリスクに真摯に取り組むことで、社会全体のレジリエンス(回復力)向上に貢献することができます。一つの企業の取り組みが業界全体の標準を押し上げ、最終的には社会インフラの安全性向上につながるのです。
また、この分野への積極的な投資は、新たなビジネス機会の創出にもつながります。気候関連サイバーリスクに対応するための技術やサービスの需要は今後ますます高まることが予想されており、この分野で競争優位を築くことができれば、長期的な成長の基盤となるでしょう。
まとめ

気候関連サイバーリスクは、気候変動とデジタル化が同時に進行する現代社会における新たな脅威です。このリスクは従来の単純な自然災害やサイバー攻撃とは異なり、複数の要因が相互に影響し合って深刻な被害をもたらす可能性があります。
しかし、適切な準備と対策を講じることで、このリスクを管理し、さらには競争優位の源泉として活用することも可能です。重要なのは、この問題を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、長期的な視点に立った包括的な取り組みを推進することです。
企業や個人一人ひとりが気候関連サイバーリスクの存在を認識し、それぞれの立場でできる対策を実行することが、レジリエントで持続可能な社会の実現につながるのです。
参照元
・金融庁「気候変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会 課題と関係者の今後の取組への期待」の公表について https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20240709-1.html
・KPMG Japan「ESGにおけるサイバーセキュリティ」 https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/09/cyber-security-esg.html
・Everbridge「Double trouble: When climate change and cyber crime collide」 https://www.everbridge.com/blog/double-trouble-when-climate-change-and-cyber-crime-collide/
・PwC Japan「なぜESG格付けにおいてサイバーセキュリティの重要性が高まっているのか」 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/esg-articles01.html
・The Stimson Center「Cyber and Climate Threats: Shared Risks, Resilience, and Response Strategies」 https://www.stimson.org/2025/cyber-and-climate-threats-shared-risks-resilience-and-response-strategies/
・TechTarget「Where climate change and cyber attacks intersect」 https://www.techtarget.com/searchsecurity/feature/Where-climate-change-and-cyber-attacks-intersect
・World Economic Forum「Why climate change and cyber risks will shape the next decade」 https://www.weforum.org/stories/2021/10/the-next-decade-will-be-defined-by-climate-change-and-cyber-risks/





