私たちが普段使っている紙製品や木製品には、環境に配慮して作られた証である「森林認証マーク」が付いているものがあります。このマークは、森林の破壊を防ぎ、地球環境を守るための重要な取り組みを示しています。森林認証制度は、持続可能な森林管理を促進し、消費者が環境に優しい製品を選択できるようにする国際的な仕組みです。
この記事で学べるポイント
- 森林認証制度の基本的な仕組みと目的
- FSC認証とPEFC認証の特徴と違い
- 認証製品を選ぶことで得られる環境・社会への効果
森林認証制度とは何か?環境保護のための取り組み
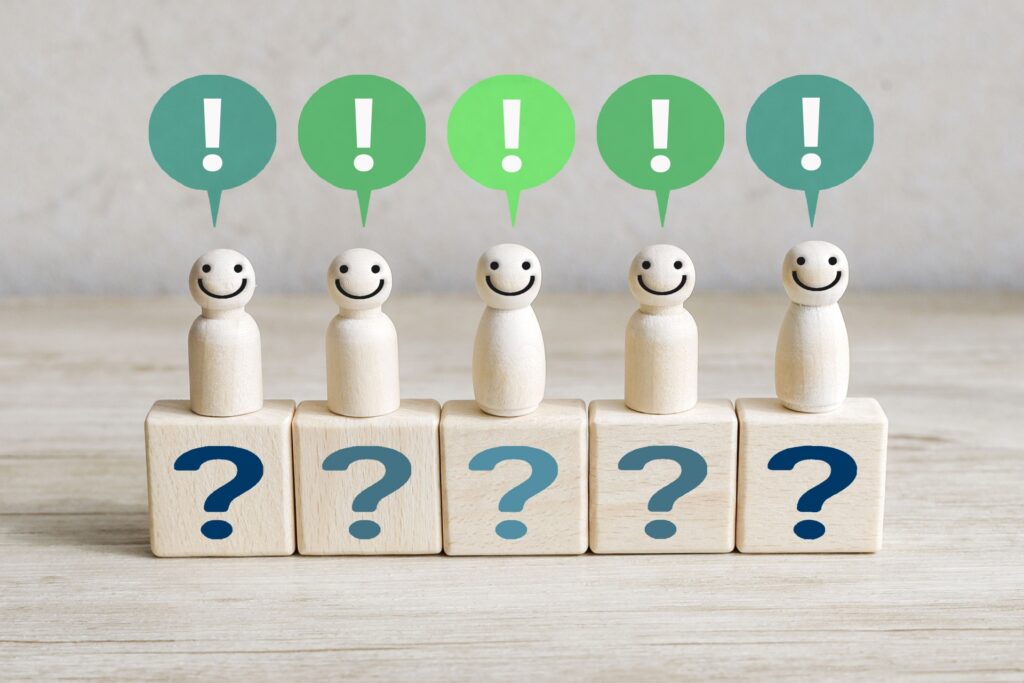
森林認証制度とは、持続可能な森林経営を促進するための国際的な制度です。独立した第三者機関が、森林の管理や経営組織の持続性、環境保全への配慮について厳格な基準で審査・認証を行います。
この制度の最大の目的は、森林の生物多様性を保護しながら、地域社会や労働者の権利を守り、経済的にも持続可能な森林利用を実現することです。認証を受けた森林から産出された木材や紙製品には認証マークが付けられ、消費者は一目でその製品が環境に配慮して作られたものであることがわかります。
森林認証制度は「森と人を結ぶ」役割を果たし、ポジティブな循環型社会の構築を目指しています。消費者が認証製品を選択することで、責任ある森林管理を行う生産者を経済的に支援し、それが世界の森林保全につながる仕組みとなっています。
世界の森林の現状と保護の必要性
現在、世界では深刻な森林破壊が進んでいます。国連の報告によると、2015年から2020年の間に世界の森林面積は平均年間1020万ヘクタールずつ減少しており、これはサッカー場約2.2秒毎に1面分の森林が失われている計算になります。
特に熱帯地域での森林破壊が深刻化しており、違法伐採や無計画な森林開発が大きな問題となっています。森林は木材や紙の原材料を提供するだけでなく、野生生物の生息地、二酸化炭素の吸収、水質保全、土砂災害の防止など、私たちの生活に欠かせない多くの機能を担っています。
このような状況を受けて、1990年代から森林の持続可能な利用を確保するための国際的な取り組みが活発化し、森林認証制度の開発と普及が進められてきました。現在では世界中で森林認証制度が導入され、責任ある森林管理の促進に重要な役割を果たしています。
第三者機関による審査・認証の仕組み
森林認証制度の信頼性は、独立した第三者機関による厳格な審査体制によって支えられています。この審査は、森林の所有者や木材・木製品の生産者・流通業者とは利害関係のない独立した認証機関が実施します。
審査では、書類検査、現地調査、関係者へのヒアリングなどを通じて、定められた基準を満たしているかどうかを詳細に検証します。認証を取得した後も、定期的な監査によって継続的に基準の遵守状況が確認され、問題が発見された場合には認証の一時停止や取り消しなどの措置が取られます。
この第三者認証システムにより、消費者は認証マークが付いた製品について、客観的で信頼性の高い評価に基づいて環境に配慮された製品であることを確信できます。認証機関自体も国際的な認定機関から認定を受けており、審査の品質と独立性が保証されています。
FSC認証の特徴と仕組み

FSC(Forest Stewardship Council:森林管理協議会)認証は、1993年にWWF(世界自然保護基金)を中心として設立された国際的な森林認証制度です。世界で最も広く普及している森林認証制度の一つで、現在82か国で約2億3000万ヘクタールの森林が認証を受けています。
FSC認証は、環境保全、社会的利益、経済的持続可能性の3つの要素をバランス良く満たす「責任ある森林管理」を推進することを目的としています。この認証制度は、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を保護しながら、経済的にも継続可能な森林利用を実現することを目指しています。
FSC認証製品を購入することは、世界の森林保全を応援することに直結します。消費者がFSCマークの付いた製品を選ぶことで、責任ある森林管理を行う生産者に経済的利益が還元され、持続可能な森林経営の拡大につながる仕組みとなっています。
世界共通の基準で審査される国際制度
FSC認証の大きな特徴は、世界共通の統一された基準で審査が行われることです。FSCでは「森林管理の10原則と70の基準」という明確な規格が定められており、世界中どこでも同じ水準で森林管理が評価されます。
10の原則には、法律や国際的な取り決めの遵守、労働者の権利と安全の確保、地域社会との関係、生物多様性の保全、森林の生態系サービスの維持などが含まれています。これらの原則の下に、さらに詳細な70の基準と約200の指標が設けられており、包括的で厳格な審査が実施されます。
この世界共通基準により、FSC認証は国際的に高い信頼性と一貫性を保っています。どの国や地域でFSC認証を取得した製品であっても、同じレベルの環境・社会配慮がなされていることが保証されており、国際取引において非常に重要な意味を持っています。
FM認証とCoC認証の2つの認証体系
FSC認証は、FM(Forest Management:森林管理)認証とCoC(Chain of Custody:加工流通過程の管理)認証という2つの認証から構成されています。この2つの認証の連鎖により、森林から最終製品まで一貫した管理体制が確保されます。
FM認証は、森林そのものの管理を認証する制度です。木材の持続可能な供給、水資源の保全、生物の生息環境の提供など、責任ある森林利用を確保するための認証で、森林所有者や林業事業者が取得対象となります。日本国内では約42万ヘクタールの森林がFM認証を取得しています。
一方、CoC認証は、FM認証を受けた森林から産出された木材が製品になるまでの加工・流通過程を認証する制度です。製材業者、製紙会社、印刷業者、家具メーカーなど、認証材を取り扱うすべての事業者が対象となります。この認証により、認証材と非認証材が混在することなく、適切に分別管理されていることが保証されます。FSC認証製品にマークを付けるためには、必ずCoC認証の取得が必要です。
PEFC認証の特徴と仕組み

PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes:森林認証制度相互承認プログラム)は、1999年にヨーロッパ11か国によって設立された森林認証制度です。当初は「汎欧州森林認証制度」として発足しましたが、2003年に現在の名称に改称され、世界各国の森林認証制度との相互承認を行う国際的な組織として発展しました。
PEFCの最大の特徴は、各国で独立して運営されている森林認証制度を国際的に共通するものとして承認する仕組みにあります。世界統一の規格は設けず、各国の森林の実情や社会情勢に応じて策定された認証制度を、PEFCが定める要求事項との適合性を審査した上で相互承認しています。
現在、PEFCには世界56か国の森林認証制度が加盟しており、認証森林面積は約3億2800万ヘクタールと、世界で最大規模の森林認証制度となっています。この規模の大きさは、各国の地域性を尊重しながら国際的な統一性を保つというPEFCのアプローチが、多くの国々に受け入れられていることを示しています。
各国の認証制度を相互承認する国際プログラム
PEFCは、FSCのような世界共通の単一基準ではなく、「持続可能な森林管理のための政府間プロセス基準」を採用することを基本としています。この政府間プロセス基準は、世界149か国の政府が支持する国際基準で、各国はこの基準をベースに自国の森林の特性に応じた認証制度を策定します。
例えば、アメリカのSFI(Sustainable Forestry Initiative)、カナダのCSA(Canadian Standards Association)、北欧諸国の森林認証制度などが、それぞれPEFCの承認を受けて相互承認されています。これにより、各国の森林の生態系や社会情勢の違いを反映した、より実情に即した森林管理が可能となっています。
PEFCの承認を受けた森林認証制度により認証された森林は、すべてPEFC認証林として認められます。この相互承認制度により、貿易において各国の認証材が国際的に通用するようになり、持続可能な森林管理の普及と国際取引の円滑化の両立が図られています。
日本のSGEC認証との関係
日本では、2003年にSGEC(Sustainable Green Ecosystem Council:緑の循環認証会議)という独自の森林認証制度が発足しました。SGECは、日本の森林の実情に応じた認証制度として、林業団体や環境NGOなどの働きかけによって創設されました。
日本は国土の約7割が森林で占められる森林大国ですが、人工林の割合が高く、零細な森林所有者が多いという特徴があります。SGECは、こうした日本特有の森林構造や林業経営の実情を考慮して設計された認証制度で、日本の認証森林の約8割をSGECが認証しています。
2014年にSGECはPEFCに加盟し、2016年にPEFC総会で相互承認が正式に認められました。これにより、SGEC認証を受けた製品は、PEFC認証商品として国際的に流通することが可能となりました。現在、日本国内では約215万ヘクタールの森林がSGEC/PEFC認証を取得しており、日本の持続可能な森林管理の推進に重要な役割を果たしています。
FSC認証とPEFC認証の違いと特徴の比較
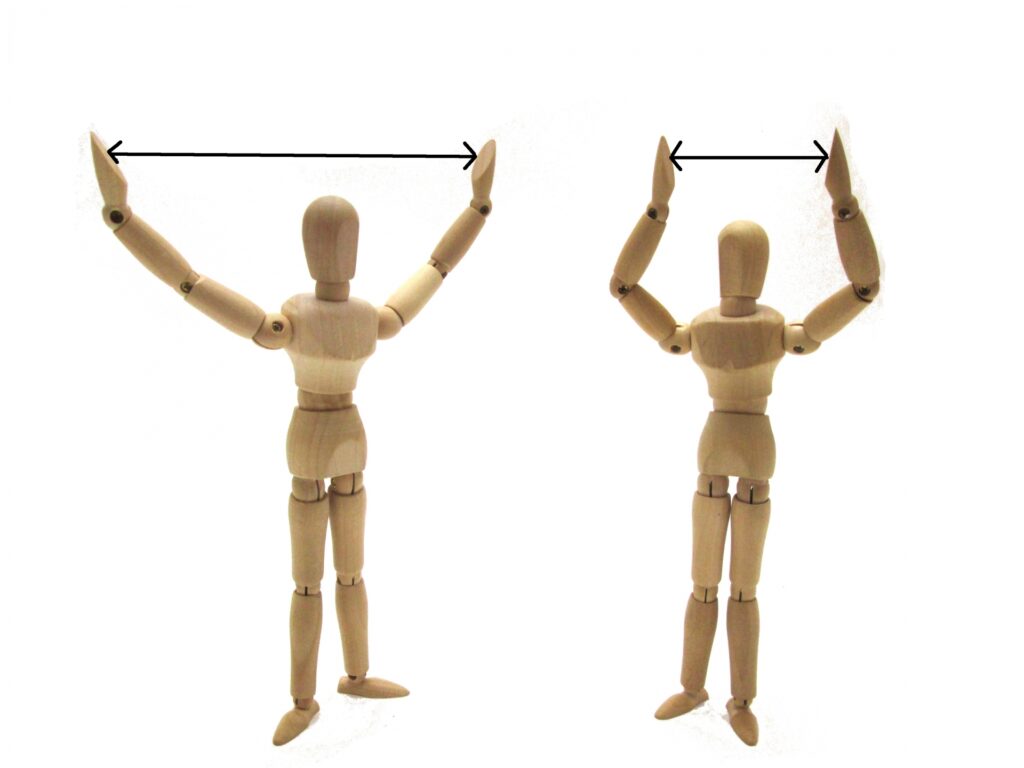
FSC認証とPEFC認証は、いずれも持続可能な森林管理を促進する国際的な認証制度ですが、その運営方針や審査基準には重要な違いがあります。どちらの認証制度も森林管理(FM認証)と加工流通過程の管理(CoC認証)の両方を提供している点は共通していますが、認証取得を検討する際は、それぞれの特徴を理解して適切な制度を選択することが重要です。
両制度の最も大きな違いは、基準の統一性にあります。FSCは世界共通の単一基準で審査を行うのに対し、PEFCは各国の認証制度を相互承認する仕組みを採用しています。また、認証森林面積では、PEFCが約3億2800万ヘクタール、FSCが約2億3000万ヘクタールと、PEFCの方が大きな規模を誇っています。
地域的な普及状況にも違いがあり、FSCは熱帯地域や発展途上国での存在感が強い一方、PEFCはヨーロッパや北米を中心に影響力を持っています。認証取得を検討する企業は、販売先の市場がどちらの認証を重視しているか、自社の事業展開地域での認知度などを考慮して選択する必要があります。
審査基準の違い
FSC認証とPEFC認証では、森林管理を評価する基準に大きな違いがあります。FSCは「森林管理の10原則と70の基準」という世界共通の詳細な規格を設けており、全世界どこでも同じ基準で審査が行われます。この統一性により、FSC認証は国際的に高い信頼性と一貫性を保っています。
一方、PEFCは「持続可能な森林管理のための汎欧州施業ガイドライン」を基準とし、各国がこのガイドラインに基づいて独自の認証制度を策定します。PEFCの基準には、森林資源とカーボンサイクルの維持、森林生態系の保全、生産機能の増進、水質・土壌の保全、社会的・経済的価値の維持という6つの主要項目が含まれています。
FSCの基準は環境保全や社会的配慮により重点を置いているのに対し、PEFCの基準は各国の政府間プロセスに基づいているため、より実用的で柔軟な運用が可能とされています。ただし、国別で基準が異なることから、規格基準の統一性に課題があるとの指摘もあります。
普及状況と認証森林面積の比較
世界的な普及状況を見ると、認証森林面積ではPEFCがFSCを上回っています。PEFCの認証森林面積は約3億2800万ヘクタール(44か国)、FSCは約2億3000万ヘクタール(82か国)となっており、PEFCの方が約1.4倍の面積を認証しています。
CoC認証の取得件数では、FSCが約5万件(137か国)、PEFCが約1万2700件(77か国)と、FSCの方が圧倒的に多くなっています。これは、FSCの方が国際的な認知度が高く、特に消費財メーカーや小売業界での採用が進んでいることを示しています。
日本国内では、FSC認証が約42万ヘクタールの森林と約1800件のCoC認証、PEFC認証(SGEC含む)が約215万ヘクタールの森林と約500件のCoC認証を取得しています。森林面積ではPEFC(SGEC)が、CoC認証件数ではFSCが優勢という状況になっています。
森林認証製品を選ぶメリットと社会への影響

森林認証製品を購入することは、単に環境に優しい商品を選ぶということ以上の大きな意味を持っています。消費者が認証マークの付いた製品を積極的に選択することで、世界規模での森林保全活動を支援し、持続可能な社会の実現に貢献することができます。
森林認証制度は、生産者と消費者をつなぐ重要な架け橋の役割を果たしています。認証製品の購入により、責任ある森林管理を行う生産者に経済的利益が還元され、それがさらなる持続可能な取り組みの推進力となります。この好循環により、世界中で森林の保護と適切な利用が促進されています。
ただし、森林認証は環境配慮のための認証であり、その製品の品質が他の製品よりも優れていることを示すものではありません。認証製品を選ぶ意義は、地球環境の保全と社会的責任への貢献にあることを理解することが重要です。
消費者にとってのメリット
消費者が森林認証製品を選ぶ最大のメリットは、自分の購買行動を通じて地球環境の保全に直接貢献できることです。FSCやPEFCのマークが付いた製品を購入することで、違法伐採や森林破壊に関与していない、責任ある森林管理から生まれた製品であることが保証されます。
認証マークは消費者にとって非常にわかりやすい判断基準となります。複雑な環境問題や森林管理の詳細を理解していなくても、マークを確認するだけで環境に配慮した選択ができます。日常的に使用するコピー用紙、ティッシュペーパー、段ボール、木製家具などにも認証製品が増えており、特別な努力をせずに環境貢献が可能です。
また、認証製品を選ぶことは、将来世代への責任を果たすことでもあります。現在の消費行動が未来の森林環境を左右するという認識を持ち、持続可能な社会の実現に向けて行動する意識の向上にもつながります。企業や学校、行政機関などでも、組織としての環境方針を具体的に実践する手段として認証製品の導入が進んでいます。
企業の持続可能な調達への貢献
企業にとって森林認証は、持続可能な調達方針を具体化し、ステークホルダーに対して環境への取り組みを明確に示すツールとして重要な意味を持ちます。近年、ESG投資やSDGsへの対応が企業経営の重要課題となる中、森林認証の取得や認証製品の調達は、企業の社会的責任を果たす具体的な行動として評価されています。
認証製品を調達することで、企業は自社のサプライチェーン全体の透明性を高めることができます。特に、紙製品や木材を大量に使用する業界では、調達方針の明確化と実践が重要な競争要因となっています。認証製品の使用により、違法伐採に関与するリスクを回避し、企業のレピュテーション向上にも寄与します。
さらに、森林認証は人権の尊重を保証するツールとしても機能します。認証基準には労働者の権利や地域社会との関係が含まれており、認証製品を購入することは人権に配慮した調達を実践することでもあります。グローバル企業を中心に、人権デューデリジェンスの一環として森林認証の活用が広がっています。
日本における森林認証制度の現状と今後の展望

日本の森林認証制度は、国際的な制度であるFSCと、日本独自のSGEC(PEFC相互承認)を中心として発展してきました。日本は国土の約7割が森林で覆われる森林大国でありながら、木材自給率は約4割にとどまっており、持続可能な国産材の利用拡大が重要な政策課題となっています。
現在、日本国内の森林認証面積は合計で約257万ヘクタールに達し、これは日本の森林面積全体の約10%に相当します。特にSGEC認証については、日本の森林の特性に適した制度として、地域の林業者や森林組合を中心に着実に普及が進んでいます。
政府も森林認証の普及を支援しており、グリーン購入法における特定調達品目の判断基準に森林認証材が位置づけられています。また、東京オリンピック・パラリンピックでは競技施設の建設に認証材が使用されるなど、大規模プロジェクトでの活用事例も増加しています。
今後の展望として、企業のESG経営やSDGs達成への取り組みが加速する中、森林認証製品に対する需要はさらに拡大すると予想されます。特に、カーボンニュートラルの実現に向けて、森林の二酸化炭素吸収機能への注目が高まっており、適切に管理された森林から生産される認証材の価値はより一層高まることが期待されます。
また、デジタル技術の活用による認証の効率化や、ブロックチェーン技術を用いたトレーサビリティの向上など、認証制度自体の進化も進んでいます。消費者の環境意識の向上とともに、より透明性が高く、信頼性のある森林認証制度の構築が求められており、日本の森林資源の有効活用と地球環境の保全の両立を目指した取り組みが継続的に推進されています。
森林認証制度は、私たち一人ひとりの選択が地球規模の環境保全につながる仕組みです。日常生活の中で認証マークを意識し、持続可能な森林管理から生まれた製品を選ぶことで、豊かな森林を未来世代に引き継ぐことができるのです。
参照元
・森林認証SGEC/PEFCジャパン
https://sgec-pefcj.jp/
・環境省環境ラベル等データベース(FSC認証制度)
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_14.html
・環境省環境ラベル等データベース(PEFC森林認証プログラム)
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_23.html
・林野庁 主な森林認証の概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/ninshou/con_3_1.html
・Forest Stewardship Council Japan
https://jp.fsc.org/jp-ja/About_FSC
・WWF Japan 森を守るマーク 森林認証制度FSC
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3547.html





