観光業界で急速に広がる「サステナブルツーリズム」という言葉をご存知でしょうか。美しい自然や伝統文化を未来に残しながら、地域と旅行者の両方が豊かになる新しい観光のかたちとして、世界中で注目を集めています。この記事では、サステナブルツーリズムの基本概念から実践方法まで、わかりやすく解説していきます。
この記事で学べるポイント
- サステナブルツーリズムの基本的な意味と従来の観光業との違い
- 環境・経済・社会の3つの視点から見た持続可能な観光の重要性
- 私たち一人ひとりができる具体的な実践方法
サステナブルツーリズムとは何か?基本的な意味と背景

サステナブルツーリズムは、国連世界観光機関(UNWTO)により「訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光」として定義されています。簡単に言えば、観光を楽しみながら、その土地の自然環境や文化、地域住民の生活を守り、地域経済の発展にも貢献する「持続可能な観光」のことです。
この考え方が生まれた背景には、従来の大量消費型観光(マスツーリズム)による弊害があります。観光客の急激な増加により、美しい自然が破壊されたり、地域住民の生活に支障をきたしたりする問題が世界各地で発生しました。
国連が定義する持続可能な観光の概念
持続可能な観光では、環境、経済、社会文化的な側面の3つの間で適切なバランスを図り、長期的な持続可能性を確保することが求められます。具体的には、自然遺産や生物多様性の保全を図りつつ環境資源を最適に活用し、地域コミュニティの文化的真正性を尊重し、すべての関係者に公平な社会経済的利益をもたらすことが重要とされています。
この定義は単なる理念ではなく、実際の観光政策や事業活動の指針として世界中で活用されています。2017年には国連により「開発のための持続可能な観光の国際年」が制定され、持続可能な観光の重要性が国際的に認識されました。
従来の観光業との違いとは
従来の観光業は、できるだけ多くの観光客を呼び込み、短期間で大きな収益を上げることを重視していました。一方、サステナブルツーリズムは「量より質」を重視し、長期的な視点で地域全体の価値を高めることを目指します。
例えば、大型リゾート開発で自然を破壊するのではなく、既存の自然環境を活かしたエコツアーを提供したり、地域の伝統工芸品を販売することで職人の技術継承を支援したりします。このように、観光そのものが地域の持続可能な発展に貢献する仕組みを作ることが、サステナブルツーリズムの核心です。
サステナブルツーリズムが注目される理由

近年、サステナブルツーリズムへの関心が高まっている背景には、深刻化する観光公害の問題と、持続可能な開発目標(SDGs)の普及があります。
観光公害の深刻化と環境問題
世界的な観光ブームにより、人気の観光地では「観光公害」と呼ばれる問題が深刻化しています。例えば、美しいビーチがプラスチックごみで汚染されたり、歴史的建造物が観光客の増加により損傷を受けたり、地域住民の生活環境が悪化したりする事例が世界各地で報告されています。
また、交通機関からの温室効果ガス排出や宿泊施設でのエネルギー消費など、観光業は環境負荷の大きな産業でもあります。気候変動への対策が急務となる中、観光業界にも環境への配慮が強く求められるようになりました。
SDGsとの深い関係性
2015年に採択されたSDGs(持続可能な開発目標)は、17の目標と169のターゲットで構成され、2017年には国連により「開発のための持続可能な観光の国際年」が指定されました。サステナブルツーリズムは、SDGsの多くの目標と密接に関連しています。
特に関連の深い目標として、目標8「働きがいも経済成長も」では観光による雇用創出、目標11「住み続けられるまちづくりを」では地域住民の生活環境改善、目標14「海の豊かさを守ろう」では海洋環境の保護などが挙げられます。観光業がこれらの目標達成に貢献することで、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を果たすことが期待されています。
サステナブルツーリズムの3つの重要な要素

サステナブルツーリズムを理解するには、3つの重要な柱を知ることが大切です。環境、経済、社会・文化のそれぞれの持続可能性が相互に支え合うことで、真の意味での持続可能な観光が実現されます。
環境の持続可能性
環境の持続可能性は、主要な生態学的過程を維持し、自然遺産や生物多様性の保全を図りつつ、観光開発において鍵となる環境資源を最適な形で活用することを意味します。これは単に自然を保護するだけでなく、観光資源として活用しながら環境を守る仕組みを作ることです。
具体的には、国立公園での入場者数制限、再生可能エネルギーを使用した宿泊施設の運営、地産地消を重視したレストランの経営などが挙げられます。また、観光客にもゴミの持ち帰りや指定されたルートでの移動を求めるなど、環境保護への協力を促すことも重要です。
近年では、カーボンニュートラルな旅行の推進や、プラスチックフリーの取り組みなど、より積極的な環境配慮の姿勢が求められています。環境への負荷を最小限に抑えながら、その美しさを次世代に引き継ぐことが環境の持続可能性の核心です。
経済の持続可能性
経済の持続可能性では、観光による収益が地域全体に公平に分配され、長期的な経済発展につながることが重要です。大企業だけが利益を得るのではなく、地域の中小事業者や住民も恩恵を受けられる仕組みづくりが求められます。
地元の農産物や工芸品を積極的に活用したり、地域住民をガイドとして雇用したりすることで、観光収入を地域内で循環させることができます。また、季節変動に左右されない通年型の観光コンテンツを開発することで、安定した雇用を創出することも可能です。
重要なのは、短期的な利益追求ではなく、地域経済の基盤を強化し、将来にわたって持続可能な収益構造を築くことです。地域の特色を活かした付加価値の高いサービスを提供することで、価格競争に巻き込まれない独自の魅力を創出できます。
社会・文化の持続可能性
社会・文化の持続可能性は、訪問客を受け入れるコミュニティーの社会文化面での真正性を尊重し、コミュニティーの建築文化遺産や生きた文化遺産、さらには伝統的な価値観を守り、異文化理解や異文化に対する寛容性に資することを目指します。
これは、地域の祭りや伝統芸能を観光コンテンツとして活用しながら、その本来の意味や価値を正しく伝えることを意味します。表面的な演出ではなく、文化の背景にある歴史や思いを丁寧に紹介することで、観光客の理解を深めると同時に、地域住民の文化への誇りを育むことができます。
また、観光客と地域住民との交流を促進し、相互理解を深めることも重要です。地域住民が観光業に主体的に参加できる環境を整えることで、外部からの一方的な開発ではなく、地域主導の持続可能な観光地づくりが可能になります。
日本におけるサステナブルツーリズムの現状

日本では、政府と民間が連携してサステナブルツーリズムの推進に取り組んでいます。特に、国際基準に沿った日本独自のガイドラインの策定や、各地での先進的な事例の創出が注目されています。
日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)
観光庁とUNWTO駐日事務所は2020年6月に「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」を発行し、「持続可能なマネジメント」「社会経済のサステナビリティ」「文化的サステナビリティ」「環境のサステナビリティ」の4つのカテゴリーでそれぞれに満たすべき基準を定めています。
このガイドラインは、DMO(観光地域づくり法人)や観光関連事業者が実際に活用できる具体的な指針として作成されており、地域における推進体制の整備、観光を巡る実態把握、安全や治安の維持、受入環境の整備、観光資源の保護など、多岐にわたる内容を網羅しています。
2023年3月末に閣議決定された「第4次観光立国推進基本計画」では、持続可能な観光地域づくりに取り組む地域数を2025年までに100地域(2022年は12地域)とする数値目標が設定されました。この目標達成に向けて、全国各地でJSTS-Dに基づく取り組みが加速しています。
国内での具体的な取り組み事例
日本各地では、地域の特色を活かしたサステナブルツーリズムの取り組みが展開されています。例えば、北海道の阿寒湖では、アイヌ文化の保護と継承を観光と結びつけた取り組みが評価されています。地域住民が主体となって文化体験プログラムを提供し、観光収入の一部を文化保護活動に還元する仕組みを構築しています。
また、山形県鶴岡市では、1400年続く出羽三山の聖地としての価値を守りながら、精神文化に触れる特別な体験を提供する取り組みが行われています。修験道の体験や地域の食文化を通じて、深い精神性を求める旅行者のニーズに応えています。
これらの事例に共通するのは、地域住民が観光の担い手として積極的に参加し、自分たちの文化や自然環境に誇りを持って取り組んでいることです。外部からの開発ではなく、地域主導の持続可能な観光地づくりが、真のサステナブルツーリズムの実現につながっています。
私たちにできるサステナブルツーリズムの実践方法

サステナブルツーリズムは、旅行者と観光事業者が協力することで実現されます。一人ひとりの小さな心がけが、大きな変化を生み出す力となります。
旅行者として心がけるべきポイント
旅行者にできる最も重要なことは、訪問先の環境や文化を尊重し、地域経済に貢献する意識を持つことです。具体的には、地元の食材を使ったレストランを選んだり、地域の工芸品を購入したりすることで、観光収入を地域に還元できます。
また、自然環境への配慮も欠かせません。指定されたルートを歩く、ゴミは必ず持ち帰る、野生動物には適切な距離を保つなど、基本的なマナーを守ることが重要です。宿泊施設では、タオルの再利用やエアコンの適切な使用など、省エネルギーを心がけることも環境保護につながります。
さらに、旅行前に訪問先の文化や歴史について学んでおくことで、より深い理解と敬意を持って観光を楽しむことができます。地域住民との交流を大切にし、相互理解を深める姿勢を持つことも、サステナブルツーリズムの重要な要素です。
観光事業者ができる取り組み
観光事業者は、サステナブルツーリズムの推進において中心的な役割を担います。宿泊施設では、再生可能エネルギーの導入、地産地消の推進、廃棄物の削減など、環境負荷を最小限に抑える取り組みが求められます。
旅行会社やツアーオペレーターは、地域住民をガイドとして雇用したり、地元の中小事業者と連携したツアーを企画したりすることで、観光収入の地域内循環を促進できます。また、観光客数の適切な管理や、環境教育を含むプログラムの提供も重要な取り組みです。
レストランや土産物店では、地域の伝統的な食材や工芸品を積極的に活用することで、地域文化の保護と継承に貢献できます。価格競争ではなく、地域の魅力や物語を伝えることで付加価値を創出し、持続可能な経営を実現することが可能です。
サステナブルツーリズムの今後の展望
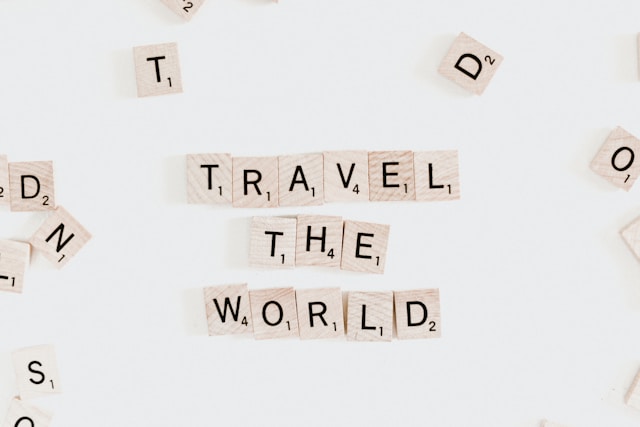
サステナブルツーリズムは、単なる一時的なトレンドではなく、観光業界の未来を決定する重要な方向性として定着しつつあります。新型コロナウイルスの影響により、人々の旅行に対する価値観が大きく変化し、量より質を重視する傾向が強まったことも、この流れを加速させています。
技術の進歩により、観光地の環境負荷をリアルタイムで監視したり、観光客の行動をデータ分析して最適な誘導を行ったりする仕組みも開発されています。デジタル技術を活用した持続可能な観光地管理は、今後さらに重要性を増すでしょう。
また、国際的な認証制度の普及により、サステナブルツーリズムの取り組みを客観的に評価し、旅行者が選択する際の指標として活用されるようになることも期待されます。消費者の意識の高まりとともに、持続可能性への取り組みが観光事業者の競争力を左右する時代が到来しています。
サステナブルツーリズムの実現には、政府、事業者、旅行者、地域住民すべての協力が不可欠です。一人ひとりが責任を持って行動することで、美しい自然や豊かな文化を未来に残しながら、誰もが恩恵を受けられる持続可能な観光の実現が可能になります。私たちの選択と行動が、観光業界の未来を築いていくのです。
参照元
・国連世界観光機関(UN Tourism)駐日事務所 https://unwto-ap.org/why/tourism-definition/
・日本政府観光局(JNTO) https://www.jnto.go.jp/projects/overseas-promotion/theme/sustainable-tourism.html
・第一生命経済研究所 https://www.dlri.co.jp/report/dlri/251291.html
・国連広報センター https://www.unic.or.jp/info/un_agencies_japan/unwto/
・日本エコツーリズムセンター https://ecocen.jp/sustainable




