近年、猛暑や豪雨、台風などの異常気象が世界各地で頻発し、私たちの生活に深刻な影響を与えています。こうした気候変動による被害を最小限に抑え、社会全体で乗り越えていくために注目されているのが「気候レジリエンス」という考え方です。
気候レジリエンスとは、気候変動の影響に対して柔軟に対応し、被害から素早く回復できる社会や組織の能力を指します。単に災害に耐えるだけでなく、変化する環境に適応しながら、重要な機能を維持し続ける強さと柔軟性を兼ね備えた概念です。
本記事では、気候レジリエンスの基本的な意味から、なぜ今この概念が重要視されているのか、そして私たち一人ひとりができる取り組みまで、わかりやすく解説していきます。
気候レジリエンスとは?基本的な意味と定義

気候レジリエンスを正しく理解するために、まずは「レジリエンス」という言葉の本来の意味から見ていきましょう。
レジリエンスの本来の意味
レジリエンス(resilience)は、もともと物理学の分野で使われていた用語で、「弾力性」や「復元力」を意味します。ゴムボールが地面に落ちても元の形に戻るように、外からの力を受けても変形し、その後元の状態に戻る性質を表していました。
この概念は次第に心理学や社会学の分野にも広がり、困難な状況に直面した時に適応し、回復する能力として使われるようになりました。例えば、大きなストレスを受けても心の健康を保ち、立ち直る力のことを「心理的レジリエンス」と呼びます。
気候レジリエンスの具体的な定義
気候レジリエンスは、このレジリエンスの概念を気候変動の分野に応用したものです。具体的には、生態系や社会、企業が気候変動の影響を予測し、準備し、対応する能力を指します。
重要なのは、気候レジリエンスが単なる「我慢強さ」ではないということです。台風が来ても建物が壊れないような頑丈さだけでなく、被害を受けた後も素早く日常生活を取り戻し、さらに次の災害に備えてより良いシステムを構築する能力まで含んでいます。
例えば、洪水の被害を受けた地域が、復旧の過程で排水システムを改良し、将来の洪水に対してより強い街づくりを行うことも気候レジリエンスの一例です。このように、単に元の状態に戻るだけでなく、学習と改善を通じてより強靭な社会を築いていく過程全体を表しています。
なぜ気候レジリエンスが注目されているのか

気候レジリエンスという概念が世界的に注目を集めている背景には、従来の対策だけでは対応しきれない新たな課題があります。
頻発する気象災害と社会への影響
地球温暖化の進行により、これまで経験したことのない規模や頻度で異常気象が発生しています。日本でも2018年の西日本豪雨、2019年の台風15号・19号、そして毎年のように更新される最高気温記録など、「想定外」の災害が日常化しています。
これらの災害は、私たちの生活のあらゆる面に影響を与えます。農作物の被害による食料価格の上昇、交通機関の麻痺による経済活動の停滞、停電や断水による生活インフラの機能停止など、被害は一つの分野にとどまらず、社会全体に連鎖的に広がります。
さらに深刻なのは、気候変動の影響が今後も継続し、さらに深刻化することが予想されている点です。一度の災害に対処するだけでなく、継続的に変化する気候条件に対応し続ける必要があるのです。
従来の防災対策との違い
従来の防災対策は、過去の災害データに基づいて「想定される最大規模の災害」に備えることが中心でした。しかし、気候変動により災害の規模や性質が変化している現在、過去のデータだけでは十分な対策を講じることが困難になっています。
気候レジリエンスのアプローチは、この課題に対してより柔軟で包括的な解決策を提供します。具体的には、災害が発生する前の予防段階から、発生時の対応、そして復旧・復興に至るまでの全ての段階を通じて、社会システム全体の適応能力を高めることを重視します。
また、単一の対策に依存するのではなく、複数の手段を組み合わせることで、一つの対策が失敗しても全体としては機能を維持できるような冗長性を持たせることも重要な特徴です。例えば、避難所の確保だけでなく、在宅避難の支援、地域コミュニティの結束強化、早期警戒システムの充実など、多層的な対策を講じることで、より強靭な社会を目指しています。
気候レジリエンスの3つの重要な要素

気候レジリエンスを効果的に構築するためには、3つの段階に分けて考えることが重要です。これらの要素が相互に連携することで、真に強靭な社会システムが実現されます。
予測・準備する力
気候レジリエンスの第一段階は、将来起こりうる気候変動の影響を予測し、事前に準備する能力です。これには科学的なデータ分析と長期的な計画立案が欠かせません。
具体的には、気象データの解析により豪雨や猛暑の発生パターンを把握し、インフラの脆弱性を事前に特定します。例えば、地下街の浸水リスクを評価し、排水設備の強化や避難経路の確保を行うことが該当します。また、農業分野では、気温上昇に適応した新しい品種の開発や栽培方法の研究も重要な準備活動です。
早期警戒システムの構築も予測・準備の重要な要素です。気象庁の特別警報や自治体の避難指示が適切なタイミングで発令され、住民に確実に伝達される仕組みを整備することで、被害を未然に防ぐことができます。
対応・適応する力
災害が実際に発生した際に、被害を最小限に抑えながら重要な機能を維持する能力が対応・適応力です。この段階では、迅速な判断と柔軟な行動が求められます。
緊急時には、電力や水道などのライフラインの確保、医療体制の維持、避難所の運営などが同時並行で必要になります。これらを効率的に実施するためには、平時からの訓練と関係機関の連携が不可欠です。
企業においては、事業継続計画(BCP)の策定と実行がこの要素に該当します。サプライチェーンの多様化、在宅勤務体制の整備、重要データのバックアップ体制など、災害時でも事業を継続できる仕組みを構築することが求められます。
回復・学習する力
災害からの復旧段階で最も重要なのが、単に元の状態に戻るのではなく、経験から学び、より強靭なシステムを構築する能力です。これが気候レジリエンスの最も特徴的な要素といえます。
復旧作業では、被害の原因を詳細に分析し、同じような被害を防ぐための改善策を講じます。例えば、河川の氾濫で浸水被害を受けた地域では、堤防の強化だけでなく、雨水の貯留施設の設置や土地利用の見直しなど、複合的な対策を検討します。
また、災害対応の過程で得られた教訓を他の地域や組織と共有することも重要です。成功事例や失敗事例を蓄積し、社会全体の対応能力向上に貢献することで、次の災害に対してより効果的な対策を講じることができます。
日本における気候レジリエンスの取り組み
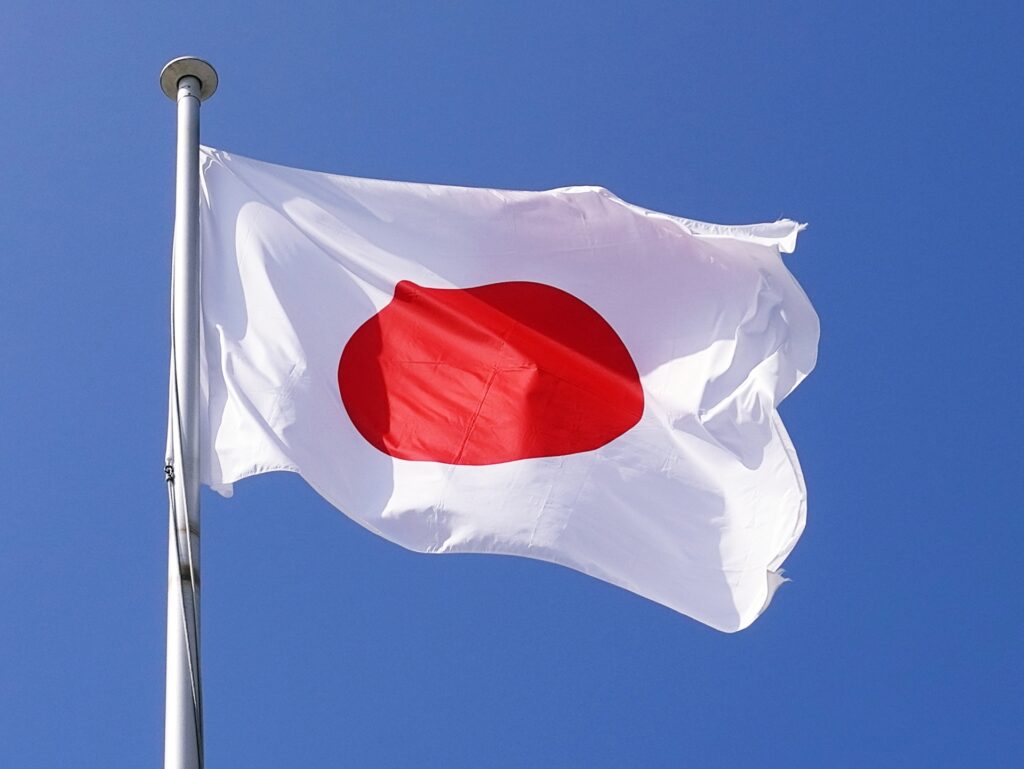
日本は世界でも有数の災害多発国であり、気候レジリエンスの構築に向けて積極的な取り組みを進めています。
気候変動適応法の制定
2018年6月に制定された気候変動適応法は、日本の気候レジリエンス向上の法的基盤となる重要な法律です。この法律により、気候変動への適応策が初めて法的に位置づけられ、国、地方公共団体、事業者、国民が連携して取り組む枠組みが整備されました。
同法では、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、国立環境研究所による情報収集・分析・提供などが義務づけられています。これにより、科学的根拠に基づいた適応策を全国規模で推進する体制が構築されました。
また、地方公共団体には地域気候変動適応計画の策定が求められており、各地域の特性に応じた具体的な対策を講じることが可能になっています。この法律は、温室効果ガス削減を目的とする地球温暖化対策推進法と並んで、気候変動対策の「両輪」として位置づけられています。
政府と自治体の連携体制
気候変動適応法に基づき、国立環境研究所内に気候変動適応センターが設立され、全国の地域気候変動適応センターとのネットワークが構築されています。このネットワークを通じて、最新の科学的知見や効果的な適応策の情報が全国に共有されています。
各都道府県や市町村では、地域の気候リスクを評価し、農業、水資源、自然災害、健康、産業など、分野別の適応策を策定しています。例えば、沖縄県では海面上昇や台風の強大化に備えた沿岸域の保全対策、北海道では気温上昇による農業への影響に対応した品種改良や栽培技術の開発などが進められています。
さらに、気候変動適応推進会議では、関係府省庁が実施する施策の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画の見直しを行っています。このように、科学的根拠に基づく継続的な改善を行うことで、社会全体の気候レジリエンス向上を図っています。
企業・地域・個人レベルでの気候レジリエンス向上策

気候レジリエンスの構築は、政府や自治体だけでなく、企業や地域コミュニティ、そして私たち一人ひとりの取り組みが重要な役割を果たします。
企業が取り組むべき対策
企業にとって気候レジリエンスの強化は、事業の継続性確保と競争力向上の両面で重要な経営課題となっています。まず基本となるのは、自社の事業活動が直面する気候リスクの詳細な評価です。製造拠点の立地条件、サプライチェーンの脆弱性、顧客への影響などを総合的に分析し、リスクマップを作成することから始まります。
事業継続計画(BCP)の策定と定期的な見直しも欠かせません。災害時の代替生産拠点の確保、重要データのバックアップ体制、従業員の安全確保と連絡体制など、多角的な準備が必要です。また、取引先との連携強化により、サプライチェーン全体でのレジリエンス向上を図ることも重要です。
近年注目されているのが、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく情報開示です。気候リスクと機会を財務的な観点から評価し、投資家やステークホルダーに透明性のある情報を提供することで、企業の信頼性向上と資金調達の円滑化にもつながります。
地域コミュニティでの取り組み
地域レベルでの気候レジリエンス向上には、住民同士の結束と相互支援の仕組みづくりが重要です。自治会や町内会を中心とした防災訓練の実施、避難経路の確認、緊急時の連絡体制の整備などが基本的な取り組みとなります。
特に効果的なのが、地域の特性を活かした自然との共生型の対策です。例えば、都市部では緑地や公園を増やすことで雨水の吸収能力を高め、洪水リスクを軽減できます。また、屋上緑化や壁面緑化により、ヒートアイランド現象の緩和と建物の冷房負荷軽減を同時に実現することも可能です。
地域の農業や漁業との連携も重要な要素です。地産地消の推進により、災害時の食料確保と平時の地域経済活性化を両立できます。さらに、伝統的な知恵と最新技術を組み合わせることで、より効果的な適応策を生み出すことができます。
個人ができる身近な対策
私たち一人ひとりができる気候レジリエンス向上の取り組みは、日常生活の中に数多く存在します。まず重要なのは、情報収集と早期対応の習慣づけです。気象情報や災害警報を定期的にチェックし、異常気象の兆候を感じたら早めの行動を心がけることが基本となります。
家庭での備えとしては、非常用品の準備はもちろん、住宅の断熱性能向上や雨水対策も有効です。窓ガラスに遮熱フィルムを貼る、庭に雨水を一時的に貯める設備を設置するなど、比較的簡単にできる対策も多くあります。
また、省エネルギー行動の実践により、電力需給の安定化に貢献することも重要です。エアコンの適切な温度設定、LED照明への切り替え、不要な電気の消灯などは、個人の光熱費削減と社会全体のエネルギーレジリエンス向上を同時に実現します。
さらに、地域の防災活動への参加や近隣住民との普段からのコミュニケーションも、いざという時の相互支援につながる重要な取り組みです。
気候レジリエンスの未来と持続可能な社会の実現

気候レジリエンスは、単なる災害対策を超えて、持続可能な社会の実現に向けた包括的なアプローチとして位置づけられています。国連の持続可能な開発目標(SDGs)においても、ゴール13「気候変動に具体的な対策を」の中で、気候関連災害に対する強靱性と適応能力の強化が明確に掲げられています。
今後の気候レジリエンス向上には、デジタル技術の活用が重要な役割を果たすと期待されています。人工知能による気象予測の精度向上、IoTセンサーを活用したリアルタイムの災害監視、ドローンによる被災状況の迅速な把握など、最新技術と従来の対策を組み合わせることで、より効果的なレジリエンス構築が可能になります。
また、気候変動の緩和策(温室効果ガスの削減)と適応策(気候レジリエンスの向上)を統合的に推進することも重要です。再生可能エネルギーの導入は温室効果ガス削減に貢献するとともに、分散型電源としてエネルギーセキュリティの向上にも寄与します。このように、一つの取り組みで複数の効果を得られる統合的なアプローチが求められています。
気候レジリエンスの構築は、現在を生きる私たちだけでなく、将来世代のためにも欠かせない取り組みです。変化し続ける気候条件の中で、安全で豊かな社会を維持し発展させていくために、政府、企業、地域、個人それぞれのレベルで継続的な努力を重ねていくことが重要です。
私たち一人ひとりが気候レジリエンスの重要性を理解し、できることから始めることで、災害に強く、持続可能な未来社会の実現に貢献できるのです。





