企業の脱炭素経営が注目される中、「再生可能エネルギー証書(REC)」という言葉を耳にする機会が増えています。RECは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電された電力の環境価値を証明する仕組みです。この証書を活用することで、企業は自社の環境への取り組みを客観的に示すことができます。
この記事で学べるポイント
- RECの基本的な仕組みと発行プロセス
- 他の環境証書との具体的な違いと特徴
- 企業がRECを活用する実践的なメリット
再生可能エネルギー証書(REC)の基本知識
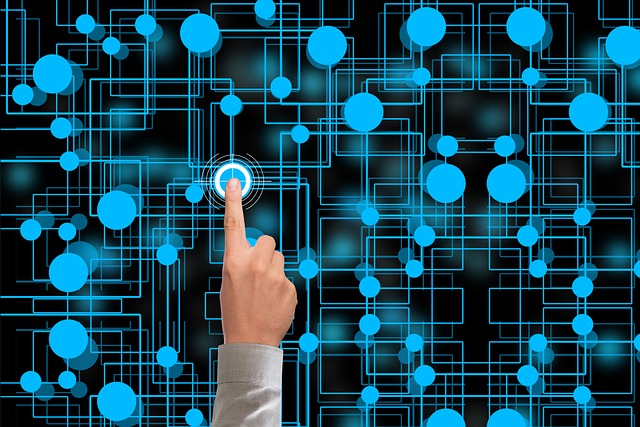
再生可能エネルギー証書(REC)は、主に北米で発行されている環境証書制度です。「グリーン・タグ」や「再生可能エネルギー・クレジット」とも呼ばれ、企業の環境経営において重要な役割を果たしています。
RECを理解するには、まず「電力の価値」が2つに分かれることを知る必要があります。再生可能エネルギーで発電された電力には、実際の電気としての価値に加えて、「環境に優しい電力である」という価値があります。RECは、この環境価値の部分だけを切り出して証書化したものです。
RECの定義と目的
RECは、1メガワット時(MWh)の再生可能エネルギー発電に対して発行される証書です。1MWhは、一般的な家庭の約1か月分の電力使用量に相当します。この証書を保有することで、企業は「再生可能エネルギー由来の電力を使用している」と主張できるようになります。
RECの主な目的は、アメリカやカナダの「RPS制度(再生可能ポートフォリオ基準)」を達成することです。RPS制度とは、電力供給事業者に対して一定割合以上の再生可能エネルギー利用を義務付ける制度で、この基準を満たすためにRECが活用されています。
また、近年では企業の自主的な脱炭素取り組みにも広く利用されています。特に、RE100やSBTといった国際的な環境イニシアティブへの報告において、RECは重要な証明手段となっています。
RECが発行される仕組み
RECの発行プロセスは、厳格な管理システムの下で行われています。まず、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー発電所が電力を生産すると、その発電量に応じてRECが発行されます。
発行されたRECには、発電所の場所、発電方法、発電時期などの詳細な情報が記録されます。これらの情報は「レジストリ」と呼ばれる電子システムで管理され、証書の二重使用や不正取引を防ぐ仕組みが整っています。
RECの取引は、主に2つの市場で行われています。1つは「義務市場」で、RPS制度の基準達成を目指す電力事業者が対象です。もう1つは「任意市場」で、企業が自主的な環境目標達成のために利用しています。証書の価格は、需要と供給のバランスによって決まり、発電方法や地域によっても異なります。
RECと他の環境証書との違い

世界には様々な再生可能エネルギー証書制度が存在します。RECは北米で発行される証書ですが、同様の目的を持つ証書が各地域で運用されています。これらの証書には、対象地域や発行条件に違いがあるため、企業が自社に適した証書を選択する際には、それぞれの特徴を理解することが重要です。
環境証書を選ぶ際のポイントは、事業展開地域、報告先の要求事項、コストなどを総合的に検討することです。グローバル企業の場合は国際的な認知度を、国内企業の場合は日本の制度への対応状況を重視する傾向があります。
I-RECとの違い
I-REC(International Renewable Energy Certificate)は、国際的な再生可能エネルギー証書制度です。RECが北米(アメリカ・カナダ)に限定されているのに対し、I-RECはアジア、アフリカ、南米など60以上の国と地域で発行されています。
最大の違いは対象地域の広さです。RECは北米の発電所からの電力のみが対象ですが、I-RECは日本を含む多くの国で発行可能です。実際に、日本では2023年1月からI-RECの発行が本格的に開始されました。
また、認証機関も異なります。RECは各州や地域の管理システムで運用されているのに対し、I-RECはオランダの非営利団体「I-REC Standard」が統一的に管理しています。この違いにより、I-RECの方が国際的な統一基準として認識されやすい特徴があります。
企業の視点では、事業展開地域に応じて選択が変わります。北米で事業を行う企業はRECを、アジアや新興国で事業を展開する企業はI-RECを選ぶことが一般的です。
日本の非化石証書・グリーン電力証書との違い
日本国内には、非化石証書とグリーン電力証書という独自の環境証書制度があります。これらとRECの主な違いは、対象地域と制度の目的にあります。
非化石証書は、日本政府が運営する公的な制度で、化石燃料を使わずに発電された電力の環境価値を証明します。特徴的なのは、原子力発電も対象に含まれている点です。また、日本の温対法(地球温暖化対策推進法)などの法的報告に利用できるため、国内企業にとって実用性が高い証書です。
グリーン電力証書は、民間機関が運営する制度で、再生可能エネルギーのみを対象としています。非化石証書と違い原子力は含まれませんが、法的な報告には別途認証が必要な場合があります。
RECとこれらの日本の証書の違いは、主に国際的な認知度と活用範囲にあります。RECは国際的なイニシアティブへの報告に直接利用できますが、日本の証書は海外では認知度が低い場合があります。一方で、日本の証書は国内の法制度に対応しているという利点があります。
企業は、自社の事業戦略や報告要件に応じて、これらの証書を使い分けることが重要です。
RECを活用するメリット

RECの活用は、企業にとって多方面にわたるメリットをもたらします。単なる環境への貢献だけでなく、ビジネス面での競争力向上や、ステークホルダーとの関係強化にも大きく寄与します。特に、グローバルに事業を展開する企業にとって、RECは国際的な環境基準に対応するための重要なツールとなっています。
近年、投資家や消費者の環境意識が高まる中、企業の環境への取り組みは事業の持続可能性を示す重要な指標として注目されています。RECの活用により、企業は自社の環境配慮を客観的に証明し、ステークホルダーからの信頼獲得につなげることができます。
企業にとってのメリット
RECを活用する最大のメリットは、企業の温室効果ガス排出量を実質的に削減できることです。具体的には、Scope2排出量(購入した電力の使用に伴う間接排出)の削減に活用できます。例えば、年間1,000MWhの電力を使用する企業がRECを購入した場合、その分の電力使用によるCO2排出量をゼロとして計算することが可能になります。
国際的な環境イニシアティブへの対応も重要なメリットです。RE100(事業運営に必要な電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際イニシアティブ)やSBT(科学的根拠に基づく温室効果ガス削減目標)、CDP(企業の環境情報開示を推進する国際プログラム)への報告において、RECは有効な証明手段として認められています。
また、RECは既存の電力契約を変更することなく環境価値を購入できるため、導入のハードルが低いという特徴があります。太陽光パネルの設置や再生可能エネルギー電力への切り替えが困難な企業でも、RECを購入することで環境目標の達成が可能になります。
コスト面でも、RECは他の脱炭素手段と比較して比較的安価で導入できることが多く、企業の予算に応じて購入量を調整できる柔軟性があります。
投資家・ステークホルダーへの効果
RECの活用は、投資家からの評価向上に直結します。ESG投資(環境・社会・ガバナンスを考慮した投資)が主流となる中、企業の環境への取り組みは投資判断の重要な要素となっています。RECを活用した環境目標の達成は、投資家に対して企業の持続可能性と将来性をアピールする強力な材料となります。
顧客や取引先との関係においても、RECの活用は大きな効果を発揮します。特に、環境意識の高い企業との取引では、サプライチェーン全体での環境配慮が求められることが増えています。RECによる環境価値の証明は、こうした取引先の要求に応える手段として活用できます。
また、企業のブランドイメージ向上にも寄与します。消費者の環境意識が高まる中、環境に配慮した企業として認知されることは、ブランドの差別化や顧客ロイヤリティの向上につながります。RECの活用は、こうしたブランド戦略の重要な要素となっています。
人材採用の面でも効果が期待できます。特に若い世代の求職者は、企業の社会的責任や環境への取り組みを重視する傾向があります。RECを活用した環境経営は、優秀な人材の獲得や従業員のエンゲージメント向上に貢献することができます。
RECの購入方法と活用事例

RECの購入は、企業の規模や目的に応じて様々な方法があります。適切な購入方法を選択することで、コスト効率良く環境目標を達成することが可能になります。また、多くの企業がRECを活用して実際に成果を上げている事例を参考にすることで、自社での導入イメージを具体化することができます。
RECの市場は年々拡大しており、価格の透明性や取引の利便性も向上しています。企業にとっては選択肢が増える一方で、自社のニーズに最適な購入方法を見極めることがより重要になっています。
RECの購入プロセス
RECの購入は、主に3つの方法で行うことができます。1つ目は、電力購入契約(PPA)との組み合わせです。これは、再生可能エネルギー発電事業者と長期契約を結び、電力とRECを一括で購入する「バンドル」と呼ばれる方法です。安定した価格で長期間の調達が可能ですが、契約期間や購入量に制約があります。
2つ目は、RECのみを単独で購入する「アンバンドル」方式です。この方法では、電力契約とは別にRECだけを購入するため、既存の電力契約を変更する必要がありません。短期間での調達や、必要な分だけの購入が可能で、多くの企業が採用している方法です。
3つ目は、仲介業者を通じた購入です。RECの取引に精通した専門業者が、企業のニーズに応じて最適なRECを調達してくれます。初めてRECを購入する企業や、手続きを簡素化したい企業に適しています。
購入時に重要なのは、RECの「ヴィンテージ」(発電年)の確認です。多くの国際イニシアティブでは、運転開始から15年以内の新しい発電設備からのRECを求めています。また、発電方法や地域も選択できるため、企業の環境戦略に合致したRECを選ぶことが重要です。
企業の活用事例
多くのグローバル企業がRECを活用して環境目標を達成しています。例えば、IT企業では大規模なデータセンターの電力使用によるCO2排出量を削減するためにRECを活用するケースが多く見られます。これらの企業は、数十万MWhから数百万MWhという大量のRECを購入し、事業活動における再生可能エネルギー比率100%を実現しています。
製造業では、工場の電力使用に伴う排出量削減にRECを活用する事例があります。特に、環境配慮型製品の製造において、「製造過程で使用した電力は100%再生可能エネルギー由来」というメッセージを消費者に伝える手段として活用されています。
金融業界でも、オフィスビルの電力使用やIT設備の運用に伴う排出量削減にRECを活用する事例が増えています。ESG投資を推進する金融機関にとって、自社の環境配慮は重要な経営課題となっており、RECはその解決手段の一つとして注目されています。
小売業では、店舗運営に必要な電力にRECを活用し、「環境に配慮した店舗運営」を顧客にアピールする事例があります。特に、環境意識の高い消費者をターゲットとする企業では、RECの活用が差別化戦略の重要な要素となっています。
RECの課題と今後の展望

RECの活用が広がる一方で、制度面や運用面での課題も指摘されています。これらの課題を理解し、適切に対応することで、RECをより効果的に活用することが可能になります。また、今後の市場動向を把握することで、長期的な環境戦略の策定に役立てることができます。
環境証書市場は急速に発展しており、新しい技術や制度の導入により、これらの課題の多くは解決される見込みです。企業は最新の動向を注視しながら、戦略的にRECを活用していく必要があります。
現在の課題
RECの最大の課題は、証書の購入が実際の温室効果ガス排出量を直接削減するわけではないという点です。RECは「環境価値の移転」であり、実際の発電所で削減されたCO2排出量を証書として購入者に移転する仕組みです。そのため、RECの購入だけでは物理的な排出削減にはならず、再生可能エネルギーの新規建設を促進する「追加性」の観点が重要になります。
トラッキング(追跡可能性)の確保も重要な課題です。同一のREC証書が複数の企業によって二重に使用されることを防ぐため、厳格な管理システムが必要です。現在、各州や地域で異なる管理システムが運用されているため、システム間の連携や統一化が課題となっています。
価格の変動性も企業にとっての課題の一つです。RECの価格は市場の需給バランスによって決まるため、大きく変動することがあります。特に、RPS制度の基準が厳しくなったり、企業の環境目標が高まったりすると、需要が急増して価格が上昇する傾向があります。
また、RECの種類や品質に関する理解不足も課題として挙げられます。発電方法、発電時期、地域などによってRECの価値が異なるため、企業は自社の目的に適したRECを選択する必要があります。しかし、これらの違いを十分に理解せずに購入してしまうケースも見られます。
今後の市場展望
RECの市場は今後も拡大が続くと予想されます。特に、企業の環境目標がより高度化し、RE100やSBTなどの国際イニシアティブへの参加企業が増加することで、RECの需要は一層高まると考えられます。
技術面では、ブロックチェーン技術を活用したより透明性の高いトラッキングシステムの導入が進むと予想されます。これにより、RECの二重使用防止や取引の透明性向上が期待されています。
制度面では、各地域のREC制度の統一化や相互認証の仕組み作りが進むと考えられます。現在、地域ごとに異なる制度が運用されていますが、グローバル企業の利便性向上のため、制度の統一化や相互運用性の向上が求められています。
また、「追加性」を重視した新しいREC制度の開発も進んでいます。従来のRECに加えて、新規建設された再生可能エネルギー発電所からのRECに付加価値を付ける仕組みや、地域の経済発展に貢献するRECの開発などが検討されています。
日本市場においても、I-RECの本格導入により、国際的な環境証書市場との連携が強化されると予想されます。これにより、日本企業がグローバルな環境基準により容易に対応できるようになることが期待されています。
まとめ

再生可能エネルギー証書(REC)は、企業の脱炭素経営において重要な役割を果たす制度です。RECを活用することで、企業は既存の電力契約を変更することなく、再生可能エネルギーの環境価値を獲得し、温室効果ガス排出量の削減を実現できます。
RECの最大の特徴は、北米を中心とした地域で発行される国際的に認知度の高い環境証書であることです。RE100やSBTなどの国際的な環境イニシアティブへの報告にも活用でき、グローバル企業にとって重要なツールとなっています。
ただし、RECの活用にあたっては、環境価値の移転であることを理解し、実際の排出削減と組み合わせた総合的な環境戦略を策定することが重要です。また、発電方法や地域、ヴィンテージなどの違いを理解して、自社の目的に適したRECを選択する必要があります。
今後、環境証書市場の拡大とともに、RECの制度や技術はさらに発展していくと予想されます。企業は最新の動向を把握しながら、戦略的にRECを活用することで、持続可能な経営の実現と競争力の向上を図ることができるでしょう。
参照元
・IBM Japan https://www.ibm.com/jp-ja/topics/renewable-energy-certificates
・自然電力グループ https://shizenenergy.net/decarbonization_support/column_seminar/i_rec/
・経済産業省資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html
・環境省 https://www.env.go.jp/earth/はじめての再エネ活用ガイド(企業向け).pdf
・SCSK株式会社 https://www.scsk.jp/sp/enetrack/topics/page004/
・日本品質保証機構 https://www.jqa.jp/service_list/environment/service/greenenergy/file/index/outline.pdf





