電気を作るときに捨てられている熱を有効活用できるシステムがあることをご存知でしょうか。コージェネレーションは、発電と同時に生じる熱エネルギーを回収し、給湯や暖房に利用する革新的な技術です。この一石二鳥のシステムによって、従来の約2倍のエネルギー効率を実現できます。
この記事で学べるポイント
- コージェネレーションの基本的な仕組みと従来システムとの違い
- 発電方式による3つの種類とそれぞれの特徴
- 導入による省エネ効果と経済的なメリット
コージェネレーションとは何か

コージェネレーションとは、一つの燃料から電気と熱の2つのエネルギーを同時に生み出すシステムのことです。「Co(共同で)」と「Generation(生成する)」を組み合わせた言葉で、日本では「熱電併給システム」とも呼ばれています。
このシステムの最大の特徴は、従来なら捨てられていた排熱を有効利用する点にあります。例えば、私たちが普段利用している火力発電所では、発電時に大量の熱が発生しますが、その多くは冷却水として川や海に放出されています。コージェネレーションでは、この排熱を回収して給湯や暖房、工場の蒸気源として活用します。
基本的な定義と意味
コージェネレーションシステムは、天然ガス、石油、LPガスなどを燃料とし、エンジンやタービン、燃料電池などを使って発電を行います。その際に生じる廃熱を蒸気や温水として回収し、冷暖房や給湯、工場の熱源などに利用するのが基本的な流れです。
このシステムが注目される理由は、エネルギー効率の飛躍的な向上にあります。単独で発電だけを行う場合の効率は約40%程度ですが、コージェネレーションでは排熱利用により総合効率を75~80%まで高めることができます。つまり、同じ燃料でほぼ2倍のエネルギーを取り出せることになります。
従来の発電システムとの違い
従来の電力供給システムでは、大型の火力発電所で電気を作り、送電線を通じて需要地まで送電します。しかし、この過程で送電ロスが発生し、さらに発電時の排熱は利用されずに環境中に放出されてしまいます。
一方、コージェネレーションシステムは需要地の近くに設置するため、送電ロスを大幅に削減できます。また、発電と同時に生じる熱をその場で活用するため、エネルギーの無駄が最小限に抑えられます。
具体的な例として、ホテルでコージェネレーションを導入した場合を考えてみましょう。発電で得た電気は客室の照明や空調に使用し、同時に発生した熱は給湯や暖房に活用します。このように電気と熱の両方を同じ施設内で消費することで、エネルギー効率を最大化できるのです。
コージェネレーションの仕組み

コージェネレーションシステムの基本的な流れは、燃料の燃焼→発電→排熱回収→熱利用という4つのステップで構成されています。このプロセスを理解することで、なぜ高いエネルギー効率を実現できるのかが分かります。
まず、天然ガスなどの燃料を燃焼させてエンジンやタービンを動かし、発電機で電気を生み出します。この時点では従来の発電システムと同じです。違いが生まれるのは次のステップで、発電時に発生する熱を冷却水や排気ガスから回収し、蒸気や温水として取り出します。回収した熱エネルギーは、給湯、暖房、冷房(吸収式冷凍機を使用)、工場の蒸気源などに幅広く活用されます。
発電と排熱回収の流れ
発電プロセスでは、燃料の燃焼により高温のガスが発生し、これがエンジンやタービンを回転させます。エンジンの冷却水は80~90℃、排気ガスは300~500℃の高温になるため、これらの熱を回収することで大量の温水や蒸気を得ることができます。
排熱回収の方法は用途によって異なります。給湯用途では、エンジンの冷却水を熱交換器で回収し、60~80℃の温水として利用します。より高温の熱が必要な場合は、排気ガスから熱を回収して100℃以上の蒸気を生成します。このように、必要な温度レベルに応じて適切な熱源を選択することで、効率的な熱利用が可能になります。
主な原動機の種類
コージェネレーションで使用される原動機には、主に3つのタイプがあります。それぞれ特徴や適用範囲が異なるため、用途に応じて適切な方式を選択することが重要です。
ガスタービン方式は、大規模な産業用途に適しており、数百kWから数万kWの発電が可能です。燃料を燃焼させて高温・高圧のガスを作り、これでタービンを回転させます。起動が早く、運転制御が容易な特徴があります。
ガスエンジン方式は、中小規模の業務用途で広く使われており、数十kWから数千kWの範囲で利用されます。自動車のエンジンを大型化したような仕組みで、メンテナンスが比較的容易で信頼性が高いのが特徴です。
燃料電池方式は、水素と酸素の化学反応で直接電気を生み出すため、発電効率が高く、環境負荷が小さいのが特徴です。家庭用の「エネファーム」として普及が進んでおり、1kW程度の小型システムから産業用の数百kWシステムまで幅広く展開されています。
コージェネレーションの種類

コージェネレーションシステムは、発電に使用する原動機の種類によって大きく3つの方式に分類されます。それぞれに異なる特徴があり、設置場所や用途に応じて最適な方式を選択することが重要です。
日本国内では内燃機関方式が最も多く導入されており、全体の約9割を占めています。一方、欧米では外燃機関方式が主流となっているなど、地域によって普及状況に違いがあります。これは気候条件や熱需要パターンの違いが影響しているためです。
内燃機関方式
内燃機関方式は、燃料を機関内部で燃焼させて動力を得る方式で、ガスエンジン、ガスタービン、ディーゼルエンジンなどがあります。この方式の最大の特徴は、起動時間が短く、電力需要の変動に柔軟に対応できることです。
ガスエンジン方式は、天然ガスを燃料とし、自動車エンジンを大型化したような仕組みで発電します。発電効率は35~42%程度で、排熱回収により総合効率を80%近くまで高めることができます。病院や福祉施設、オフィスビルなど、電気と熱の需要が安定している施設で多く採用されています。
ガスタービン方式は、高温・高圧の燃焼ガスでタービンを回転させる方式で、大容量発電が可能です。工場や大型商業施設での導入が多く、特に蒸気需要の多い製造業では排気ガスの高温を活用して効率的な蒸気供給が行えます。
外燃機関方式
外燃機関方式は、ボイラーで蒸気を作り、その蒸気でタービンを回して発電する方式です。燃料を機関外部で燃焼させるため「外燃機関」と呼ばれます。
この方式の特徴は、多様な燃料を使用できることです。天然ガスや石油だけでなく、木質バイオマスや廃棄物なども燃料として活用できるため、環境配慮と経済性を両立できます。また、発電後の蒸気をそのまま工程用蒸気として利用できるため、製紙業や化学工業など蒸気を大量に使用する産業での導入効果が高くなります。
運転特性としては、起動に時間がかかるものの、一度安定運転に入ると長時間の連続運転が可能で、メンテナンス頻度も比較的少ないという利点があります。
燃料電池方式
燃料電池方式は、水素と酸素の化学反応を利用して直接電気を発生させる最も効率的な発電方式です。燃焼プロセスを経ないため、発電効率が40~60%と高く、排出されるのは水と熱のみという環境にやさしい特徴があります。
家庭用燃料電池「エネファーム」は、都市ガスから水素を取り出して発電し、同時に60~80℃の温水を生成します。一般的な家庭の電力需要の約6~7割、給湯需要の約8~9割をまかなうことができ、大幅な光熱費削減につながります。
産業用燃料電池は、数百kWから数MWの大容量システムも開発されており、データセンターや工場などでの導入が進んでいます。発電時の騒音が極めて小さく、有害物質の排出もないため、都市部での設置にも適しています。
コージェネレーション導入のメリット
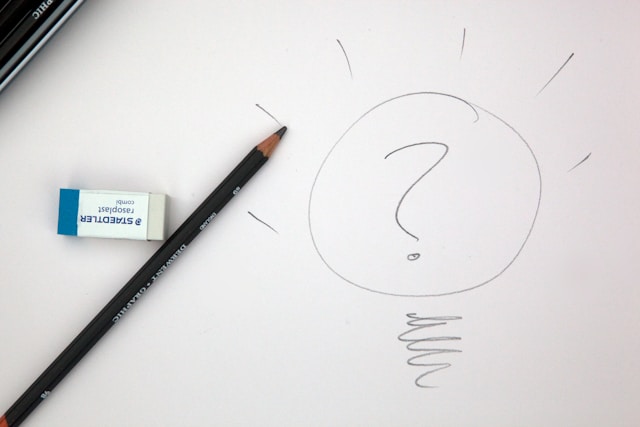
コージェネレーションシステムを導入することで、エネルギー効率の向上、経済性の改善、エネルギーセキュリティの強化など、多方面にわたるメリットを得ることができます。特に電気と熱の両方を必要とする施設では、その効果は顕著に現れます。
これらのメリットは単独で現れるものではなく、相互に関連し合いながら総合的な価値を生み出します。例えば、省エネルギー効果により運営コストが削減され、それによって初期投資の回収期間も短縮されるという好循環が生まれます。
省エネルギー効果
コージェネレーションの最大のメリットは、従来システムと比較して格段に高いエネルギー効率を実現できることです。一般的な火力発電所の発電効率は約40%ですが、コージェネレーションでは排熱利用により総合効率を75~80%まで向上させることができます。
この効率向上により、同じエネルギー消費量でより多くの電気と熱を得ることができ、結果として一次エネルギー消費量を20~30%削減することが可能です。また、エネルギー効率の向上は直接的に二酸化炭素排出量の削減につながるため、環境負荷の軽減にも大きく貢献します。
具体例として、年間電力使用量3,000MWhの中規模オフィスビルでコージェネレーションを導入した場合、従来システムと比較して年間約600~900MWh相当の一次エネルギーを削減できる計算になります。
経済性とコスト削減
コージェネレーションの導入により、電気料金とガス料金の両方で大幅なコスト削減を実現できます。自家発電により電力会社からの電気購入量を削減できるだけでなく、多くのガス会社がコージェネレーション導入者向けの優遇料金プランを提供しているためです。
また、電力のピーク時間帯にコージェネレーションを稼働させることで、電力の基本料金を決める最大デマンド電力を抑制できます。これにより基本料金の削減効果も期待でき、年間の電気料金を15~25%程度削減することが可能です。
さらに、売電制度を活用すれば、余剰電力を電力会社に売却することで収益を得ることもできます。特に再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の対象となるバイオマス燃料を使用する場合は、高い売電価格が適用されるため、投資回収効果が高くなります。
災害時の電源確保
コージェネレーションシステムは、災害時の非常用電源として重要な役割を果たします。地震や台風などで電力系統からの電気供給が停止した場合でも、燃料さえ確保できれば継続的に電力と熱を供給することができます。
この特徴は、病院や福祉施設、データセンターなど、電力供給の停止が重大な影響を与える施設では特に重要です。実際に、東日本大震災の際には、コージェネレーションを導入していた多くの施設で、停電期間中も正常な運営を継続できた事例が報告されています。
また、平常時においても電力系統との連系により電源の二重化を図ることができ、電力供給の信頼性向上にも寄与します。一定の条件を満たしたコージェネレーションシステムは、消防法上の非常電源としても認められており、防災設備としての価値も高く評価されています。
導入時の注意点とデメリット
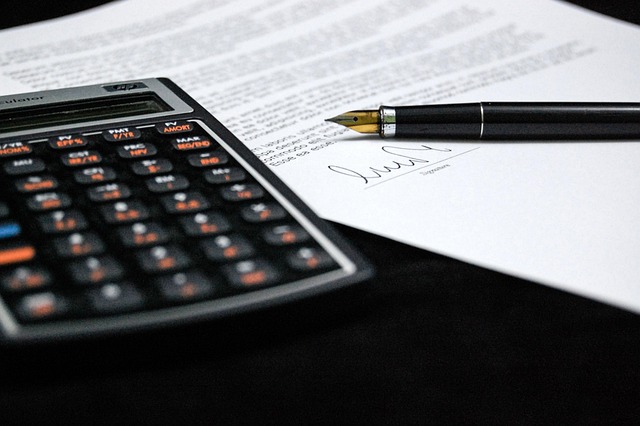
コージェネレーションシステムには多くのメリットがある一方で、導入前に十分検討すべき課題も存在します。特に初期投資の大きさや運用面での制約については、事前に詳しく検討することが成功の鍵となります。
これらの課題を理解した上で適切な計画を立てることで、コージェネレーションの持つポテンシャルを最大限に活用することができます。導入を検討する際は、専門家によるエネルギー診断や経済性評価を行うことが重要です。
初期投資の課題
コージェネレーションシステムの最大の課題は、高額な初期投資です。システム本体の価格に加えて、設置工事費、電気・ガス設備の改修費、各種申請手続き費用などを含めると、相当な金額になります。
例えば、中小規模の業務用ガスエンジン(100kW級)では、設備費と工事費を合わせて3,000万円から5,000万円程度の投資が必要になることが一般的です。家庭用のエネファームでも150万円から250万円程度の費用がかかります。
このため、投資回収期間は通常5年から10年程度と長期になり、金利負担や設備の陳腐化リスクも考慮する必要があります。ただし、国や自治体の補助金制度を活用することで、初期投資負担を軽減できる場合があります。
設置・運用時の制約
コージェネレーションシステムの設置には、法的手続きや技術的制約があります。一定規模以上のシステムでは、電気事業法や ガス事業法に基づく届出や検査が必要になり、専門の技術者による定期点検も義務付けられています。
また、システムを効率的に運用するためには、電気と熱の需要バランスが重要です。発電量に対して熱需要が少ない場合、余剰熱を有効活用できず、期待したエネルギー効率を得られないことがあります。このため、導入前には詳細な需要分析と最適なシステム容量の検討が不可欠です。
メンテナンス面では、従来の電気設備に加えて熱回収設備の保守も必要になるため、維持管理コストが増加します。また、故障時には電気と熱の両方の供給が停止するリスクもあるため、バックアップ設備の検討も重要です。
コージェネレーションの活用事例と将来性

コージェネレーションは産業分野から家庭まで幅広い用途で活用されており、技術の進歩とともにその適用範囲は着実に拡大しています。カーボンニュートラルの実現に向けて、今後さらなる普及が期待される重要な技術の一つです。
現在、日本国内では累積設備容量が約900万kWに達しており、年間約3,000万トンの二酸化炭素削減効果をもたらしています。これは日本全体の二酸化炭素排出量の約2.5%に相当する規模です。
産業・業務用での活用
製造業では、工場の生産プロセスで必要な電気と蒸気を同時に供給するコージェネレーションが広く導入されています。特に製紙業、化学工業、食品製造業など、大量の蒸気を消費する業種での導入効果が高く、エネルギーコストの大幅削減を実現しています。
業務用分野では、病院、ホテル、オフィスビル、商業施設などでの導入が進んでいます。病院では24時間安定した電力と温水供給が必要なため、コージェネレーションの特性が活かされています。また、ホテルでは客室の電力と給湯・暖房を効率的に供給でき、運営コストの削減と環境配慮を両立できます。
空港や大型ショッピングセンターなど、電力と熱の大量消費施設では、メガワット級の大型コージェネレーションシステムが導入されており、地域のエネルギーセンターとしての役割も果たしています。
家庭用システムの普及
家庭用燃料電池「エネファーム」の普及により、一般家庭でもコージェネレーションが身近な存在になっています。2023年時点で国内設置台数は約40万台を超え、年間約2万台のペースで増加しています。
エネファームは、一般的な家庭の電力需要の約60~70%、給湯需要の約80~90%をまかなうことができ、年間の光熱費を約10万円削減できるとされています。また、停電時でも継続的に電力と給湯を供給できるため、災害に強い住宅としての価値も高く評価されています。
最近では、太陽光発電との組み合わせによる「ダブル発電」システムも普及しており、より一層の省エネ効果と経済メリットを実現できるようになっています。
カーボンニュートラルへの貢献
政府が掲げる2050年カーボンニュートラル目標の実現に向けて、コージェネレーションは重要な役割を担っています。高効率なエネルギー利用により化石燃料の消費量を削減するとともに、将来的には水素燃料やバイオマス燃料の活用により、さらなる脱炭素化が期待されています。
水素コージェネレーションの技術開発も進んでおり、純粋な水素を燃料とすることで、運転時の二酸化炭素排出量をゼロにすることが可能です。また、再生可能エネルギーの変動性を補完する調整電源としての活用も検討されており、分散型エネルギーシステムの中核技術として位置づけられています。
まとめ
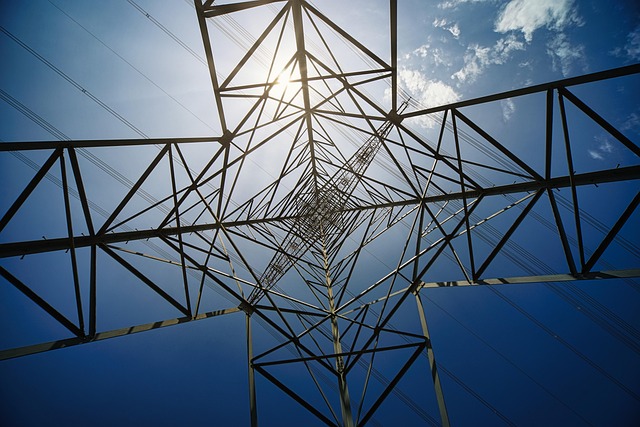
コージェネレーションは、一つの燃料から電気と熱を同時に生み出す革新的なエネルギーシステムです。従来の発電方式と比較して約2倍のエネルギー効率を実現でき、大幅な省エネ効果と経済メリットをもたらします。
内燃機関、外燃機関、燃料電池の3つの方式があり、用途や規模に応じて最適なシステムを選択できます。産業用から家庭用まで幅広い分野で活用されており、特に電気と熱の両方を必要とする施設では高い導入効果が期待できます。
初期投資の大きさや運用面での制約といった課題はありますが、長期的な経済性と環境性を総合的に評価すれば、多くの場合で導入メリットが上回ります。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、コージェネレーションの重要性は今後ますます高まっていくと予想されます。
参照元
・資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/cogeneration.html
・資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/other/cogeneration/
・一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター https://www.ace.or.jp/web/chp/chp_0010.html
・国立環境研究所 環境展望台 https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=8
・東京電力エナジーパートナー株式会社 https://www.tepco.co.jp/ep/private/glossary/cogeneration-system.html




