私たちが毎日食べている魚や海藻は、どこから来ているのでしょうか。海の恵みは無限に続くものだと思われがちですが、実は世界の水産資源の3分の1以上が危機的な状況にあります。このまま何も対策を取らなければ、将来の子どもたちは今のように豊かな海の幸を味わえなくなるかもしれません。そこで注目されているのが「持続可能な漁業」という考え方です。
この記事で学べるポイント
- 持続可能な漁業の基本的な考え方と重要性
- 世界と日本の水産資源が抱える深刻な問題の実態
- 海の豊かさを守るために私たちができる具体的な行動
持続可能な漁業とは何か?基本的な考え方を理解しよう
 持続可能な漁業とは、海に十分な水産資源を残しながら、生態系への影響を最小限に抑えて漁獲を行う漁業のことです。つまり、今の世代が魚を獲って食べることができるだけでなく、将来の世代も同じように海の恵みを受け続けられるような漁業を指します。
持続可能な漁業とは、海に十分な水産資源を残しながら、生態系への影響を最小限に抑えて漁獲を行う漁業のことです。つまり、今の世代が魚を獲って食べることができるだけでなく、将来の世代も同じように海の恵みを受け続けられるような漁業を指します。
海の資源を守りながら続けられる漁業
持続可能な漁業の考え方は、資金運用によく例えられます。例えば、ある海域に100トンのカツオが生息していて、1年間で新たに3トンのカツオが成長して加わる場合、年間の漁獲量を3トン以内に抑えることで、カツオの総数を維持できます。このように、魚が自然に増える分だけを獲ることで、魚の種類や数を将来にわたって保つことができるのです。
しかし、持続可能な漁業は単に魚を獲りすぎないことだけを意味するわけではありません。漁業の方法や使用する道具、漁業が行われる場所の環境保護なども含めた総合的な取り組みが必要です。海洋生態系は複雑につながり合っているため、一つの種類の魚が減ると、他の海洋生物にも影響が及ぶ可能性があります。
将来の世代も魚を食べ続けられるために
世界では38万人もの人々が漁業に従事しており、水産物は世界の3分の1以上の人々にとって重要なタンパク源となっています。特に島国である日本では、古くから海との関わりが深く、魚や海藻は日本人の食生活に欠かせない存在です。
持続可能な漁業を実現することで得られる利益は計り知れません。適切な管理が行われれば、現在よりも年間1600万トン多くの水産物が生産できると推定されており、これは世界の7200万人分のタンパク質需要に相当する量です。また、水産物は陸上で生産される動物性タンパク質と比べて二酸化炭素の排出量が少ないため、地球温暖化対策にも貢献できます。
世界と日本の水産資源が直面している深刻な問題
 国連食糧農業機関(FAO)の最新データによると、世界の水産資源の現状は非常に深刻です。2020年の世界の水産物生産量は2億1400万トン、消費量は1億5700万トンと過去最高を記録しましたが、その一方で持続可能な範囲を超えて漁獲されている水産資源が急増しています。
国連食糧農業機関(FAO)の最新データによると、世界の水産資源の現状は非常に深刻です。2020年の世界の水産物生産量は2億1400万トン、消費量は1億5700万トンと過去最高を記録しましたが、その一方で持続可能な範囲を超えて漁獲されている水産資源が急増しています。
世界の水産資源の3分の1が危機的状況
FAOの継続的な調査によると、生物学的に持続可能なレベルで漁獲されている海洋水産資源の割合は年々減少しており、2017年時点で66%となっています。これは裏を返すと、世界の水産資源の3分の1以上が持続可能性の限界を超えて漁獲されていることを意味します。
この背景には、世界人口の増加と生活水準の向上による魚介類消費量の急激な増加があります。世界全体の1人あたりの魚介類年間消費量は、1961年の9.0キログラムから2019年には20.5キログラムまで約2倍に増加しました。特に中国では約9倍、インドネシアでは約4倍に達するなど、新興国での消費拡大が顕著です。2030年には1人あたりの供給量が21.4キログラムになると予想されており、今後も需要の増加が続く見込みです。
日本の海でも約半数の魚種が枯渇状態
日本周辺の状況も決して楽観できません。水産庁の資料によると、日本周辺で漁獲される50魚種84系群のうち、約49%が枯渇している状態で、豊富とされるものはわずか17%に過ぎません。これは世界の海と同様に、日本の水産資源も非常に危機的な状況にあることを示しています。
日本の漁獲量は1984年の1282万トンをピークに減少を続けており、近年は400万トン台まで落ち込んでいます。それにもかかわらず、日本の食卓には依然として豊富な魚が並んでいるのは、輸入に頼る割合が増加しているためです。現在、国内で消費されている魚介類のうち約半分を輸入に依存しており、日本の水産物輸入金額は約1.8兆円で世界第2位となっています。
しかし、輸入に頼ることで新たな問題も生まれています。輸送に伴う二酸化炭素排出量の増加は地球温暖化の一因となり、また輸入先の国々でも同様に水産資源の枯渇が進んでいるため、根本的な解決にはなりません。
持続可能な漁業を実現するための具体的な取り組み
 水産資源の危機的状況を改善するため、世界各国では持続可能な漁業を実現するためのさまざまな取り組みが進められています。これらの取り組みは、科学的な根拠に基づいた資源管理と、海洋環境への配慮を両立させることを目的としています。
水産資源の危機的状況を改善するため、世界各国では持続可能な漁業を実現するためのさまざまな取り組みが進められています。これらの取り組みは、科学的な根拠に基づいた資源管理と、海洋環境への配慮を両立させることを目的としています。
科学的な資源管理と漁獲制限
持続可能な漁業の核となるのが、科学的なデータに基づいた資源管理です。各国の水産研究機関では、魚の個体数や繁殖状況、海洋環境の変化などを継続的に調査し、適切な漁獲量の上限(漁獲可能量)を設定しています。
特に重要なのが「漁獲制御ルール」と呼ばれる予防的措置です。これは水産資源が減少した場合に自動的に漁獲量を減らす仕組みで、魚の個体数が危険な水準まで下がる前に対策を講じることができます。例えば、ある魚種の個体数が基準値を下回った場合、翌年の漁獲量を30%削減するといったルールを事前に決めておくのです。
日本でも2020年に漁業法が改正され、科学的根拠に基づく資源管理が強化されました。主要な魚種については漁獲可能量(TAC)を設定し、漁業者に配分する個別漁獲割当(IQ)制度の導入も進められています。これにより、各漁業者が自分に割り当てられた分だけを計画的に漁獲できるようになり、乱獲を防ぐ効果が期待されています。
海洋環境を守る漁法の改善
持続可能な漁業では、目的の魚以外を誤って捕獲してしまう「混獲」を減らすことも重要な課題です。特に、ウミガメや海鳥、海洋哺乳類などの保護が必要な生物が漁網にかかってしまうことは、海洋生態系全体に深刻な影響を与えます。
この問題を解決するため、漁業技術の革新が進められています。例えば、マグロ漁で使われる延縄漁業では、ウミガメが釣り針にかかりにくい「サークルフック」と呼ばれる特殊な釣り針の使用が推奨されています。また、イルカの混獲を防ぐために開発された「ピンガー」という音響装置を漁網に取り付けることで、イルカに漁網の存在を知らせる技術も実用化されています。
さらに、漁網が海に放置されたり紛失したりする「ゴーストフィッシング」も深刻な問題となっています。これらの網は長期間海に残り続け、魚や海洋生物を傷つけてしまいます。そのため、生分解性の漁網の開発や、GPS機能付きの漁具による追跡システムの導入など、環境負荷を軽減する技術開発が活発に行われています。
MSC認証など、持続可能な漁業を支える仕組み
 持続可能な漁業を世界的に推進するため、国際的な認証制度や規制の枠組みが整備されています。これらの仕組みは、消費者が持続可能な水産物を選択できるようにするとともに、漁業者に改善のインセンティブを与える役割を果たしています。
持続可能な漁業を世界的に推進するため、国際的な認証制度や規制の枠組みが整備されています。これらの仕組みは、消費者が持続可能な水産物を選択できるようにするとともに、漁業者に改善のインセンティブを与える役割を果たしています。
MSC認証の3つの原則
海洋管理協議会(MSC)は、持続可能な漁業の世界的な推進を目的として設立された国際機関です。MSCが定める漁業認証規格は、持続可能な漁業の国際基準として広く認められており、以下の3つの原則に基づいています。
第1原則は「持続可能な魚の個体数」です。漁業が対象とする魚の個体数が持続可能なレベルに維持されており、過剰漁獲が行われていないことを求めています。具体的には、科学的な調査に基づいて魚の個体数を把握し、将来にわたって漁業を継続できる範囲での漁獲を行うことが必要です。
第2原則は「海洋生態系への最小限の環境インパクト」です。漁業活動が海洋環境や他の海洋生物に与える影響を最小限に抑えることを要求しています。混獲の削減、海底環境の保護、食物連鎖への配慮などが含まれます。
第3原則は「効果的なガバナンス」です。漁業が適切な法規制の下で管理され、地域や国際的なルールを遵守していることを求めています。また、漁業者や地域コミュニティが資源管理に積極的に参加し、透明性のある意思決定が行われることも重要です。
MSC認証を取得した漁業で獲られた水産物には「海のエコラベル」が付けられ、消費者が持続可能な水産物を識別できるようになっています。現在、世界で約400の漁業がMSC認証を取得しており、認証水産物の市場規模は年々拡大しています。
IUU漁業対策と国際的な取り組み
持続可能な漁業の最大の脅威となっているのが、IUU漁業です。IUUとは、違法(Illegal)、無報告(Unreported)、無規制(Unregulated)漁業の頭文字を取ったもので、国際的なルールや各国の法律に違反した漁業活動を指します。
IUU漁業による年間漁獲量は1100万トンから2600万トンに上ると推定されており、これは世界の総漁獲量の約15~30%にあたります。IUU漁業は適切な資源管理を困難にし、合法的に漁業を行う人々の経済的損失を招くだけでなく、海洋生態系にも深刻な影響を与えています。
この問題に対応するため、国際的な協力体制が構築されています。国連では2030年までにIUU漁業を終了させることを目標とし、地域漁業管理機関(RFMO)を通じた監視・規制の強化が進められています。また、2019年にはAPEC海洋・漁業作業部会で「IUU漁業対策に関するロードマップ」が承認されるなど、国際的な取り組みが加速しています。
日本でも2022年12月に「水産流通適正化法」が施行され、輸入水産物の流通過程での透明性確保が義務付けられました。この法律により、指定された魚種については漁獲から消費まで全ての段階で記録を保持することが求められ、IUU漁業で獲られた水産物の流入を防ぐ水際対策が強化されています。
私たちにできること:持続可能な漁業を応援する方法
 持続可能な漁業の推進は、漁業者や政府だけの責任ではありません。消費者である私たち一人ひとりの選択と行動が、海の未来を左右する重要な要素となっています。日常生活の中で実践できる具体的な方法を知ることで、誰でも持続可能な漁業を応援することができます。
持続可能な漁業の推進は、漁業者や政府だけの責任ではありません。消費者である私たち一人ひとりの選択と行動が、海の未来を左右する重要な要素となっています。日常生活の中で実践できる具体的な方法を知ることで、誰でも持続可能な漁業を応援することができます。
エコラベル付き水産物の選択
最も身近で効果的な方法は、買い物の際にエコラベルが付いた水産物を選ぶことです。MSC認証の「海のエコラベル」をはじめ、日本国内でもMEL(マリン・エコラベル・ジャパン)やASC(水産養殖管理協議会)認証など、持続可能な水産物を示すマークがあります。
これらのエコラベルは、厳格な審査を通過した漁業や養殖業で生産された水産物にのみ付けられています。スーパーマーケットや飲食店でエコラベル付きの商品を選ぶことで、持続可能な漁業を行う事業者を経済的に支援し、より多くの漁業者が持続可能な方法に転換するきっかけを作ることができます。
現在、日本国内でもエコラベル付き水産物の取り扱いが増えており、大手スーパーチェーンや回転寿司チェーンでも積極的に導入されています。商品を購入する際は、パッケージや店頭表示でエコラベルの有無を確認する習慣をつけることが大切です。
また、旬の魚を選ぶことも持続可能性に貢献します。旬の時期の魚は自然のサイクルに合わせて豊富に存在するため、資源への負荷が少なく、栄養価も高くなります。季節ごとの旬の魚を知り、その時期に応じた魚料理を楽しむことで、美味しさと持続可能性を両立できます。
海洋環境保護への意識向上
持続可能な漁業を支援するためには、海洋環境全体の保護についても理解を深めることが重要です。海洋プラスチックごみの問題、地球温暖化による海水温上昇、海洋酸性化など、さまざまな環境問題が水産資源に影響を与えています。
日常生活でできる海洋環境保護の取り組みとしては、使い捨てプラスチック製品の使用を減らし、適切なごみの分別とリサイクルを心がけることが挙げられます。また、海岸清掃活動への参加や、海洋環境保護に取り組む団体への寄付なども効果的な支援方法です。
水産資源や海洋環境に関する正しい知識を身につけることも大切です。WWFジャパンや海洋管理協議会(MSC)、水産庁などの信頼できる情報源から最新の情報を入手し、家族や友人と共有することで、社会全体の意識向上につながります。
さらに、地域の漁業関係者や海洋研究者と交流する機会を作ることもお勧めします。漁業組合や水族館、大学が開催するイベントやセミナーに参加することで、現場の声を直接聞き、地域の海や漁業が抱える課題について理解を深めることができます。
まとめ
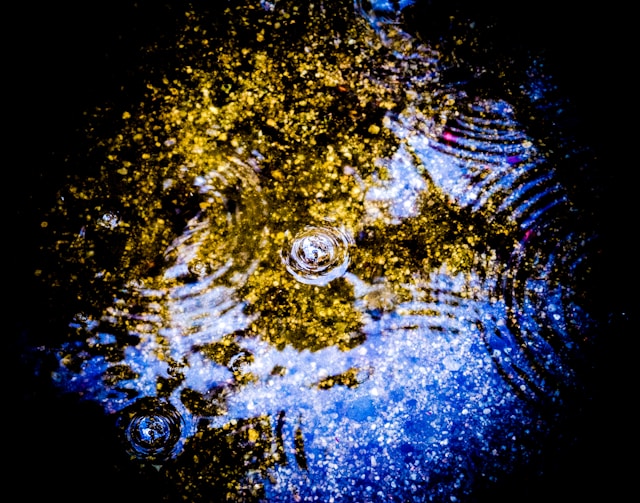 持続可能な漁業は、現在と未来の世代が共に海の恵みを享受するために不可欠な取り組みです。世界の水産資源の3分の1以上が危機的状況にある中、科学的な資源管理、環境に配慮した漁法の導入、国際的な認証制度の普及など、多角的なアプローチが進められています。
持続可能な漁業は、現在と未来の世代が共に海の恵みを享受するために不可欠な取り組みです。世界の水産資源の3分の1以上が危機的状況にある中、科学的な資源管理、環境に配慮した漁法の導入、国際的な認証制度の普及など、多角的なアプローチが進められています。
私たち消費者にも重要な役割があります。エコラベル付き水産物の選択、旬の魚を楽しむ食生活、海洋環境保護への積極的な参加など、日常生活の中でできることは数多くあります。一人ひとりの小さな行動が積み重なることで、海の豊かさを守り、持続可能な漁業の実現に貢献することができるのです。
海は地球全体でつながっており、その恩恵は国境を越えて私たちに届けられています。今こそ、海の未来を守るための行動を始める時です。持続可能な漁業への理解と支援を通じて、豊かな海を次の世代に引き継いでいきましょう。
参照元
・Marine Stewardship Council(海洋管理協議会) https://www.msc.org/jp/what-we-are-doing/our-approach-JP/what-is-sustainable-fishing-JP
・WWFジャパン https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3554.html
・IDEAS FOR GOOD https://ideasforgood.jp/glossary/sustainable-fishing/
・スペースシップアース https://spaceshipearth.jp/sustainable_fishery/
・mymizu https://www.mymizu.co/blog-ja/eco-with-kanae-sustainable-fishery





