地球温暖化対策が急務となる中、発電所や工場から排出されるCO2を大気に放出せず、地下深くに閉じ込める技術「CCS」が世界的に注目されています。この革新的な技術は、カーボンニュートラル達成の切り札として期待されており、日本でも大規模な実証実験が進行中です。
この記事で学べるポイント
- CCSの基本的な仕組みと地球温暖化対策における重要性
- CO2を回収から貯留まで行う具体的な技術プロセス
- 日本や世界各国で進むCCSの実用化に向けた取り組み状況
CCS(CO2回収・貯留)とは何か

CCSの基本的な定義
CCSとは「Carbon dioxide Capture and Storage」の略語で、日本語では「二酸化炭素回収・貯留」技術と呼ばれます。この技術は、火力発電所や製油所、化学工場、セメント工場などの産業施設から排出されるCO2を、他の気体から分離して回収し、地下深くの安定した地層に長期間貯留する一連のプロセスを指します。
従来は大気中に放出されていたCO2を物理的に取り除き、地中に閉じ込めることで、温室効果ガスの排出量を大幅に削減することが可能になります。CCSは単純にCO2を減らすだけでなく、回収したCO2を化学原料として再利用する技術と組み合わせることで、より効果的な脱炭素化を実現できる技術として位置づけられています。
なぜ注目されているのか
CCSが世界的に注目される最大の理由は、2050年カーボンニュートラル達成において不可欠な技術だからです。再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率の向上だけでは、すべての産業分野でCO2排出をゼロにすることは困難です。特に製鉄業やセメント製造業、化学工業などの重工業では、製造プロセス上どうしてもCO2の排出が避けられません。
例えば、約27万世帯分の電力を供給する石炭火力発電所にCCSを導入した場合、年間約340万トンものCO2排出を防ぐことができます。これは日本の年間CO2排出量の約0.3%に相当する規模であり、複数の施設への導入により大きな削減効果が期待できます。
また、CCSは再生可能エネルギーの普及促進にも貢献します。太陽光や風力発電の余剰電力を利用してCO2から燃料を製造することで、エネルギーの貯蔵問題を解決し、再生可能エネルギーのさらなる導入を後押しする効果があります。
CCSの仕組みと技術

CO2の回収方法
CCSにおけるCO2回収は、主に5つの技術方式があります。最も代表的な方法は「化学吸収法」で、アミン水溶液と呼ばれるアルカリ性の薬剤を使用します。この薬剤は温度によってCO2を吸収したり放出したりする特性があり、低温時にCO2を吸収し、加熱することでCO2だけを効率的に分離回収できます。
その他の方法として「物理吸収法」「膜分離法」「固体吸収法」「深冷分離法」があり、それぞれ排出源のCO2濃度や条件に応じて最適な技術が選択されます。現在のCCS技術では、CO2濃度が7%から50%程度の排ガスが対象となっており、大気中の低濃度CO2(約0.04%)の直接回収は技術開発が進行中の段階です。
輸送・貯留の流れ
回収されたCO2は、専用パイプラインや船舶、タンカーを使って貯留地点まで輸送されます。輸送時には、CO2を高圧で圧縮して液体状態にすることで、効率的な運搬が可能になります。日本のように島国で長距離輸送が必要な場合は、船舶輸送技術の確立が重要な課題となっています。
貯留地点に到着したCO2は、地下800メートル以上の深度にある貯留層まで専用の井戸を通じて圧入されます。この深度では、CO2は高い圧力により液体に近い状態を保ち、岩石の微細な隙間に浸透して安定的に貯留されます。科学的な調査によると、適切に管理された貯留層では、CO2を1000年以上にわたって安全に閉じ込めることが可能とされています。
貯留場所の条件
CO2を安全に貯留するためには、特定の地質条件を満たす場所が必要です。まず、隙間の多い砂岩などでできた「貯留層」があることが条件です。この貯留層は、CO2を大量に蓄積できる空隙を持つ必要があります。
さらに重要なのが、貯留層の上部を覆う「遮蔽層」の存在です。この層は泥岩などの緻密な岩石でできており、CO2が地表に漏れ出すことを防ぐ役割を果たします。日本では環境省による適地調査が実施されており、2022年時点で国内11拠点において約160億トンのCO2貯留が可能と推定されています。これは日本の年間CO2排出量の約140年分に相当する膨大な貯留ポテンシャルです。
CCSの効果とメリット

CCSの導入により、地球温暖化対策と産業の持続可能な発展の両立が期待されています。この技術がもたらす効果は、単なるCO2削減にとどまらず、エネルギー分野全体の構造変化を促進する可能性を秘めています。
温室効果ガス削減効果
CCSの最も直接的な効果は、大幅なCO2排出削減です。従来の火力発電所にCCSを適用した場合、CO2排出量を80%から90%削減することが可能です。これは、石炭火力発電所であれば、通常1キロワット時あたり約900グラムのCO2を排出するところを、90グラム程度まで削減できることを意味します。
日本全体で見ると、環境省の調査では国内の貯留ポテンシャルは最大約2400億トンと推定されており、これは現在の日本の年間CO2排出量の約200年分に相当します。火力発電所や製鉄所、化学工場などの主要排出源が沿岸部に集中している日本の地理的特徴も、海底への輸送エネルギーを抑制できる利点となっています。
再生可能エネルギーとの連携
CCSは再生可能エネルギーの普及を加速させる重要な役割も担っています。太陽光発電や風力発電は天候に左右されるため、発電量が需要を上回る場合があります。この余剰電力の有効活用が、再生可能エネルギー普及の課題の一つでした。
CCSと組み合わせることで、余剰電力を使って水素を製造し、回収したCO2と化学反応させてメタンを生成できます。メタンは既存の都市ガスインフラで利用可能なため、新たなインフラ整備を待たずに余剰電力を貯蔵・活用できます。これにより、再生可能エネルギーの導入拡大が促進され、脱炭素社会の実現が加速されると期待されています。
産業への影響
CCSの導入は、これまで脱炭素化が困難とされてきた重工業分野に新たな可能性をもたらします。セメント製造業では、原料の石灰石を焼成する際に必然的にCO2が発生しますが、CCSにより排出を大幅に削減できます。製鉄業においても、コークスを使った製鉄プロセスから発生するCO2を回収・貯留することで、産業活動を継続しながら脱炭素化を進められます。
また、回収したCO2を化学原料として活用する「カーボンリサイクル」により、新たな産業創出も期待されています。CO2から製造したメタノールやプラスチック原料は、従来の化石燃料由来製品の代替として利用でき、循環型の産業構造の構築に貢献します。
CCSの課題と現状

一方で、CCSの本格的な社会実装には解決すべき課題も多く存在します。技術的な完成度向上とコスト削減、そして制度整備が重要な鍵となっています。
技術的な課題
現在のCCS技術では、CO2の分離・回収プロセスが最大の技術的課題となっています。化学吸収法で使用するアミン水溶液は、CO2を分離する際に大量のエネルギーを必要とし、発電所の出力を20%から30%低下させる場合があります。これは、CCS導入により実質的な発電効率が大幅に下がることを意味します。
また、日本では島国という地理的条件により、CO2の船舶輸送技術の確立が不可欠です。しかし、大量のCO2を安全に海上輸送する技術は世界的にも実施例が少なく、輸送容器の開発や安全基準の策定など、多くの技術的課題が残されています。
コストの問題
CCSの最大の実用化阻害要因は、高いコストです。現在、CO2を1トン回収・貯留するために約4000円から8000円のコストがかかると推定されており、これは発電コストを大幅に押し上げる要因となっています。特に、既存の発電所にCCSを後付けで導入する場合、設備投資と運用コストがさらに高くなる傾向があります。
コスト削減のためには、技術開発による効率向上と大規模化による設備コストの低減が必要です。政府の支援制度や炭素税などの政策的な後押しも、CCSの経済性向上には不可欠な要素となっています。
法的整備の必要性
日本では、CCSに特化した法律が整備されておらず、現在は複数の既存法律を適用して運用している状況です。地下へのCO2貯留に関する所有権や責任の所在、長期的な安全管理の責任者など、多くの法的課題が未解決のままです。
特に、貯留したCO2が万が一漏洩した場合の責任の所在や、数十年から数百年にわたる長期管理の責任体制については、明確な法的枠組みの確立が急務となっています。欧米では政府による積極的な支援制度が整備されており、日本でも同様の制度設計が求められています。
日本と世界のCCSの取り組み
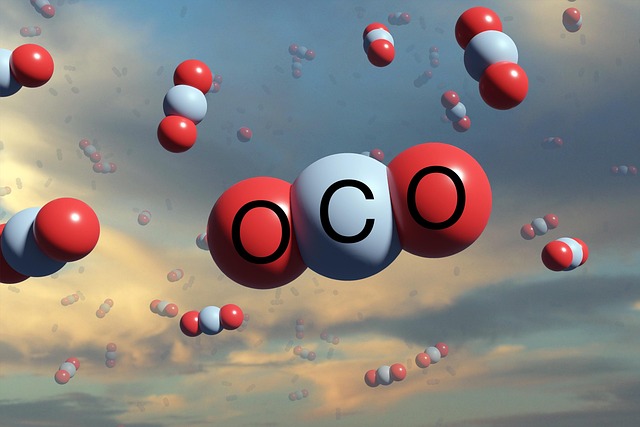
世界各国がカーボンニュートラル達成に向けてCCSの実用化を急ぐ中、技術開発と実証実験が加速しています。特に日本では独自の地理的条件を活かしたCCS技術の確立を目指しています。
日本の実証実験
日本におけるCCSの最大の実証プロジェクトは、北海道苫小牧市で実施された大規模実証実験です。2012年から2019年まで実施されたこの実証実験では、製油所から発生したCO2を分離・回収し、海底下の地層に累計約30万トンのCO2を貯留することに成功しました。
この実証実験により、日本の地質条件でのCO2貯留の安全性が実証され、長期的なモニタリング技術も確立されました。現在も貯留したCO2の動向を継続的に監視しており、漏洩などの異常は確認されていません。
環境省では2030年以降の本格的なCCS事業開始に向けて、洋上浮体からのCO2圧入技術の実証や、新しい分離回収技術の開発を進めています。福岡県大牟田市では大規模なCO2分離回収実証設備が稼働し、アミン系吸収剤を使った実証運転が実施されています。
海外の先進事例
世界のCCS開発は急速に拡大しており、2022年時点で196のプロジェクトが進行中です。そのうち30プロジェクトが既に操業を開始し、年間約3150万トンのCO2を回収しています。
アメリカでは政府による税額控除制度が拡充され、CCS事業への投資が急激に増加しています。ノルウェーでは1990年代からCCS技術を商業運用しており、北海の海底下にこれまで約2000万トンのCO2を貯留した実績があります。
カナダでは石油増進回収と組み合わせたCCUSプロジェクトが多数稼働し、CO2を貯留しながら原油生産を継続する技術が確立されています。これらの成功事例は、CCSが技術的に実現可能であることを証明しています。
国際連携の動向
CCS技術の普及には国際協力が不可欠であり、各国間での技術共有や共同研究が活発化しています。日本は2015年から米国との共同研究開発を推進し、2017年にはCCUSまで協力範囲を拡大しました。
アジア太平洋地域では、インドネシアやマレーシアが積極的にCCS開発を進めており、日本企業との技術協力が拡大しています。特にインドネシアでは、天然ガス田からのCO2を地中貯留するプロジェクトが本格稼働し、年間約130万トンのCO2を処理しています。
CCSの今後の展望

CCS技術は2030年代の本格的な社会実装に向けて、技術革新とコスト削減が急速に進んでいます。将来の脱炭素社会における重要な基盤技術として、さらなる発展が期待されています。
技術開発の方向性
次世代CCS技術では、エネルギー効率の大幅な改善が重要な目標となっています。従来のアミン水溶液に代わる固体吸収材の開発により、CO2分離に必要なエネルギーを現在の半分以下に削減する技術開発が進んでいます。
また、大気中の低濃度CO2を直接回収するDAC(Direct Air Capture)技術の実用化も進展しています。この技術により、発電所や工場などの大規模排出源だけでなく、分散した排出源からのCO2回収も可能になり、CCSの適用範囲が大幅に拡大される見込みです。
社会実装への道筋
日本政府は2030年のCCS事業開始を目標に、法制度の整備とコスト削減に向けた支援策を検討しています。CO2貯留権の設置や事業者の責任範囲の明確化など、事業化に必要な制度基盤の構築が進められています。
経済性の確保に向けては、炭素税やカーボンプライシングの導入により、CCSの経済的価値を適正に評価する仕組みづくりが重要となります。また、複数の企業が共同でCCSインフラを利用するバリューチェーンの構築により、コスト分散と事業リスクの軽減が図られています。
期待される影響
CCSの本格的な普及により、日本のCO2排出量を2030年までに現在の46%削減、2050年のカーボンニュートラル達成が現実的な目標となります。特に、脱炭素化が困難とされてきた重工業分野での大幅な排出削減が可能になり、産業構造の根本的な変革が期待されています。
また、CCSと再生可能エネルギーの組み合わせにより、エネルギー貯蔵問題が解決され、再生可能エネルギーの導入拡大が加速される見込みです。これにより、エネルギー安全保障の強化と脱炭素化の両立が実現し、持続可能な社会の構築に大きく貢献することが期待されています。
CCS技術は、地球温暖化対策の切り札として、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。技術開発の進展と制度整備により、2030年代には本格的な社会実装が始まり、脱炭素社会の実現に向けた重要な一歩となることが期待されます。
参照元
・経済産業省 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ccus.html
・環境省 https://www.env.go.jp/earth/ccs/index.html
・独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC) https://www.jogmec.go.jp/publish/plus_vol09.html





