地球温暖化対策として注目を集める「炭素クレジット」。企業の脱炭素化や2050年カーボンニュートラル実現に向けて、重要な役割を果たすとされています。しかし、その仕組みや効果について正しく理解している人は多くありません。炭素クレジットは単なる「排出権の売買」ではなく、実際の温室効果ガス削減活動を促進する仕組みです。
この記事で学べるポイント
- 炭素クレジットの基本的な仕組みと生まれる流れ
- 日本のJ-クレジット制度と国際制度の違い
- 企業が活用する際のメリットと注意すべき課題
炭素クレジットの基本的な仕組み

炭素クレジットとは、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を数値化し、取引可能な形にした証書のことです。「カーボンクレジット」とも呼ばれ、現在では政府機関や国際的にはこちらの表現が一般的になっています。
この仕組みの核心は、環境に良い活動を行った人や企業が、その成果を「クレジット」として他者に販売できるという点にあります。例えば、工場で省エネ設備を導入してCO2排出量を年間100トン削減できた場合、この100トン分がクレジットとして認証されます。一方、どうしても排出量を削減できない企業は、このクレジットを購入することで自社の排出量を相殺(オフセット)できるのです。
炭素クレジットが生まれる流れ
炭素クレジットが実際に発行されるまでには、厳格な手続きが必要です。まず、排出削減や吸収活動を行う事業者が、その計画を認証機関に申請します。この時点で「もしこの活動を行わなかった場合の排出量」(ベースライン排出量)を設定します。
次に、実際に活動を実施し、削減された排出量を測定・報告します。この測定結果は第三者機関による検証を受け、適正であると認められて初めてクレジットとして発行されます。例えば、ある企業が太陽光発電設備を導入し、従来の電力使用と比較して年間50トンのCO2削減を達成した場合、この50トン分がクレジットとして認証されるのです。
カーボンオフセットとの関係
炭素クレジットを理解する上で重要なのが「カーボンオフセット」という概念です。カーボンオフセットとは、どうしても避けられない温室効果ガスの排出について、同じ量の削減活動に投資することで排出を相殺する考え方です。
日常生活や事業活動では、完全にCO2排出をゼロにすることは困難です。航空業界や製造業などでは、現在の技術では大幅な削減が難しい分野もあります。そこで、まず可能な限りの削減努力を行い、それでも残る排出分については炭素クレジットを購入して相殺するのです。重要なのは、クレジット購入は「削減努力の代替」ではなく「最後の手段」として位置づけられていることです。
炭素クレジットの種類と認証制度

炭素クレジットには、国内制度と国際制度の大きく2つの枠組みがあります。それぞれ認証基準や取引方法が異なるため、利用する際には制度の特徴を理解することが重要です。
日本国内では環境省、経済産業省、農林水産省が共同で運営するJ-クレジット制度が中心となっています。一方、国際的にはVerra(VCS)やGold Standardなど、複数の認証機関が存在します。これらの制度は互いに補完関係にあり、企業は目的に応じて使い分けています。
J-クレジット制度(国内制度)
J-クレジット制度は、2013年に開始された日本独自の炭素クレジット認証制度です。省エネ・再生可能エネルギー設備の導入、森林管理などによる温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証しています。
この制度の特徴は、中小企業や自治体でも参加しやすい仕組みになっていることです。例えば、小規模な工場でのボイラー更新や、地域の森林整備活動なども対象となります。2024年時点で70を超える方法論が用意されており、様々な削減活動をクレジット化できます。認証されたクレジットは、企業の温室効果ガス削減目標達成や、カーボンニュートラル宣言などに活用されています。
J-クレジット制度のもう一つの重要な意義は、国内での資金循環を促進することです。削減活動を行う地方の企業や自治体がクレジットを販売し、都市部の大企業がそれを購入することで、環境対策と地域経済活性化の両立を図っています。
国際的なクレジット制度
国際的な炭素クレジット市場では、Verra(Verified Carbon Standard)やGold Standard、Climate Action Reserveなど複数の認証機関が運営しています。これらの制度は、途上国での森林保全プロジェクトや再生可能エネルギー事業など、大規模な削減活動を対象とすることが多いです。
国際制度の特徴は、プロジェクトの規模が大きく、1件あたり数万トンから数百万トンのクレジットが発行される点です。また、生物多様性保全や地域コミュニティの発展など、気候変動対策以外の効果(コベネフィット)も重視されています。例えば、ブラジルの森林保全プロジェクトでは、CO2吸収だけでなく、先住民の生活向上や野生動物の保護も同時に実現しています。
ただし、国際制度には品質のばらつきや透明性の課題も指摘されています。プロジェクトの実施状況を現地で確認することが困難なケースもあり、購入する企業は認証機関の信頼性や第三者による評価を慎重に検討する必要があります。
企業が炭素クレジットを活用するメリット

炭素クレジットは、企業にとって脱炭素化を進める重要な手段の一つです。特に、技術的な制約や経済的な理由で直接的な排出削減が困難な企業にとって、炭素クレジットの活用は現実的な選択肢となります。
近年、投資家や消費者の環境意識が高まる中で、企業の気候変動対策は競争力に直結する要素となっています。炭素クレジットを適切に活用することで、企業は環境責任を果たしながら事業を継続できるのです。ただし、重要なのは炭素クレジットを「最後の手段」として位置づけ、まず自社での削減努力を最大化することです。
脱炭素目標の達成支援
多くの企業が2030年や2050年に向けた温室効果ガス削減目標を設定していますが、事業の性質上、目標達成が困難な場合があります。例えば、航空会社は燃料効率の改善や持続可能な航空燃料の導入を進めていますが、現在の技術では完全な脱炭素化は不可能です。
こうした企業にとって、炭素クレジットは目標達成のための重要な補完手段となります。自社でできる最大限の削減を行った上で、残る排出分をクレジット購入で相殺することで、カーボンニュートラルを実現できるのです。実際に、大手航空会社の多くが森林保全プロジェクトや再生可能エネルギー事業のクレジットを購入し、フライトのカーボンオフセットサービスを提供しています。
また、製造業においても、工場の電化や省エネ設備の導入を進めつつ、どうしても残る排出分についてはクレジット購入で対応する企業が増えています。これにより、厳しい削減目標を達成しながら、生産活動を継続することが可能になります。
企業価値向上への効果
炭素クレジットの活用は、企業の環境への取り組み姿勢を対外的に示す効果もあります。投資家の間では、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が主流となり、企業の気候変動対策が投資判断の重要な要素となっています。
適切なクレジット購入により、企業は「カーボンニュートラル」や「ネットゼロ」を達成したとアピールできます。これにより、環境意識の高い投資家からの資金調達が有利になったり、サステナビリティを重視する顧客からの支持を得られたりします。特に、消費者向けの商品やサービスを展開する企業では、環境配慮が差別化要因となるケースが増えています。
さらに、炭素クレジットの購入を通じて途上国の環境プロジェクトを支援することで、企業の社会貢献活動としてもアピールできます。例えば、インドの風力発電プロジェクトや東南アジアの森林保全活動に資金提供することで、グローバル企業としての責任を果たしているとの評価を得られるのです。
炭素クレジットの課題と注意点
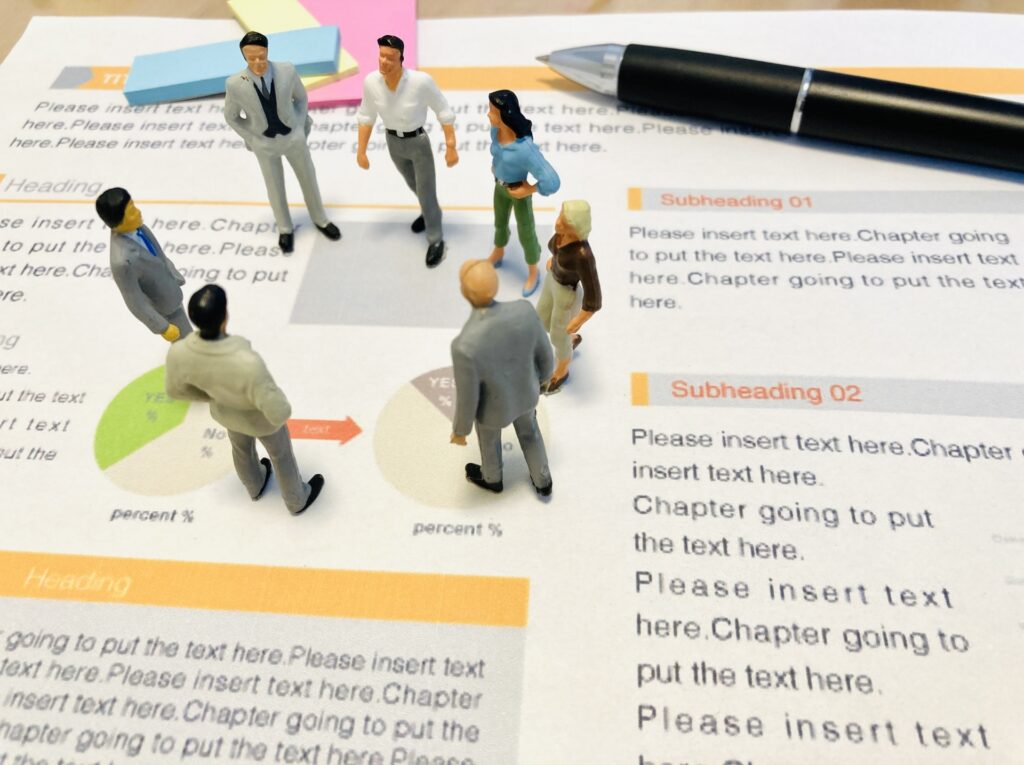
炭素クレジットには多くのメリットがある一方で、制度や市場の課題も指摘されています。企業が炭素クレジットを活用する際には、これらの課題を十分に理解し、適切な判断を行うことが重要です。
最も大きな課題は、クレジットの品質や実効性に関する疑問です。すべてのクレジットが同じ品質ではなく、中には期待された削減効果を実現していないプロジェクトも存在します。企業がクレジット購入を検討する際には、認証機関の信頼性やプロジェクトの透明性を慎重に評価する必要があります。
品質や透明性の問題
炭素クレジット市場では、プロジェクトによって品質に大きな差があることが課題となっています。特に森林保全プロジェクトでは、火災や病害虫により予期せぬ排出が発生するリスクがあります。また、プロジェクトの実施状況を継続的に監視することが困難な場合もあり、期待された削減効果が実現されないケースが報告されています。
さらに、一つのクレジットが複数回販売される「二重計上」の問題も存在します。統一された登録システムが整備されていないため、同じ削減活動に基づくクレジットが異なる市場で重複して取引される可能性があります。また、国が自国の気候目標にクレジットを算入し、同時に企業がそのクレジットを購入して自社の目標達成に使用するという問題も指摘されています。
これらの課題に対処するため、クレジットの品質を第三者が評価するサービスも登場しています。購入企業は、こうした評価サービスを活用したり、認証機関の基準を詳細に確認したりすることで、信頼性の高いクレジットを選択することが重要です。
実効性への疑問
炭素クレジットに対する根本的な批判として、「実際の削減努力を怠る言い訳になる」という指摘があります。企業がクレジット購入により簡単に目標達成できるため、コストがかかる自社での削減投資を先送りする可能性があるのです。
また、一部の森林保全プロジェクトでは、「そもそも伐採される予定がなかった森林」を保全対象としているケースもあり、実際の追加的な環境効果が疑問視されています。このような「追加性」の問題は、クレジットの根本的な価値に関わる重要な課題です。
さらに、クレジットによる削減効果が一時的なものである可能性も指摘されています。例えば、森林プロジェクトで吸収されたCO2が、将来的に森林伐採や自然災害により大気中に放出される「永続性」の問題があります。このため、購入企業は長期的な視点でクレジットの効果を評価し、可能な限り自社での削減を優先することが求められています。
炭素クレジット市場の現状と今後の展望

炭素クレジット市場は近年急速な拡大を見せており、今後さらなる成長が予想されています。気候変動対策への関心の高まりと、企業の脱炭素化目標の設定により、クレジットへの需要は世界的に増加しています。
市場の拡大とともに、制度の透明性や品質向上に向けた取り組みも進められています。各国政府や国際機関は、より信頼性の高いクレジット制度の構築を目指し、認証基準の厳格化やデジタル技術の活用による透明性向上に取り組んでいます。
市場規模の拡大
世界の炭素クレジット市場は急激な成長を続けています。2024年に114.8億米ドルで評価された市場は、2025年から2034年までに15.8%の年平均成長率で成長すると推定されています。別の調査では、市場規模は2024年の5,263億ドルから2025年には6,946億ドルに成長し、年平均成長率32.0%で拡大するとも予測されています。
この成長の背景には、世界各国の2050年カーボンニュートラル目標や、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大があります。特に大手企業では、投資家や消費者からの圧力により、積極的な気候変動対策が求められており、炭素クレジットの需要が急増しています。
航空業界では、国際民間航空機関(ICAO)が導入したCORSIA(国際民間航空のためのカーボンオフセット及び削減スキーム)により、2025年以降、これらの需要は急速に増大する見込みであり、2027年には1億トンを超えるクレジットが必要になる見込みです。このように、規制による義務的な需要も市場拡大の重要な要因となっています。
制度の改善に向けた取り組み
市場の急速な拡大に伴い、クレジットの品質向上と透明性確保が重要な課題となっています。2024年7月、Verraがより強力な透明性プロトコルへの移行をマークし、温室効果ガス除去に対する革新的な戦略を採用し、品質保証基準を改善することを目指したラベルを発足させるなど、認証機関による制度改善が進んでいます。
高品質なカーボンクレジットを保証する国際的な基準として世界的に認知されているものの一つがICVCMのコア・カーボン原則(CCP)であり、この基準への注目も高まっています。これらの基準は、追加性・永続性・測定可能性といった重要な要素を厳格に評価し、信頼性の高いクレジットの供給を目指しています。
また、ブロックチェーン技術の活用による取引の透明性向上や、衛星データを用いた森林保全プロジェクトの監視システムなど、デジタル技術による品質管理の向上も進んでいます。これらの技術革新により、二重計上や虚偽報告といった問題の解決が期待されています。
日本では、2024年9月には内閣官房に「GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ」が設立され、具体的な制度設計の検討が行われています。政府は「成長志向型カーボンプライシング」として、企業の排出量削減を促進する制度設計を進めており、これにより国内のクレジット需要も拡大すると予想されています。
まとめ|炭素クレジットの正しい理解と活用

炭素クレジットは、地球温暖化対策における重要な手段の一つですが、その活用には正しい理解と慎重な判断が必要です。単なる「排出権の購入」ではなく、実際の環境改善活動を支援し、全世界での温室効果ガス削減を促進する仕組みとして位置づけることが重要です。
企業がクレジットを活用する際は、まず自社での削減努力を最大化し、どうしても削減できない部分についてのみクレジット購入を検討するという「削減ヒエラルキー」の考え方が基本となります。また、購入するクレジットについては、認証機関の信頼性、プロジェクトの透明性、長期的な持続可能性を十分に検証することが必要です。
今後、炭素クレジット市場はさらなる成長が予想される一方で、品質向上と透明性確保に向けた取り組みも進んでいます。企業や個人がこの仕組みを正しく理解し、適切に活用することで、2050年カーボンニュートラル実現に向けた重要な一歩を踏み出すことができるでしょう。
参照元
・J-クレジット制度 https://japancredit.go.jp/
・環境省 J-クレジット制度及びカーボン・オフセットについて https://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
・GM Insights 炭素クレジット市場規模、成長予測 2025-2034 https://www.gminsights.com/ja/industry-analysis/carbon-credit-market
・Research and Markets 炭素クレジットの世界市場レポート 2025 https://www.gii.co.jp/report/tbrc1682020-carbon-credit-global-market-report.html
・アスエネメディア カーボンクレジットの価格予想は?今後の動向に注目! https://asuene.com/media/1608/
・Tolligence 【2025年のカーボンクレジット市場見通し】GXリーグやカーボンクレジット価格の動向を解説 https://tolligence.com/2025-outlook-for-vcm/





