地球温暖化が深刻化する中、世界各国が注目している対策の一つが「炭素隔離(カーボンシークエスト)」です。この技術は、大気中の二酸化炭素を減らし、気候変動の進行を抑える重要な手段として期待されています。自然の力を活用する方法から最新の技術まで、炭素隔離にはさまざまなアプローチがあります。
この記事で学べるポイント
- 炭素隔離の基本的な仕組みと種類
- 森林や海洋が果たす自然の炭素隔離機能
- 最新のCCS技術と地球温暖化対策への貢献
炭素隔離(カーボンシークエスト)とは何か

炭素隔離とは、大気中の二酸化炭素を捕捉し、長期間にわたって貯蔵するプロセスのことです。英語では「Carbon Sequestration」と呼ばれ、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを大気中から取り除く重要な手段として注目されています。
私たちが化石燃料を燃やしたり、工場で製品を作ったりするとき、必ず二酸化炭素が発生します。この二酸化炭素がそのまま大気中に放出されると、地球全体の気温上昇を引き起こしてしまいます。炭素隔離は、この二酸化炭素を「隔離」することで、温室効果を抑制する技術なのです。
炭素隔離の基本的な定義
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)では、炭素隔離を「二酸化炭素を炭素プールに蓄えるプロセス」と定義しています。炭素プールとは、地球システム内で炭素がさまざまな化学形態で一定期間存在する貯蔵庫のことを指します。
具体的には、森林の木々、土壌、海洋、そして地下の地層などが炭素プールとして機能します。これらの場所に二酸化炭素を長期間貯蔵することで、大気中の二酸化炭素濃度を下げることができるのです。
炭素隔離は大きく分けて2つの種類があります。一つは生物学的隔離と呼ばれる自然のプロセス、もう一つは地質学的隔離と呼ばれる人工的な技術です。どちらも同じ目標を持っていますが、アプローチの方法が異なります。
炭素貯蔵との違い
炭素隔離と似た言葉に「炭素貯蔵」がありますが、この2つには重要な違いがあります。炭素貯蔵は、特定の時点で炭素がどれだけ蓄えられているかを示す静的な状態です。一方、炭素隔離は二酸化炭素を積極的に捕捉し、貯蔵場所に移動させる動的なプロセスを指します。
例えば、森林に蓄えられている炭素の量を測定するのが炭素貯蔵の考え方です。これに対して、新たに植林を行って二酸化炭素を吸収させ、森林の炭素蓄積量を増やしていく活動が炭素隔離にあたります。
自然の炭素循環における位置づけ
炭素隔離は、地球上で自然に起こっている炭素循環の一部でもあります。炭素は生物圏、土壌圏、地圏、水圏、そして大気圏の間を常に移動しており、このサイクルの中で自然に隔離が行われています。
植物は光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し、炭素を体内に蓄積します。動物が死んで土に還ると、その炭素は土壌に蓄えられます。また、海洋では海水に溶け込んだ二酸化炭素が深海に運ばれ、長期間貯蔵されます。
人間が行う炭素隔離は、この自然のプロセスを強化したり、新たな技術を用いて効率化したりするものです。自然の力と人間の技術を組み合わせることで、より効果的な地球温暖化対策が可能になります。
生物学的炭素隔離の仕組みと事例

生物学的炭素隔離は、植物や微生物などの生物の力を活用して二酸化炭素を吸収・貯蔵する方法です。これは地球上で何億年も続いてきた自然のプロセスですが、人間の活動によってその機能を強化することができます。
最も身近な例が森林による炭素隔離です。木々は光合成を行う際に大気中の二酸化炭素を吸収し、炭素を幹や枝、葉に蓄えます。この炭素は木が生きている限り、そして木材として利用されている間も長期間貯蔵され続けます。
森林による二酸化炭素の吸収と貯蔵
森林は地球最大の炭素貯蔵庫の一つです。世界中の森林では、光合成によって年間約25億トンもの二酸化炭素が吸収されています。これは人間が排出する二酸化炭素の約4分の1に相当する膨大な量です。
森林による炭素隔離のメカニズムは比較的単純です。木々は根から吸収した水と、葉から取り込んだ二酸化炭素を使って光合成を行います。この過程で二酸化炭素中の炭素が糖分に変換され、最終的にセルロースやリグニンという形で木の組織に蓄積されます。
興味深いことに、森林は呼吸によって二酸化炭素を放出もしています。しかし、健全な森林では吸収量が放出量を大きく上回るため、全体として見ると二酸化炭素を減らす効果があります。特に成長期の若い森林では、この効果が顕著に現れます。
新規植林や再植林は、生物学的炭素隔離を人為的に強化する代表的な方法です。荒廃した土地に新たに森林を造成することで、大気中の二酸化炭素を長期間にわたって吸収し続けることができます。
土壌や海洋での炭素隔離
森林以外にも、土壌は重要な炭素貯蔵庫として機能しています。土壌中には大気中の約3倍もの炭素が蓄えられており、その量は森林の炭素蓄積量をも上回ります。
土壌での炭素隔離は、植物の根や落ち葉、動物の死骸などの有機物が分解される過程で起こります。これらの有機物中の炭素は、微生物の働きによって土壌中に安定した形で蓄積されます。適切な農業管理や草地管理を行うことで、土壌の炭素蓄積量を増やすことが可能です。
海洋もまた、巨大な炭素貯蔵庫です。海水は大気中の二酸化炭素を直接溶かし込むだけでなく、海中の植物プランクトンが光合成によって二酸化炭素を吸収します。これらの炭素は海流によって深海に運ばれ、数百年から数千年という長期間にわたって貯蔵されます。
グリーンカーボンとブルーカーボンの役割
炭素隔離の分野では、貯蔵場所によって「グリーンカーボン」と「ブルーカーボン」という概念が使われています。
グリーンカーボンは、陸上の植生や土壌に蓄えられる炭素を指します。森林、草原、農地などがその代表例です。これまでの炭素隔離対策では、主にこのグリーンカーボンに注目が集まってきました。
一方、ブルーカーボンは海洋や沿岸域の生態系に蓄えられる炭素のことです。海草藻場、塩性湿地、マングローブ林などがブルーカーボンの重要な貯蔵場所となっています。これらの生態系は面積あたりの炭素蓄積量が非常に高く、近年その重要性が再認識されています。
特にマングローブ林は、一般的な森林の3~4倍もの炭素を蓄積できることが知られています。しかし、世界各地でこれらの沿岸生態系が破壊されており、その保全と復元が急務となっています。
日本でも、沿岸域の藻場やマングローブ林の保全を通じたブルーカーボン対策が注目されています。これらの取り組みは、炭素隔離効果だけでなく、生物多様性の保全や漁業資源の維持にも貢献する一石二鳥の効果が期待されています。
地質学的炭素隔離(CCS)の技術と応用

地質学的炭素隔離は、人工的な技術を用いて二酸化炭素を地下深くに貯蔵する方法です。生物学的隔離とは異なり、工学的なアプローチによって大量の二酸化炭素を確実に処理できることが特徴です。この技術は「CCS(Carbon Capture and Storage:炭素回収・貯留)」と呼ばれ、世界各国で実用化が進められています。
地質学的炭素隔離が注目される理由は、その規模の大きさにあります。発電所や製鉄所などの大規模な排出源から直接二酸化炭素を回収できるため、短期間で大きな削減効果が期待できます。また、地下数百メートルから数キロメートルの深さに貯蔵するため、数千年という長期間にわたって安全に保管することが可能です。
炭素回収・貯留(CCS)の基本プロセス
CCSは「回収(Capture)」「輸送(Transport)」「貯留(Storage)」の3つのステップから構成されています。この一連のプロセスにより、工場や発電所で発生した二酸化炭素を大気に放出することなく、地下に安全に隔離します。
まず回収の段階では、燃焼前、燃焼後、酸素燃焼という3つの方法があります。燃焼前回収は、石炭や天然ガスから事前に炭素を分離する方法です。燃焼後回収は、燃焼で発生した排ガスから二酸化炭素だけを取り出す方法で、現在最も実用化が進んでいます。酸素燃焼は、純酸素中で燃焼させることで高純度の二酸化炭素を得る方法です。
回収された二酸化炭素は、高圧で圧縮してパイプラインやタンカーで貯留地点まで輸送されます。二酸化炭素は圧縮すると液体に近い状態になるため、効率的な輸送が可能になります。日本では、北海道の苫小牧で行われているCCS実証実験において、約60キロメートルのパイプラインが建設されています。
最終段階の貯留では、地下800メートル以深の適切な地層に二酸化炭素を圧入します。この深度では地圧が高いため、二酸化炭素は超臨界状態となり、液体と気体の中間的な性質を持ちます。この状態の二酸化炭素は密度が高く、効率的に大量を貯蔵できます。
地中への二酸化炭素貯蔵方法
地下への二酸化炭素貯蔵には、主に3つの方法があります。それぞれ異なる地層の特性を活用して、安全で長期的な貯蔵を実現しています。
最も一般的なのが深部塩水層への貯蔵です。塩水層とは、地下深くにある塩分を含んだ地下水の層のことです。この塩水は飲用には適さないため、二酸化炭素を注入しても水資源に影響を与えません。世界各地に広く分布しており、貯蔵容量も非常に大きいことが特徴です。
2つ目は、枯渇した石油・ガス田への貯蔵です。長年にわたって石油や天然ガスを蓄えていた地層は、気体を閉じ込める能力が実証済みです。また、既存の設備を活用できるため、コストを抑えながら実施できる利点があります。さらに、圧入した二酸化炭素が残存する石油の回収を促進する効果もあります。
3つ目は炭層への貯蔵です。石炭層は二酸化炭素を吸着する性質があり、同時にメタンガスを放出します。このメタンは天然ガスとして利用できるため、経済的なメリットも期待できます。
どの方法においても重要なのは、貯蔵した二酸化炭素が長期間にわたって地下に留まることです。そのため、上部に不透水性の岩石層(キャップロック)がある地層を選定し、継続的な監視システムを構築することが不可欠です。
直接空気回収(DAC)技術
近年注目されているのが、直接空気回収(DAC:Direct Air Capture)技術です。これは大気中から直接二酸化炭素を吸収する革新的な技術で、排出源に関係なく、どこでも炭素隔離を実行できます。
DACの仕組みは、大きく分けて2つの方式があります。固体吸収材を使用する方式では、アミン系の化学物質を固体に固定した吸収材を用います。この吸収材は室温で二酸化炭素を吸着し、加熱すると二酸化炭素を放出する性質があります。
液体吸収材を使用する方式では、水酸化ナトリウムなどのアルカリ性溶液で二酸化炭素を吸収します。回収された二酸化炭素は、電気分解などの工程を経て高純度の状態で取り出されます。
現在、アイスランドやアメリカなどで商用規模のDAC設備が稼働しています。アイスランドの「Orca」プラントでは、年間4,000トンの二酸化炭素を大気中から回収し、地下の玄武岩層に貯蔵しています。回収された二酸化炭素は玄武岩と反応して炭酸塩鉱物に変化し、永続的に固定化されます。
ただし、DACは現在のところコストが高く、実用化には技術革新が必要です。しかし、既に大気中に蓄積された二酸化炭素を除去できる唯一の技術として、将来的に重要な役割を果たすことが期待されています。
炭素隔離が地球温暖化対策に果たす役割
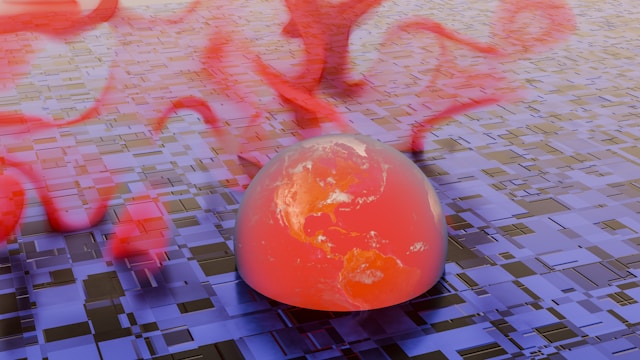
炭素隔離は、地球温暖化対策における重要な柱の一つとして位置づけられています。温室効果ガスの削減だけでは不十分とされる現在の状況において、既に大気中に蓄積された二酸化炭素を積極的に除去する「ネガティブエミッション」技術として注目されています。
国際的な気候変動対策の目標である「カーボンニュートラル」の実現には、炭素隔離が不可欠です。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を均衡させ、実質的な排出量をゼロにすることを指します。この目標達成のためには、排出削減努力と並行して炭素隔離を大幅に拡大する必要があります。
カーボンニュートラル実現への貢献
カーボンニュートラルの実現において、炭素隔離は2つの重要な機能を果たします。一つは、削減が困難な分野からの排出を相殺することです。航空業界や重工業など、技術的に完全な排出ゼロが困難な分野では、炭素隔離によってその排出分を打ち消すことが必要になります。
もう一つは、過去の累積排出を除去することです。産業革命以降、人類は大量の二酸化炭素を大気中に放出してきました。この累積された二酸化炭素を除去するには、大規模な炭素隔離プロジェクトが不可欠です。
具体的な数値目標として、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書では、地球温暖化を1.5℃に抑制するために、2030年までに世界全体で年間100億~200億トンの二酸化炭素を除去する必要があるとされています。これは現在の世界の年間排出量の約3分の1から2分の1に相当する膨大な量です。
日本政府も2050年カーボンニュートラル宣言において、森林などの自然吸収源に加えて、CCSやDACなどの技術的な炭素隔離を重要な要素として位置づけています。特に、産業界からの排出が多い日本では、技術的な炭素隔離の役割が重要になります。
IPCC報告書が示す重要性
IPCC第6次評価報告書では、炭素隔離の重要性が明確に示されています。報告書によると、1.5℃目標を達成するためのほとんどのシナリオにおいて、大規模な炭素除去(CDR:Carbon Dioxide Removal)が必要不可欠とされています。
特に注目すべきは、従来の排出削減だけでは目標達成が困難であるという指摘です。エネルギー効率化や再生可能エネルギーの導入を最大限進めても、残存する排出を相殺するためには年間数十億トン規模の炭素除去が必要になります。
報告書では、森林などの自然ベースの解決策(NbS:Nature-based Solutions)と、BECCSやDACCsなどの技術的解決策の両方が重要であることが強調されています。BECCSとは、バイオエネルギーと炭素回収・貯留を組み合わせた技術で、植物が成長過程で吸収した二酸化炭素をエネルギー利用後に地下に貯留する方法です。
ただし、IPCCは炭素隔離技術の大規模展開には慎重な検討が必要であることも指摘しています。生態系への影響、水資源の利用、食料生産との競合など、様々な副次的影響を考慮した持続可能な実施が求められています。
各国政府と企業の取り組み事例
世界各国で炭素隔離に向けた政策支援と実証プロジェクトが加速しています。アメリカでは、バイデン政権がDAC技術の開発に35億ドルの予算を確保し、商用規模での実用化を目指しています。また、炭素隔離1トンあたり最大50ドルの税額控除制度を設けて、民間企業の投資を促進しています。
欧州連合(EU)では、2030年までに年間2.8億トンの炭素除去を目標とする法案が検討されています。また、炭素除去に対する認証制度の構築も進められており、市場メカニズムを活用した炭素隔離の拡大が期待されています。
企業レベルでも積極的な取り組みが見られます。マイクロソフトは2030年までにカーボンネガティブ(排出量よりも除去量が多い状態)を達成すると宣言し、世界各地のDAC技術やBECCS、森林保護プロジェクトに投資しています。
日本企業では、三菱重工業がマレーシアで大規模なCCSプロジェクトを進めているほか、トヨタ自動車が「トヨタ環境チャレンジ2050」において、工場での二酸化炭素排出ゼロに加えて、森林保護による炭素隔離にも取り組んでいます。
石油会社も炭素隔離事業に注力しています。エクソンモービルは2027年までに年間100万トンの炭素回収能力を持つCCS設備の建設を計画しており、シェルも世界各地でCCSプロジェクトを展開しています。これらの企業は、従来のエネルギー事業から低炭素ビジネスへの転換を図っています。
炭素隔離の課題と今後の展望

炭素隔離は地球温暖化対策の重要な手段として期待されていますが、実用化と大規模展開に向けては多くの課題が残されています。技術的な課題から経済的な問題、さらには環境への影響まで、解決すべき問題は多岐にわたります。
しかし、世界各国の政策支援と技術革新により、これらの課題は徐々に克服されつつあります。特に近年は、民間企業の積極的な参入と国際協力の拡大により、炭素隔離技術の発展が加速しています。
技術的・経済的な課題
炭素隔離技術の最大の課題はコストの高さです。特にCCSにおける二酸化炭素の分離・回収工程では、現在でもコスト全体の約60~70%を占めています。化学吸収法による分離では、1トンのCO2を処理するために50~100ドルのコストがかかり、これは他の温室効果ガス削減手段と比べて高い水準です。
DAC技術はさらに高コストで、現在のところ1トンあたり600~1,000ドル程度が必要です。これは、大気中の二酸化炭素濃度が約400ppmと低いため、大量の空気を処理する必要があるからです。コスト削減のためには、より効率的な吸収材の開発や、プロセス全体の最適化が急務となっています。
貯留地点の確保も重要な課題です。CCSでは、二酸化炭素を安全に長期間貯蔵できる地層を見つける必要がありますが、適切な地質条件を満たす場所は限られています。また、貯留地点と排出源との距離が遠い場合、輸送コストが大幅に増加してしまいます。
技術的な信頼性の向上も求められています。二酸化炭素の分離・回収プロセスを稼働させるために必要なエネルギーが大きく、場合によっては追加的なCO2排出を引き起こす可能性があります。このため、全体のライフサイクルで確実にCO2削減効果を実現する技術の確立が重要です。
政策支援と国際協力の必要性
炭素隔離の普及には、政府による強力な政策支援が欠かせません。多くの国で炭素税や排出権取引制度が導入されており、これらの制度により炭素隔離の経済的な価値が高まっています。
アメリカでは、45Q税額控除制度により、CCSプロジェクトに1トンあたり最大85ドルの税額控除が提供されています。また、インフレ抑制法により、DAC技術に対して1トンあたり180ドルという大規模な税額控除が新設されました。これらの政策により、民間企業の投資意欲が大幅に向上しています。
日本政府も2025年にGX2040ビジョンを策定し、炭素隔離技術への支援を強化しています。経済産業省では、グリーンイノベーション基金から2兆円規模の支援を行い、企業の技術開発と実証実験を10年間継続的に支援する計画です。また、CCS事業に対する長期金融支援制度も創設され、民間投資の呼び水となることが期待されています。
国際協力の面では、技術開発や標準化に向けた多国間協力が進展しています。国際エネルギー機関(IEA)は、世界全体でCCS技術の標準化と技術移転を促進するプラットフォームを提供しています。また、二国間協力も活発化しており、日本はオーストラリアやアメリカとCCS技術の共同開発を進めています。
持続可能な炭素隔離の実現に向けて
将来的に持続可能な炭素隔離を実現するためには、技術革新と社会システムの両面からのアプローチが必要です。技術面では、より効率的で低コストな炭素隔離技術の開発が続けられています。
特に注目されているのが、人工光合成技術です。この技術は、太陽光エネルギーを使って水とCO2から有用な化学品を直接製造するもので、炭素隔離と資源生産を同時に実現できます。現在は研究段階ですが、将来的には画期的な解決策となる可能性があります。
社会システムの面では、炭素隔離によるCO2削減量を適切に評価・認証する仕組みの構築が重要です。国際的な炭素クレジット市場において、炭素隔離プロジェクトが正当に評価され、経済的インセンティブが働く制度設計が求められています。
また、炭素隔離は他の気候変動対策と組み合わせて実施することで、より大きな効果を発揮します。再生可能エネルギーとの連携により、炭素隔離プロセスで使用するエネルギーをクリーン化することで、全体のCO2削減効果を最大化できます。
地域コミュニティとの連携も重要な要素です。特に森林保護や植林による生物学的炭素隔離では、地域住民の理解と協力が成功の鍵となります。環境保全と地域経済の発展を両立させる仕組みづくりが求められています。
最終的に、炭素隔離は地球温暖化対策の「銀の弾丸」ではありませんが、排出削減と組み合わせることで、カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な手段となります。技術革新、政策支援、国際協力、そして社会全体の取り組みが一体となって進展することで、持続可能な未来の実現が可能になるでしょう。
参照元
・環境省 脱炭素ポータル https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/
・環境省 国の取組 – 脱炭素ポータル https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/road-to-carbon-neutral/
・経済産業省 エネルギーの基礎用語~CO2を集めて埋めて役立てる「CCUS」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ccus.html
・経済産業省 CO2削減の夢の技術!進む「カーボンリサイクル」の開発・実装 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_recycling2021.html
・気象庁 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)について https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/index.html
・IBM 炭素隔離とは https://www.ibm.com/jp-ja/think/topics/carbon-sequestration




