地球温暖化対策が急務となる中、企業の温室効果ガス削減を促進する新たな仕組みとして「排出量取引制度」が注目を集めています。この制度は、温室効果ガスの排出に経済的なコストを設けることで、企業が自主的に脱炭素化に取り組むインセンティブを生み出します。日本でも2026年度から本格導入が予定されており、多くの企業にとって重要な制度となります。排出量取引制度がどのような仕組みで、私たちの社会にどのような影響をもたらすのかを詳しく解説します。
排出量取引制度とは何か
 排出量取引制度とは、温室効果ガスの排出量削減を目的とした経済的手法です。国や地域が全体の温室効果ガス削減目標を設定し、その目標に基づいて企業ごとに「排出枠」と呼ばれる排出できる温室効果ガスの上限量を割り当てます。企業は自社の実際の排出量と割り当てられた排出枠を比較し、排出枠を超過した場合は他の企業から余剰分を購入し、逆に排出枠に余裕がある場合は他社に売却することができる制度です。
排出量取引制度とは、温室効果ガスの排出量削減を目的とした経済的手法です。国や地域が全体の温室効果ガス削減目標を設定し、その目標に基づいて企業ごとに「排出枠」と呼ばれる排出できる温室効果ガスの上限量を割り当てます。企業は自社の実際の排出量と割り当てられた排出枠を比較し、排出枠を超過した場合は他の企業から余剰分を購入し、逆に排出枠に余裕がある場合は他社に売却することができる制度です。
基本的な定義と仕組み
排出量取引制度は「カーボンプライシング」と呼ばれる政策手法の一種です。カーボンプライシングとは、温室効果ガスの排出に価格をつけることで、排出者の行動変容を促す仕組みのことです。これまで企業が温室効果ガスを排出しても直接的な経済的負担は発生しませんでしたが、この制度により排出には一定のコストが伴うようになります。
制度の対象となる企業は、政府から無償で排出枠を割り当てられます。例えば、A社が年間10万トンのCO2排出枠を割り当てられたとします。実際の排出量が8万トンだった場合、A社は2万トン分の排出枠が余ることになります。一方、B社が12万トンの排出枠を割り当てられたにも関わらず、実際の排出量が14万トンだった場合、2万トン分の排出枠が不足します。この場合、B社はA社から2万トン分の排出枠を購入することで、制度上の義務を履行できます。
キャップ・アンド・トレードの原理
排出量取引制度は「キャップ・アンド・トレード」とも呼ばれます。キャップ(Cap)は排出量の上限設定を、トレード(Trade)は排出枠の取引を意味します。この仕組みの最大の特徴は、全体の排出量に明確な上限を設けることで、確実な削減効果を実現できることです。
制度全体の排出枠の総量は、国や地域の削減目標に基づいて決定されます。例えば「2030年までに2013年比で46%削減」という目標がある場合、その目標達成に必要な排出枠の総量だけが市場に供給されます。企業間で排出枠の売買が行われても、全体の排出量がこの上限を超えることはありません。
市場メカニズムを活用することで、排出削減コストが最も安い企業から優先的に削減が進むため、社会全体として効率的な削減が実現されます。削減コストが高い企業は排出枠を購入し、削減コストが安い企業は積極的に削減して余剰分を販売するという自然な流れが生まれます。
排出量取引制度の具体的な流れ
 排出量取引制度は段階的なプロセスを経て実施されます。まず政府が全体の削減目標を設定し、その目標に基づいて市場に供給する排出枠の総量を決定します。次に、対象企業への排出枠の分配方法を決め、実際に各企業に排出枠を割り当てます。企業は事業活動を行いながら自社の排出量を監視し、年度末に実際の排出量と保有する排出枠の収支を合わせる必要があります。
排出量取引制度は段階的なプロセスを経て実施されます。まず政府が全体の削減目標を設定し、その目標に基づいて市場に供給する排出枠の総量を決定します。次に、対象企業への排出枠の分配方法を決め、実際に各企業に排出枠を割り当てます。企業は事業活動を行いながら自社の排出量を監視し、年度末に実際の排出量と保有する排出枠の収支を合わせる必要があります。
排出枠の設定から分配まで
排出枠の分配方法には主に3つの方式があります。第一に「グランドファザリング方式」は、企業の過去の排出実績に基づいて排出枠を配分する方法です。過去3年間の平均排出量に一定の削減率を適用して排出枠を決定するため、実績データが入手しやすく導入が比較的容易です。
第二に「ベンチマーク方式」は、業界の優良企業の排出効率を基準として排出枠を設定する方法です。例えば鉄鋼業界であれば、効率的な企業の「鉄1トン当たりのCO2排出量」を基準値とし、各企業の生産量に基準値を掛けて排出枠を算出します。この方式は過去の削減努力が適切に評価されるため公平性が高いとされています。
第三に「オークション方式」は、排出枠を競売によって有償で配分する方法です。企業は必要な排出枠を入札によって購入します。この方式では排出枠の経済的価値が明確になり、削減インセンティブが最も強く働きます。ただし、企業の負担が大きくなるため、制度導入初期は無償配分が中心となることが多いです。
企業間の取引と価格決定
排出枠の価格は市場での需給バランスによって決まります。多くの企業が排出枠を必要とする状況では価格が上昇し、逆に排出枠に余裕のある企業が多い場合は価格が下落します。価格変動が激しすぎると企業の投資計画に悪影響を与えるため、多くの制度では価格安定化措置が設けられています。
日本の制度案では、排出枝の上限価格と下限価格を設定する予定です。市場価格が上限を超えた場合、企業は上限価格で政府から排出枠を購入できます。逆に市場価格が下限を下回った場合、政府が市場から排出枠を買い取ることで価格の安定化を図ります。
企業は排出枠の過不足に応じて、自社での削減努力と排出枠購入のどちらが経済的に有利かを判断します。例えば、排出枠の市場価格が1トン当たり5000円で、自社での削減コストが1トン当たり3000円であれば、削減努力を行って余剰分を販売した方が利益になります。このように経済合理性に基づいた判断により、社会全体で最も効率的な削減が進むことが期待されています。
排出量取引制度のメリットとデメリット
 排出量取引制度は温室効果ガス削減に向けた有効な政策手法として世界的に注目されていますが、同時にいくつかの課題も指摘されています。制度のメリットとデメリットを正しく理解することで、企業や社会全体への影響をより適切に評価できます。
排出量取引制度は温室効果ガス削減に向けた有効な政策手法として世界的に注目されていますが、同時にいくつかの課題も指摘されています。制度のメリットとデメリットを正しく理解することで、企業や社会全体への影響をより適切に評価できます。
企業にとってのメリット
排出量取引制度の最大のメリットは、企業に削減手段の選択肢を提供することです。従来の規制では「必ず自社で削減しなければならない」という制約がありましたが、この制度では「自社での削減」か「排出枠の購入」かを企業が自由に選択できます。業種や事業形態によって削減コストは大きく異なるため、この柔軟性により企業負担の軽減が期待できます。
制度により削減目標が明確化されることも重要なメリットです。企業は割り当てられた排出枠という具体的な数値目標を持つため、削減計画を立てやすくなります。また、排出枠の市場価格により「CO2削減の経済的価値」が可視化されるため、省エネ投資や再生可能エネルギー導入の経済効果を定量的に評価できるようになります。
さらに、早期に削減に取り組んだ企業は余剰排出枠を販売することで収益を得られます。これにより、環境への取り組みが直接的な経済メリットにつながり、企業の脱炭素化へのインセンティブが強化されます。技術革新により大幅な削減を実現した企業ほど大きな利益を得られるため、イノベーションの促進効果も期待されています。
制度の課題と懸念点
一方で、排出量取引制度にはいくつかの課題があります。最も深刻な問題とされているのが「カーボンリーケージ」です。これは、排出規制が厳しい国の企業が、規制の緩い国に生産拠点を移転してしまう現象を指します。この結果、地球全体で見ると温室効果ガスの削減効果が相殺される可能性があります。
排出枠の適切な設定も大きな課題です。排出枠を厳しく設定しすぎると企業の負担が過大になり、経済活動に悪影響を与える恐れがあります。逆に緩く設定すると削減効果が期待できず、制度の意義が失われてしまいます。特に業種間の公平性を保ちながら適切な排出枠を設定することは非常に複雑な作業となります。
市場価格の変動リスクも企業にとって大きな懸念材料です。排出枠の価格が予想以上に上昇した場合、企業の収益に深刻な影響を与える可能性があります。また、制度の運用には高度な監視・測定体制が必要であり、企業にとって新たな事務負担が発生することも課題として挙げられています。
世界と日本の排出量取引制度の現状
 排出量取引制度は世界各地で導入が進んでおり、それぞれの地域の特性に応じた制度設計が行われています。先進事例から学ぶことで、日本の制度設計にも貴重な知見が活かされています。
排出量取引制度は世界各地で導入が進んでおり、それぞれの地域の特性に応じた制度設計が行われています。先進事例から学ぶことで、日本の制度設計にも貴重な知見が活かされています。
EUなど海外の取り組み事例
世界最大規模の排出量取引制度として、EU域内で運用されている「EU-ETS」があります。2005年に開始されたこの制度は、EU27カ国とアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの計30カ国が参加する国際的な制度です。対象となるのは発電所や製造業など大規模な排出源で、EU全体の温室効果ガス排出量の約40%をカバーしています。
EU-ETSでは段階的に制度を拡充しており、2023年からは海運セクターも対象に加わりました。また、2026年からは無償配分を段階的に廃止し、オークション方式への移行を進める予定です。排出枠の価格は2023年12月時点で1トン当たり約66ユーロ(約1万円)と高水準で推移しており、企業の削減インセンティブとして機能していることがうかがえます。
アメリカでは連邦レベルでの制度はありませんが、カリフォルニア州やニューヨーク州など複数の州が地域的な排出量取引制度を運用しています。中国も2021年から全国規模の制度を開始し、対象企業数では世界最大の制度となっています。韓国、カナダなども独自の制度を展開しており、排出量取引制度は世界的な潮流となっています。
日本の導入計画と東京都・埼玉県の先行事例
日本では国レベルでの排出量取引制度はまだ導入されていませんが、東京都と埼玉県が先行して地域レベルでの制度を運用しています。東京都の制度は2010年から開始され、大規模事業所を対象とした総量削減義務と排出量取引を組み合わせた仕組みです。年間エネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上の事業所が対象となり、約1300の事業所が参加しています。
埼玉県も2011年から同様の制度を導入しており、両制度間での排出枠の相互利用も可能となっています。これらの先行事例では、制度導入により確実な削減効果が確認されており、参加企業からも一定の評価を得ています。東京都の制度では、制度開始から約10年間で対象事業所の排出量が約30%削減されるなど、具体的な成果が示されています。
国レベルでは、2023年に成立したGX推進法に基づき、2026年度から本格的な排出量取引制度が開始される予定です。年間CO2直接排出量が10万トン以上の事業者約300〜400社が対象となり、日本全体の温室効果ガス排出量の約60%をカバーする大規模な制度となります。制度設計においては、東京都・埼玉県の経験やEU-ETSなど海外事例の知見が活用されており、日本の産業構造に適した仕組みの構築が進められています。
日本の排出量取引制度の今後の展開
 日本の排出量取引制度は2026年度の本格導入に向けて、現在詳細な制度設計が進められています。この制度は「成長志向型カーボンプライシング」の柱として位置づけられ、企業の脱炭素化と経済成長の両立を目指した仕組みとなります。
日本の排出量取引制度は2026年度の本格導入に向けて、現在詳細な制度設計が進められています。この制度は「成長志向型カーボンプライシング」の柱として位置づけられ、企業の脱炭素化と経済成長の両立を目指した仕組みとなります。
2026年度からの本格導入
2025年の通常国会でGX推進法の改正案が提出される予定で、これにより排出量取引制度の法的基盤が整備されます。制度の対象となるのは、年間CO2直接排出量が10万トン以上の事業者で、業種を問わず一律に参加が義務付けられます。この基準により、電力会社、鉄鋼メーカー、化学メーカー、セメント会社など、日本の主要な大規模排出事業者が制度の対象となります。
排出枠の配分は当初無償で行われ、業種ごとの特性を考慮した政府指針に基づいて実施されます。企業は翌年度に実際の排出量を報告し、排出量と同量の排出枠を保有する義務を負います。排出枠が不足した企業は、他の企業から購入するか、上限価格での政府購入により義務を履行できます。
価格安定化措置として上下限価格が設定され、企業の予見可能性を確保します。また、2033年度からは排出枠の一部を有償オークションで配分する予定で、段階的に制度の厳格化が図られます。このように長期的な制度設計を明確にすることで、企業が計画的に脱炭素投資を進められる環境が整備されます。
対象企業と影響範囲
制度の対象となる約300〜400社は、日本の温室効果ガス排出量の約60%を占める規模です。これらの企業には、従来の自主的な削減努力に加えて、法的義務としての排出量管理が求められるようになります。対象企業は排出量の正確な測定・報告体制を整備し、排出枠の管理や取引に関する新たな業務への対応が必要となります。
制度の影響は対象企業だけにとどまりません。大企業のサプライチェーン全体で脱炭素化の要請が強まり、中小企業においても省エネや再エネ導入の必要性が高まることが予想されます。また、排出枠の取引市場の整備により、金融機関や商社などが新たなビジネス機会を見出すことも期待されています。
消費者への影響としては、排出量取引制度により企業のコストが増加した場合、一部が製品価格に転嫁される可能性があります。しかし、同時に技術革新やスケールメリットにより、省エネ製品や再エネ由来の製品の価格競争力が向上することも見込まれます。長期的には、環境配慮型の製品・サービスが市場で優位に立つ構造変化が進むと考えられています。
まとめ|排出量取引制度が目指す脱炭素社会
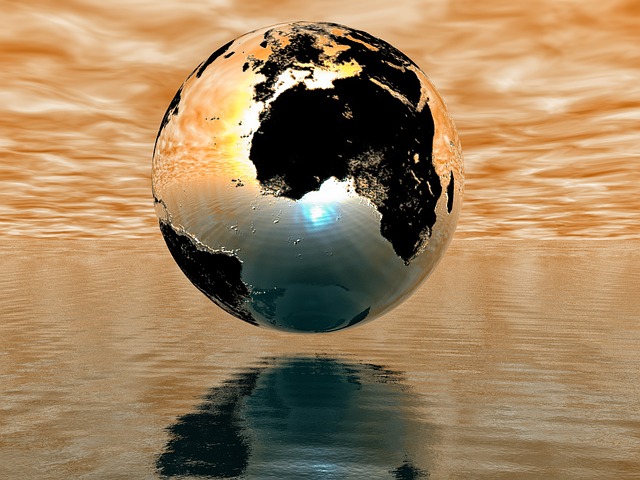 排出量取引制度は、市場メカニズムを活用して効率的な温室効果ガス削減を実現する画期的な仕組みです。企業に削減手段の選択肢を提供し、早期の取り組みに経済的インセンティブを与えることで、社会全体の脱炭素化を加速させる効果が期待されています。
排出量取引制度は、市場メカニズムを活用して効率的な温室効果ガス削減を実現する画期的な仕組みです。企業に削減手段の選択肢を提供し、早期の取り組みに経済的インセンティブを与えることで、社会全体の脱炭素化を加速させる効果が期待されています。
日本でも2026年度からの本格導入により、大規模排出事業者を中心とした削減努力が本格化します。制度の成功には、適切な排出枠の設定、公平な配分方法、効果的な価格安定化措置など、きめ細かな制度設計が不可欠です。また、対象企業だけでなく、サプライチェーン全体や社会全体への波及効果も考慮した総合的なアプローチが重要となります。
世界各国で導入が進む排出量取引制度は、地球温暖化対策の重要な政策手法として定着しつつあります。日本の制度が国際的な基準と整合性を保ちながら、日本の産業構造に適した形で運用されることで、国際競争力を維持しつつ脱炭素社会の実現に貢献することが期待されています。企業、政府、市民が協力して制度を支えることで、持続可能な社会の構築に向けた大きな一歩となるでしょう。
参照元
・経済産業省 METI Journal「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ https://journal.meti.go.jp/p/36485/
・環境省 国内排出量取引制度
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/index.html
・東京都環境局 排出量取引
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/trade/
・WWF 温室効果ガス排出量取引/入門編
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/1138.html
・経済産業省 排出量取引制度小委員会 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/index.html





