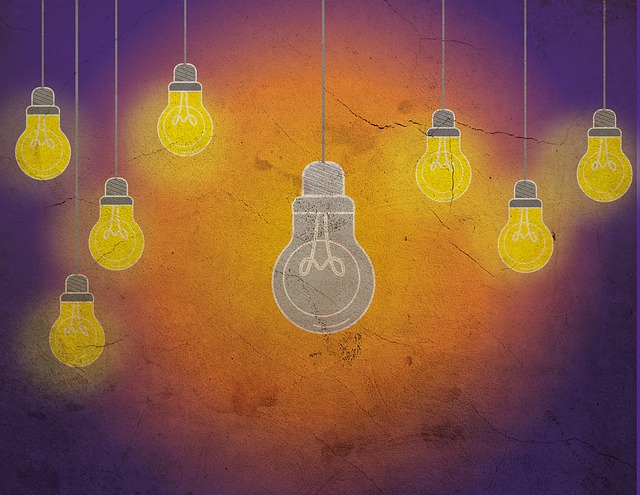分散型電源は、私たちの身近な場所で電気を作り出す新しい発電システムです。従来の大型発電所とは異なり、小規模な発電設備を各地域に分散して配置することで、より効率的で安定した電力供給を実現します。東日本大震災をきっかけに注目が高まり、現在では日本のエネルギー政策の重要な柱として位置づけられています。
分散型電源とは何か?基本的な定義と特徴

分散型電源とは、需要家エリアに隣接して分散配置される小規模な発電設備全般の総称です。電力を使う場所の近くに小さな発電設備を設置し、その地域で必要な電力を供給する仕組みを指します。
たとえば、住宅の屋根に設置する太陽光パネル、企業の敷地内に建設する小型風力発電機、病院やホテルが導入する燃料電池システムなどが代表例です。これらはすべて、電力会社の大型発電所と比べて小規模で、電力を使う場所のすぐ近くに設置されています。
分散型電源の最大の特徴は、発電設備の所有者もしくは設置場所周辺の地域で消費されている点です。遠く離れた発電所から長い送電線を通じて電気を運ぶのではなく、その場で作った電気をその場で使うという「地産地消」の考え方が基本となっています。
従来の集中型電源との違い
これまでの日本の電力供給は、電力会社が運営する大規模な火力発電所や原子力発電所が中心でした。これらの発電所は一箇所に大きな発電能力を集中させ、全国に張り巡らされた送電網を通じて各家庭や企業に電力を届けるシステムです。
一方、分散型電源は発電設備を各地域に分散配置します。コンビニエンスストアに例えると、集中型電源は大型ショッピングモール1つで広域をカバーする方式、分散型電源は各住宅地に小さな店舗を点在させる方式と言えるでしょう。
この違いにより、集中型電源では発電所から消費地までの距離が長く、送電時に電力ロスが発生します。また、一つの発電所にトラブルが起きると広範囲に影響が及ぶリスクもあります。分散型電源では、これらの課題を解決できる可能性があります。
分散型電源が注目される背景
分散型電源が求められるようになった主な理由は、災害対策と脱炭素化という2つの大きな変化にあります。
2011年の東日本大震災では、福島第一原子力発電所の事故により、従来の一極集中型による発電および送配電システムの限界が明らかになりました。大規模停電が発生し、電力供給の安定性に対する懸念が高まったのです。
また、地球温暖化対策として、国はカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を実質ゼロにする取り組み)を推進しています。これには、大規模な火力発電所からの脱却と、再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠です。
さらに、エネルギー自給率の向上も重要な課題です。日本のエネルギー自給率は約12%と先進国の中でも低い水準にあり、エネルギー安全保障の観点からも分散型電源への期待が高まっています。
分散型電源の種類と仕組み
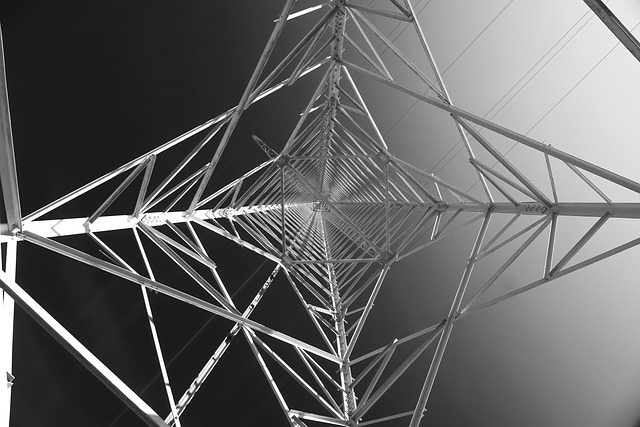
分散型電源は、使用するエネルギー源によっていくつかの種類に分類されます。それぞれ異なる特徴と仕組みを持っており、用途や設置場所に応じて選択されています。
再生可能エネルギー系統
再生可能エネルギーを活用した分散型電源は、環境負荷が少なく、資源の枯渇の心配がないという特徴があります。
太陽光発電は最も身近な分散型電源の一つです。住宅の屋根や企業の建物に設置されたソーラーパネルが太陽の光を直接電気に変換します。設置が比較的容易で、日中の電力需要ピーク時間帯に発電するため、電力系統への貢献度が高いのが特徴です。
風力発電は、風の力でタービンを回転させて発電します。大型の風力発電所だけでなく、小型の風力発電機を住宅や事業所に設置するケースも増えています。
小水力発電は、ダムを使わずに河川や農業用水路の流れを利用して発電する方式です。一般的な水力発電と異なり、自然環境への影響が小さく、地域密着型の電源として注目されています。
化石燃料系統
化石燃料を活用した小規模な発電システムも分散型電源に含まれます。大規模な火力発電所とは異なり、地域のニーズに合わせて柔軟に運用できるのが特徴です。
ガスタービン発電は、天然ガスを燃焼させてタービンを回す発電方式です。起動時間が短く、電力需要の変動に素早く対応できるため、電力系統の安定化に重要な役割を果たします。病院や工場などで非常用電源としても活用されています。
ディーゼルエンジン発電は、軽油を燃料とする発電システムです。設置コストが比較的安く、メンテナンスが容易なため、離島や山間部での電力供給に適しています。
コージェネレーションシステム(熱電併給システム)は、発電と同時に発生する排熱を冷暖房や給湯に活用する効率的なシステムです。総合エネルギー効率が80%以上に達することもあり、省エネルギー効果が高く評価されています。
燃料電池・蓄電システム
燃料電池は、水素と酸素の化学反応によって直接電気を生み出す発電システムです。発電効率が高く、副産物は水だけというクリーンな特徴を持っています。
家庭用燃料電池(エネファーム)は、都市ガスから水素を取り出して発電し、同時に発生する熱で給湯を行います。一般家庭での導入が進んでおり、光熱費の削減と環境負荷の軽減を同時に実現できます。
業務用・産業用燃料電池は、より大きな規模で電力と熱を供給します。ホテルや病院、工場などで導入が進んでおり、エネルギーコストの削減と事業継続性の向上に貢献しています。
蓄電システムは、電気エネルギーを貯蔵し、必要な時に供給する設備です。太陽光発電や風力発電などの出力が不安定な電源と組み合わせることで、安定した電力供給を実現できます。家庭用から産業用まで様々な規模のシステムがあり、災害時の非常用電源としても重要な役割を果たします。
分散型電源のメリット
分散型電源の導入には、従来の集中型電源では得られない多くの利点があります。これらのメリットが、世界各国で分散型電源の普及が進む理由となっています。
送電ロスの削減と効率向上
分散型電源の最も重要なメリットの一つが、送電ロスの大幅な削減です。従来の集中型電源では、発電所から消費地まで数百キロメートルの送電が必要な場合があり、その過程で電力の約5~10%が失われていました。
分散型電源では、電力を使用する場所の近くで発電するため、送電距離を大幅に短縮できます。これにより、送電ロスを1%以下に抑えることが可能になり、エネルギー効率が大幅に向上します。
さらに、コージェネレーションシステムのように発電時の排熱も有効活用できる場合、総合エネルギー効率は80%を超えることもあります。これは従来の火力発電所の効率(約40%)と比べて2倍以上の効率を実現していることになります。
災害時の安定供給
分散型電源は災害に対する強靭性(レジリエンス)の向上に大きく貢献します。2018年の北海道胆振東部地震では、道内全域が停電する「ブラックアウト」が発生しましたが、この際に分散型電源を導入していた施設では、自立的に電力を確保できました。
台風や地震によって送電線が損傷した場合でも、分散型電源があればその地域だけは電力供給を継続できます。病院や避難所、重要なインフラ施設にとって、この自立性は極めて重要な価値を持ちます。
また、複数の小規模電源が分散配置されているため、一つの設備にトラブルが発生しても、他の設備でカバーできるリスク分散効果もあります。これは「卵を一つのかごに盛らない」という投資の基本原則と同じ考え方です。
地産地消によるエネルギー自給
分散型電源は地域のエネルギー自給率向上に直結します。太陽光や風力、小水力、バイオマスなど、その地域に存在する自然エネルギーを活用することで、外部からのエネルギー購入を減らすことができます。
経済面では、エネルギー代金が地域外に流出することを防ぎ、地域内での経済循環を促進します。農村部では、使われなくなった農地に太陽光発電を設置し、新たな収入源とするケースも増えています。
環境面では、輸送に伴うエネルギー消費や環境負荷を削減できます。また、地域住民がエネルギー問題を身近に感じることで、省エネルギーへの意識向上にもつながります。
分散型電源のデメリットと課題
一方で、分散型電源には解決すべき課題も存在します。これらの課題を理解し、適切な対策を講じることが普及拡大のカギとなります。
発電量の不安定性
太陽光発電や風力発電は天候に左右されるため、発電量が不安定になる特徴があります。曇りや雨の日には太陽光発電の出力が大幅に低下し、風が弱い日には風力発電がほとんど機能しません。
この出力変動は電力系統全体の安定性に影響を与える可能性があります。電力システムでは常に需要と供給のバランスを保つ必要があり、急激な出力変動は周波数や電圧の乱れを引き起こすリスクがあります。
対策として、蓄電池との組み合わせや、気象予測に基づく発電量予測システムの開発が進められています。また、複数の分散型電源を統合制御するバーチャルパワープラント(仮想発電所)の技術開発も活発化しています。
初期導入コストの負担
多くの分散型電源は、初期投資コストが高額になる傾向があります。住宅用太陽光発電システムでは100万円以上、燃料電池システムでは200万円以上の初期費用が必要な場合があります。
また、設置後のメンテナンス費用や、機器の更新費用も考慮する必要があります。特に個人や中小企業にとって、これらの費用負担は大きな課題となっています。
政府や地方自治体では補助金制度を設けて導入促進を図っていますが、より一層のコスト削減と支援制度の充実が求められています。
電力系統への影響
分散型電源の大量導入は、既存の電力系統に新たな課題をもたらします。特に配電系統では、従来は変電所から需要家への一方向の電力流れを前提に設計されていましたが、分散型電源からの逆潮流により電圧上昇などの問題が発生する可能性があります。
また、多数の小規模電源を統合的に管理・制御するためには、新しい技術とシステムが必要です。この技術開発と既存インフラの改修には時間と費用を要します。
分散型電源の導入事例と活用方法
実際の導入事例を通じて、分散型電源の具体的な活用方法を見てみましょう。
家庭での活用例
一般家庭では、屋根への太陽光発電システムと蓄電池の組み合わせが最も普及している分散型電源です。昼間に太陽光で発電した電力を自家消費し、余剰分は蓄電池に貯蔵するか電力会社に売電します。
燃料電池システム(エネファーム)を導入する家庭も増えています。都市ガスから水素を取り出して発電し、同時に給湯も行うため、電気代とガス代の両方を削減できます。
電気自動車(EV)も分散型電源として活用できます。自宅で充電したEVの電池から家庭に電力を供給するV2H(Vehicle to Home)システムにより、停電時でも数日間の電力を確保できます。
企業・自治体での活用例
企業では、工場の屋根や遊休地への太陽光発電設置が進んでいます。自家消費により電気代を削減するとともに、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として環境負荷軽減をアピールしています。
病院や福祉施設では、停電時でも機能を維持するため、燃料電池や蓄電池を非常用電源として導入するケースが増えています。通常時は電気代削減効果があり、緊急時は生命に関わる医療機器の電源を確保できます。
自治体レベルでは、マイクログリッド(小規模電力網)の構築が進んでいます。複数の分散型電源と蓄電設備を組み合わせ、地域全体でエネルギーの自給自足を目指す取り組みです。
分散型電源の将来性と展望
分散型電源は今後さらなる発展が期待される分野です。技術革新と政策支援により、その可能性は大きく広がっています。
日本のエネルギー政策との関係
政府が2020年に宣言した「2050年カーボンニュートラル」の実現において、分散型電源は重要な役割を担います。第6次エネルギー基本計画では、2030年度に再生可能エネルギーの電源構成比率を36~38%まで引き上げる目標が設定されており、分散型電源の普及拡大が不可欠です。
また、エネルギー安全保障の観点からも、分散型電源によるエネルギー自給率の向上が重視されています。地域のエネルギー資源を最大限活用することで、海外への依存度を下げることができます。
FIT(固定価格買取制度)からFIP(フィード・イン・プレミアム)への移行により、分散型電源事業者は市場価格に連動した収益構造となり、より経済合理性の高い運用が求められるようになります。
スマートグリッドとの連携
次世代電力網であるスマートグリッドの発展により、分散型電源の価値はさらに高まります。AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術を活用して、多数の分散型電源を統合的に制御し、電力系統全体の最適化を図ることが可能になります。
デジタル技術の進歩により、需要予測や発電量予測の精度が向上し、分散型電源の出力変動に対応できるようになります。また、ブロックチェーン技術を活用した電力取引プラットフォームにより、個人間での電力売買も実現する可能性があります。
蓄電技術の発展も分散型電源の普及を後押しします。リチウムイオン電池のコスト低下や、新たな蓄電技術の実用化により、より安価で高性能な蓄電システムが利用可能になるでしょう。
分散型電源は、エネルギーの民主化とも呼べる大きな変革をもたらします。従来の大規模集中型から小規模分散型への移行により、エネルギーシステムはより持続可能で強靭なものとなり、私たちの生活をより豊かなものにしていくことでしょう。
参照元
・一般社団法人 日本電機工業会
https://www.jema-net.or.jp/energy/dispersed/DER.html
・Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/分散型電源
・パワーアカデミー
https://www.power-academy.jp/sp/learn/glossary/id/1450
・ATOMICA
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2436.html
・EICネット
https://www.eic.or.jp/ecoterm/index.php?act=view&serial=4340