私たちが豊かな生活をおくる裏では、自然環境に大きな負荷がかかっています。
どれほど負荷がかかっているのか数値化もされており、現在この数値が世界的に上昇傾向にあり、問題となっているのです。
本記事では、エコロジカル・フットプリントの計算方法や日本と世界の現状・SDGsとの関係性などをまとめました。
エコロジカル・フットプリントとは

引用元:WWF 日本のエコロジカル・フットプリント2015|WWFジャパン
エコロジカル・フットプリントとは、人間の消費活動が、どのくらい地球環境の負担になっているのかを表す数字です。数字が高くなるほど、地球への負荷が大きいことを表しています。
また先進国と途上国では、経済的に発展している先進国の方が、エコロジカル・フットプリントが高くなり、途上国の3~4.5倍(1人あたり)になるそうです。
エコロジカル・フットプリントの計算方法
エコロジカル・フットプリントの計算方法は下記の通りです。
人口×1人あたりの消費量×生産・廃棄効率=エコロジカル・フットプリント
この計算によって、人間の消費活動が原因で起きた環境負荷をカバーするために、必要な土地や水域の面積がわかります。
また環境負荷の原因としては、
・二酸化炭素やメタンなど温室効果ガスの排出
・森林伐採
・石油や鉱物など資源の過剰利用
・魚の過剰捕獲
などが挙げられます。
参照元:日本のエコロジカル・フットプリント2015|WWFジャパン
バイオキャパシティとオーバーシュート
私たちの生活が、地球環境にどれほどの負荷を与えているのか確認するためには、エコロジカル・フットプリント以外に、「バイオキャパシティ(生物生産力)」も知る必要もあります。
バイオキャパシティとは、1年間に自然資源を再生産し、廃棄物(主に二酸化炭素)を吸収するために、どのくらいの土地や水域が必要か面積で表したものです。
エコロジカル・フットプリントと比較することによって、私たちの生活が地球環境に、どれほどの負荷を与えているのかが分かります。
また、生態系サービスの供給量を指す言葉でもあり、下記の4つに分類されています。
| 供給サービス | 食料や水、医薬品、木材、衣類など、人が生きていくうえで必要なものは、生態系サービスから得ている。 |
| 調整サービス | 空気や水の浄化、気候の調整、自然災害からの保護など。 |
| 文化的サービス | 生態系サービスの中でも、文化や物事の考え方に大きな影響を与えたり、芸術活動のモチーフになったりするもの。 ハイキングやお花見など、レクリエーション活動の機会をつくること。 |
| 基盤サービス | 生態系サービスの基盤となるもの。植物の光合成、微生物や昆虫による土壌の形成、水の循環など。 |
このように、私たちは多くの生態系サービスの恩恵を受けて暮らしています。
しかし、自然資源は無限にあるわけではありません。
そのため、1年間に供給できる量を超えてしまうと「オーバーシュート」という状態になります。
そして地球は、1970年以降からオーバーシュートの状態が続いているのです。
参照元:
・生態系サービス|生物多様性センター(環境省自然環境局)
・生態系サービスとは|JEEF公益社団法人日本環境教育フォーラム
・エコフットとは|特定非営利活動法人 エコロジカル・フットプリント・ジャパン
エコロジカル・フットプリントの世界と日本の現状

ここからは、エコロジカル・フットプリントの世界と日本の現状を確認していきましょう。
世界
Global Footprint Networkによると、2022年時点で各国のエコロジカル・フットプリントの状態は下図の通りです。
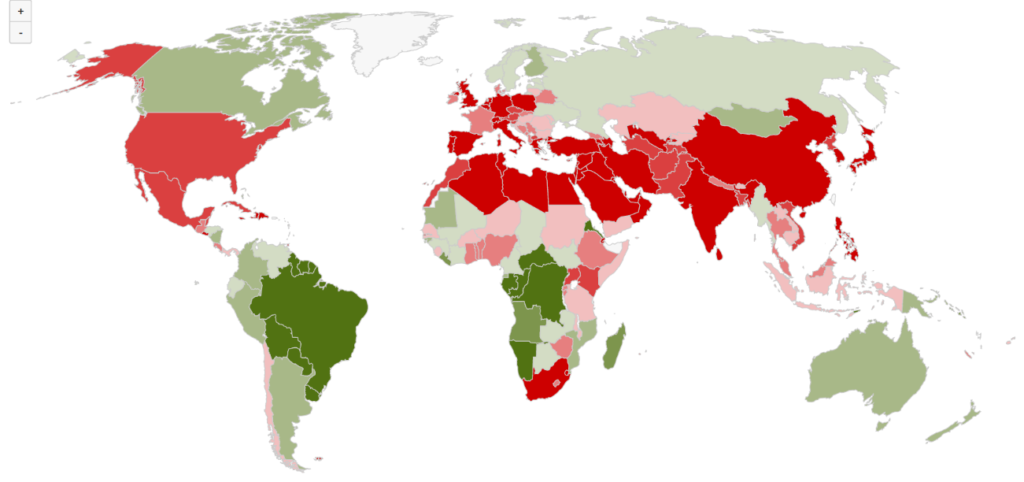
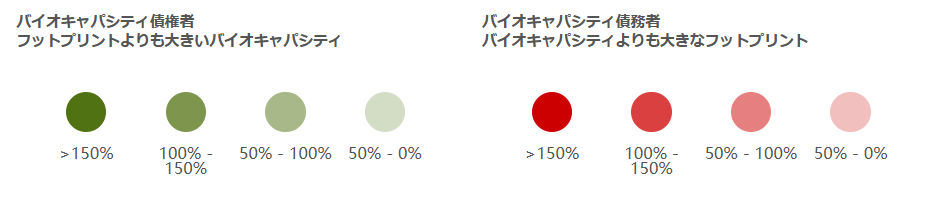
赤色は、エコロジカル・フットプリントがバイオキャパシティを上回っている国。
対して緑色は、バイオキャパシティ内に収まっている国です。
色の濃さは、双方の傾向の強さを表しています。
「赤色が濃ゆいほど、エコロジカル・フットプリントが大きい=地球に負荷がかかっている」ということです。
そして、エコロジカル・フットプリントの高い上位5カ国は下記の通りです。
| 1位 中国 | 5,540,000,000 |
| 2位 アメリカ合衆国 | 2,660,000,000 |
| 3位 インド | 1,640,000,000 |
| 4位 ロシア連邦 | 774,000,000 |
| 5位 日本 | 586,000,000 |
※単位:gha(グローバルヘクタール)
超大国と呼ばれる中国やアメリカに加え、経済成長が目まぐるしいインド、世界最大級のエネルギー資源産出国であるロシアなどの名前が並ぶなか、5位には日本が入っています。
つまり日本は、世界で5番目に環境負荷をかけている国ということになるのです。
日本
現在、日本の1人あたりのエコロジカル・フットプリントは4.7gha。
世界平均が1.7ghaのため、世界の2.8倍利用していることになります。
また、都道府県別に1人あたりのエコロジカル・フットプリントを見ると、東京都が最も高く、山梨県が最も低い結果となりました。
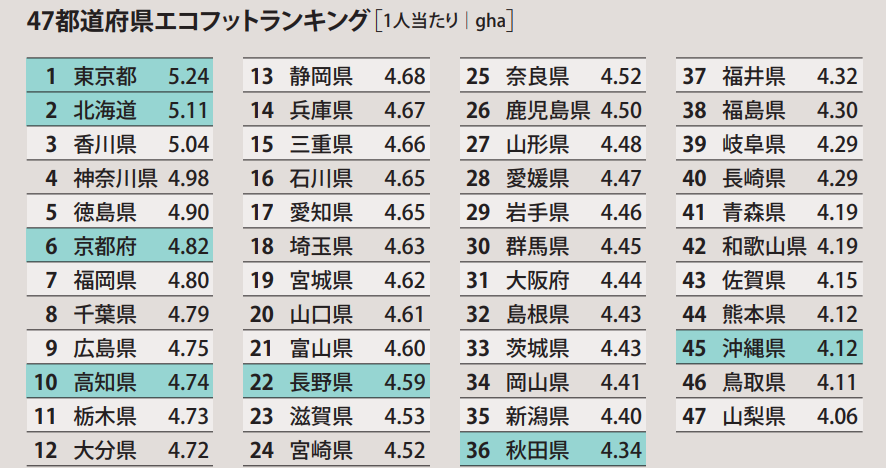
世界のエコロジカル・フットプリントより2.8倍も高い日本ですが、1人あたりのバイオキャパシティは0.6ghaしかありません。
不足分は、世界のバイオキャパシティに頼っているのが現状です。
そのため世界の自然資源が減少すると、日本は現在の暮らしを維持できなくなるでしょう。
また日本は、食料や住居・光熱費、交通など家計に関する消費活動が、エコロジカル・フットプリントの70%を占めています。
つまり、この部分を改善するとエコロジカル・フットプリントの削減につながるのです。
エコロジカル・フットプリントを減らすための取り組み

続いては、エコロジカル・フットプリントを減らすために、行っている取り組み例を見ていきましょう。
環境保全に取り組む団体「WWFジャパン」によると、下記の3つの矢が重要だと話しています。
FSCやMSCのように環境負荷の少ない認証製品を選択する
FSCやMSCとは、貴重な水産資源と森林資源を環境負荷の少ない持続可能な方法で、収穫・流通していることを示す認証マークです。
認証マークの製品を選び購入する人が増えることによって、エコロジカル・フットプリントの削減に貢献できます。
生産時に投入する資源の量や、廃棄物の量を削減する
食品ロスがゼロになると、エコロジカル・フットプリントを20%削減できるとも言われています。
そのため、1人ひとりが食品ロス対策に取り組む必要があります。
例えば、「必要な分だけ食品を購入する」や「消費期限を確認し、計画的に使用する」「食品が長持ちするように、適切な方法で保存する」などです。
効率よく資源を活用するための技術革新の推進や支援
太陽光発電や風力発電のように、発電時に二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーの導入。
資源を効率よく活用するための研究開発や、開発する研究機関・企業への支援も重要です。
エコロジカル・フットプリントとSDGs

エコロジカル・フットプリントを減らすことによって、SDGsの目標達成に貢献すると期待されています。
関係性を確認する前に、まずはSDGsについておさらいしましょう。
SDGsを簡単におさらい
SDGsとは、2015年に開催された国連総会にて、193の加盟国が賛同した国際目標です。
2030年までに、環境・社会・経済の課題解決を目指し、17の目標と169のターゲットが設定されました。
そして目標の中でも、目標6「安全な水とトイレを世界中に」、目標12「つくる責任つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」との関わりが深いと言われています。
今回は、特に関わりの深い目標12について見ていきましょう。
目標12「つくる責任つかう責任」
SDGs目標12は、持続可能な消費と生産を確実にすることが目的です。
そのため、食品ロスの削減や天然資源の管理・調達方法など、あらゆる分野のターゲットが設定されています。
先述した通り、日本のエコロジカル・フットプリントは70%が家計消費活動です。
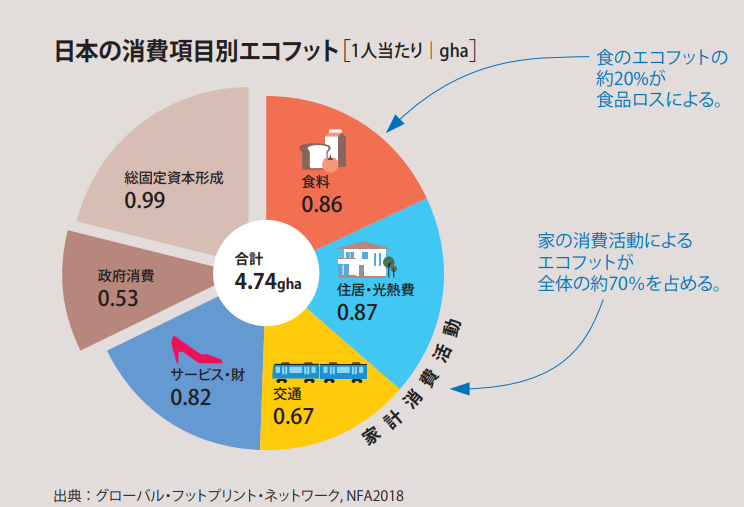
例えば、食料の項目を見ると、原因の約20%が食品ロスとなっています。
つまり、食品ロスをゼロに近づけることができれば、エコロジカル・フットプリントの削減につながり、目標12の達成にも近づくのです。
その他にも、削減のためには「地球温暖化対策」も重要だと言われています。
再生可能エネルギーの活用やプラスチック製品の使用を控えるなど、二酸化炭素の排出量を減らす工夫をすることが大切です。
まとめ

現在、日本は世界で5番目に環境負荷をかけている国です。
そのため、他の国よりもエコロジカル・フットプリントの削減に対して、積極的に取り組まなければいけません。
まずはエコロジカル・フットプリントについて知識を深め、日本の現状を知り、一人ひとりが無理のない範囲で、できることから行っていきましょう。





